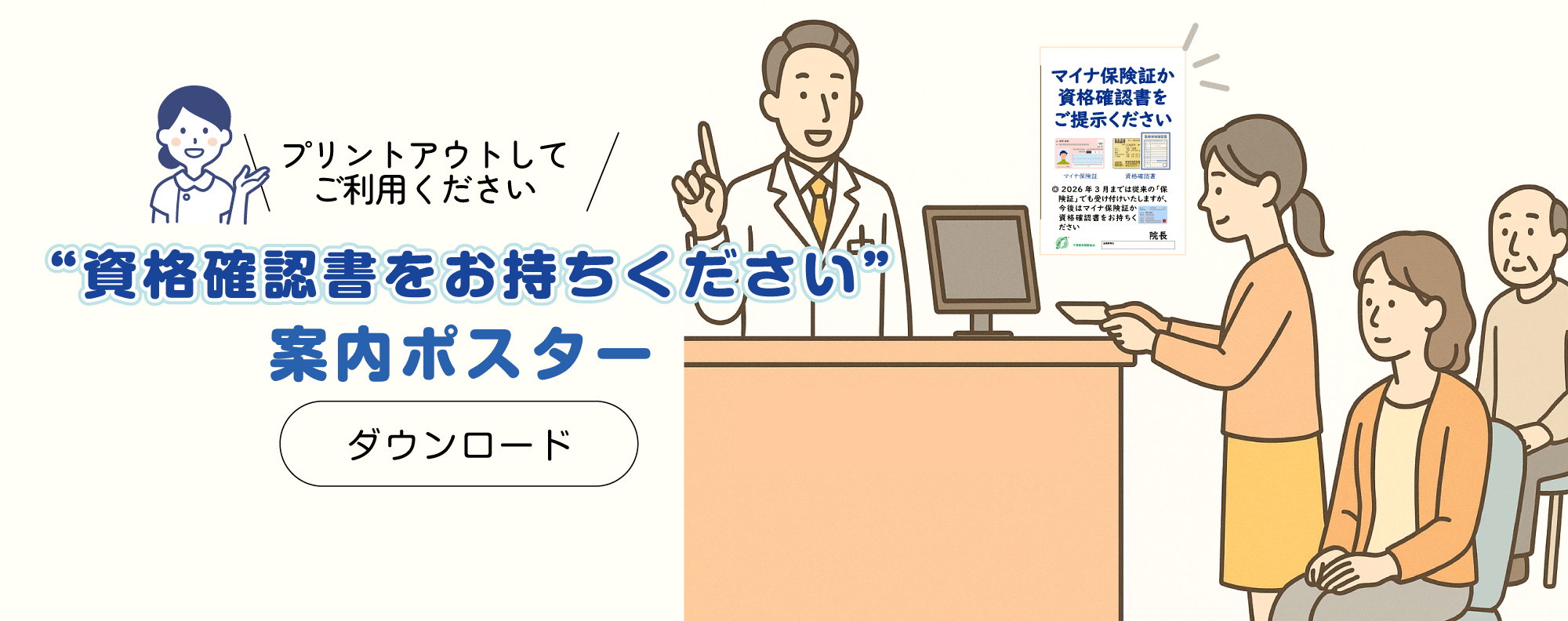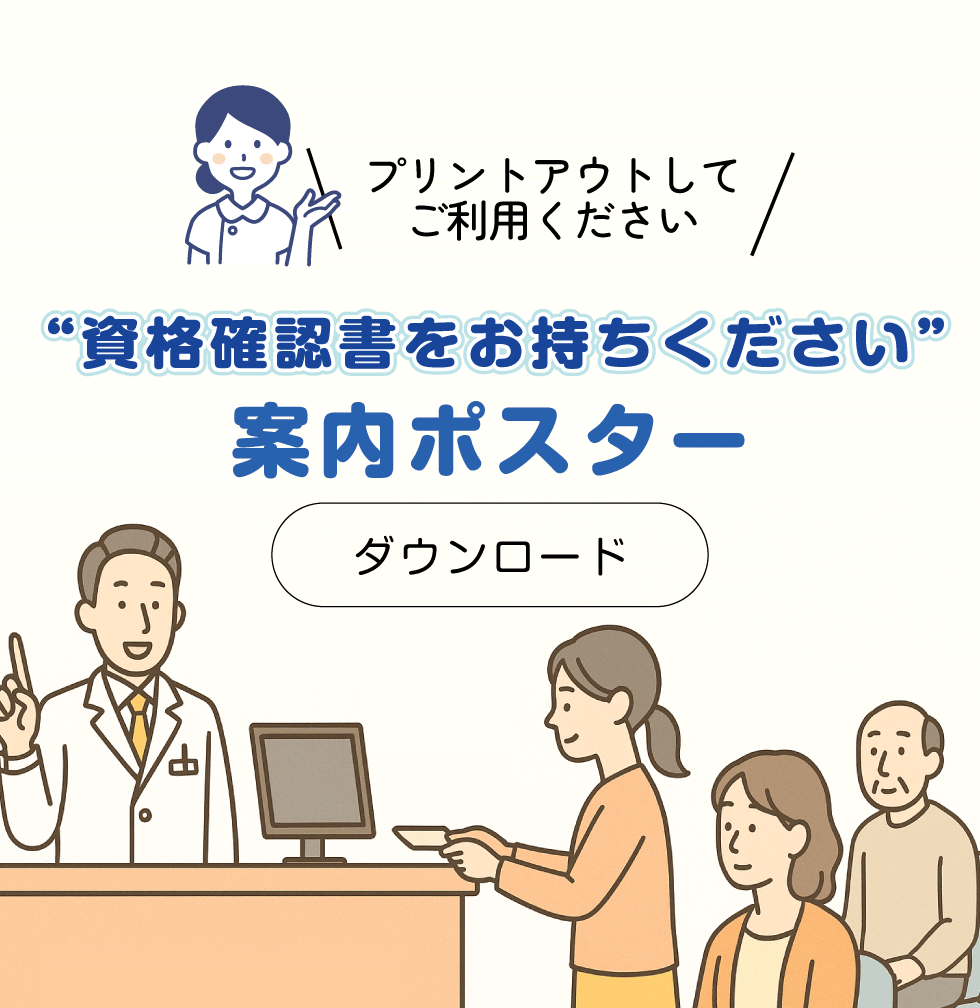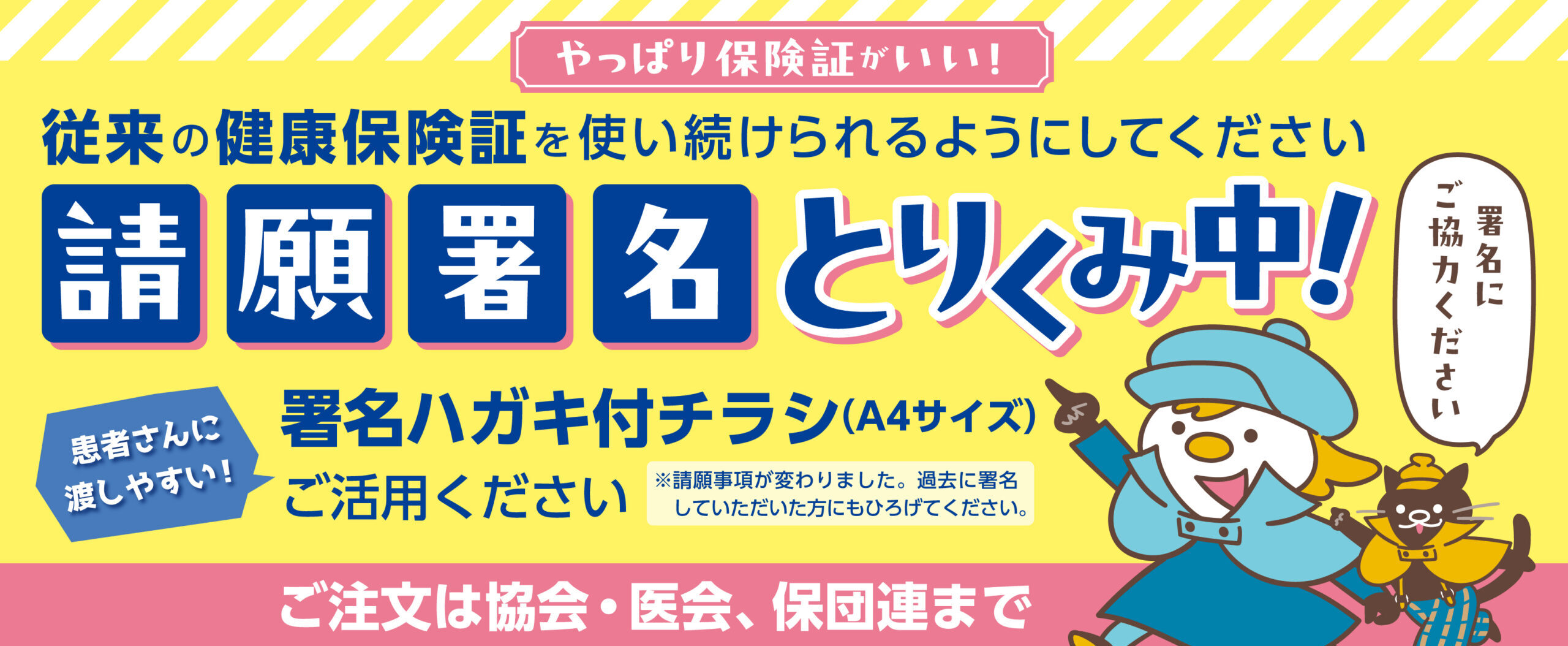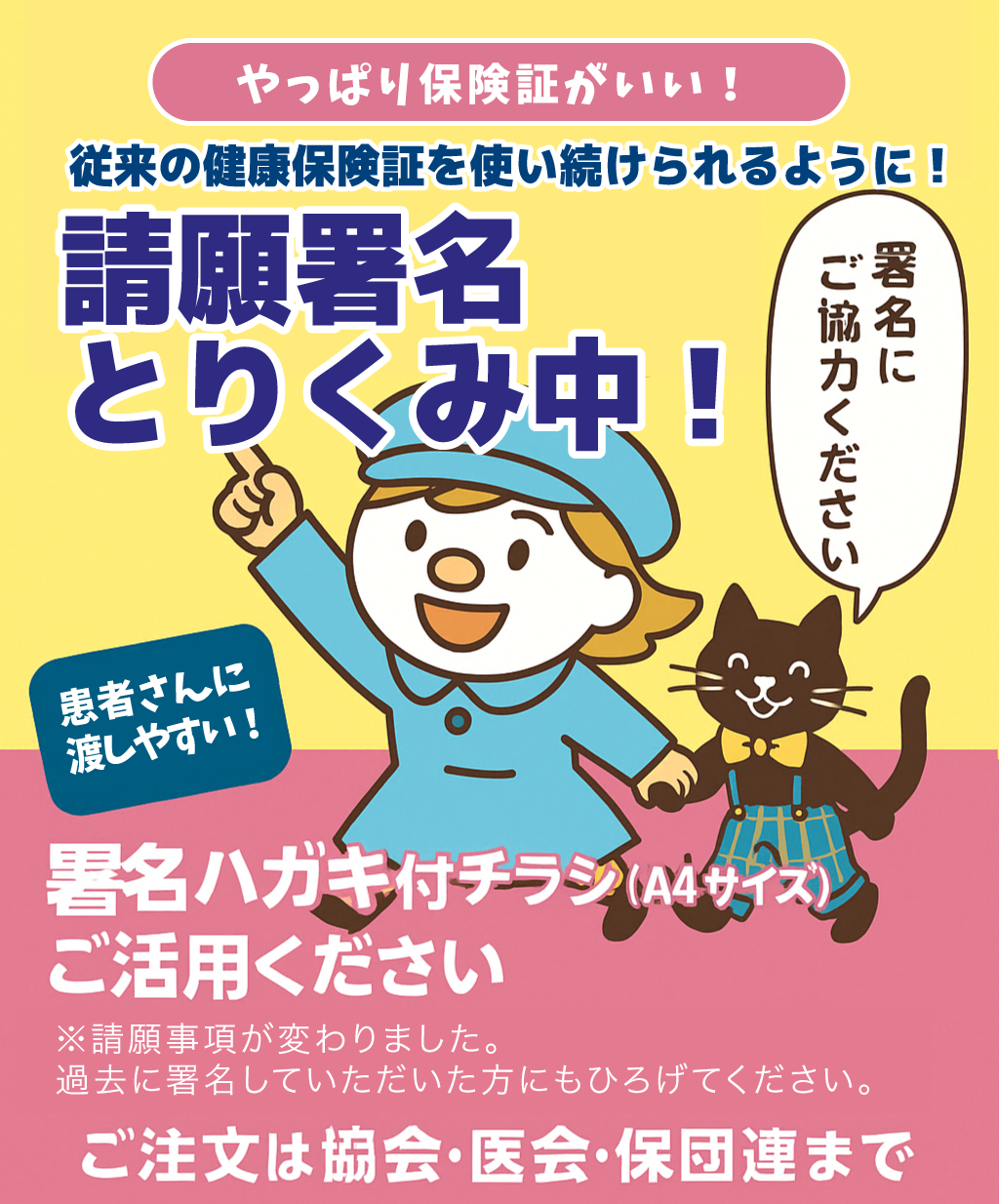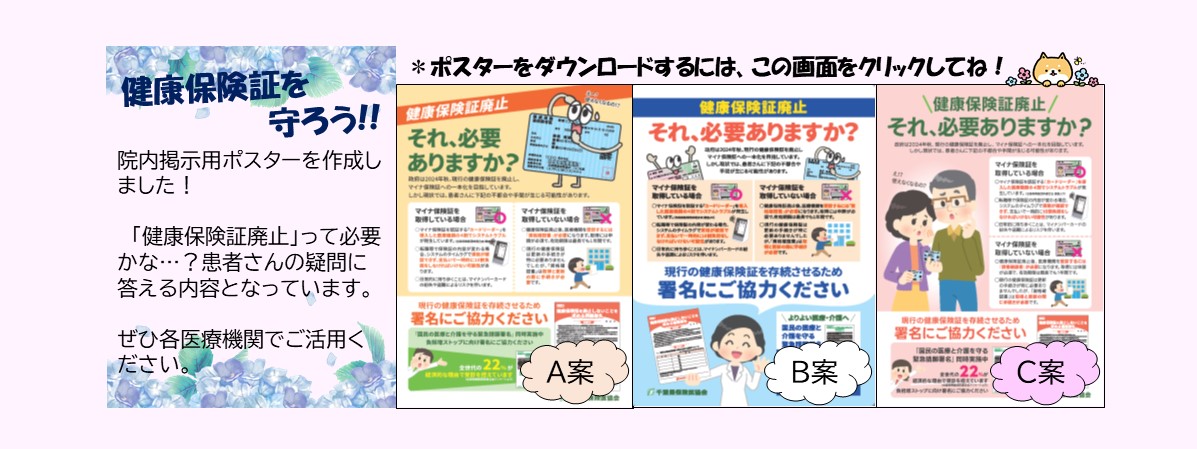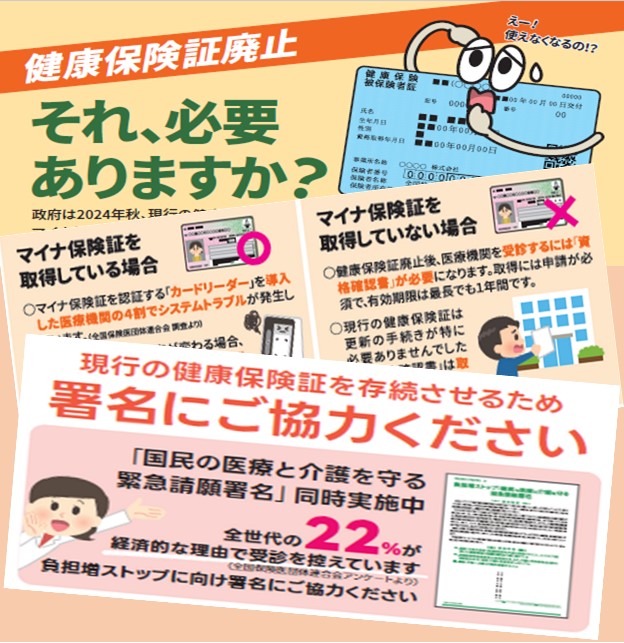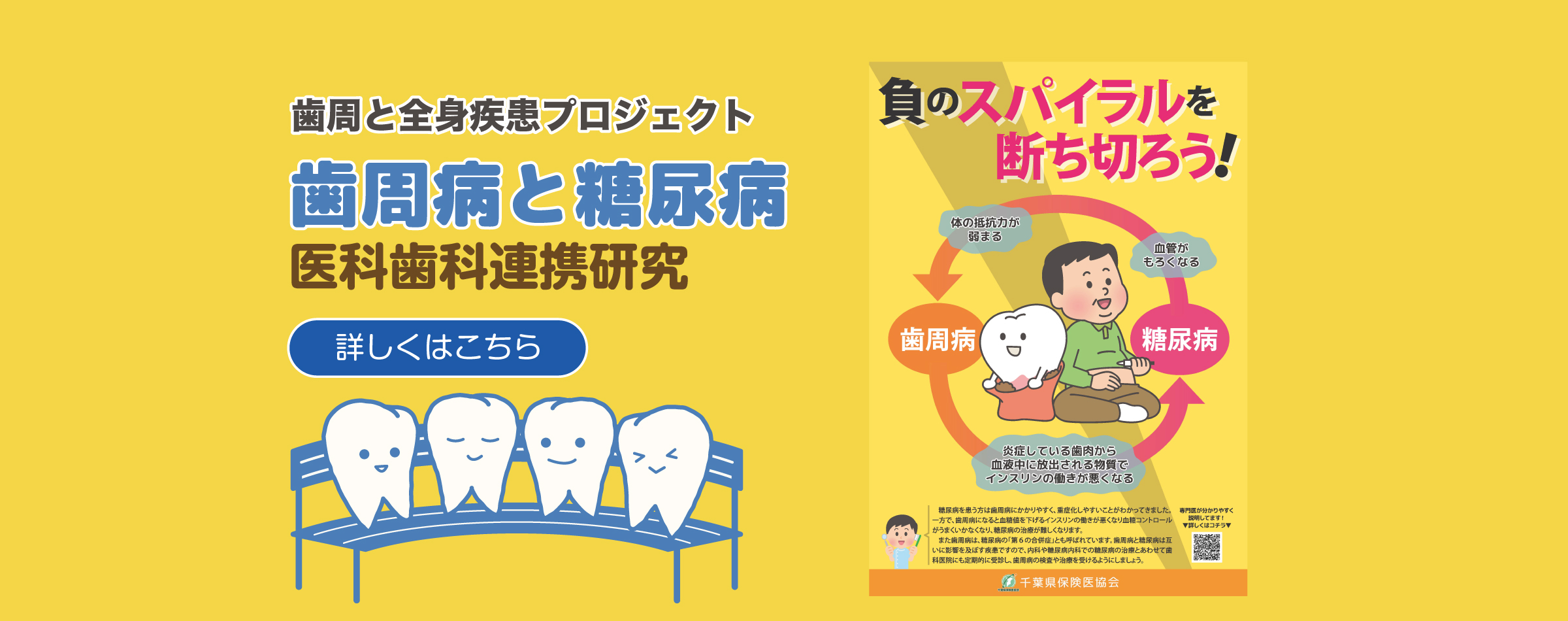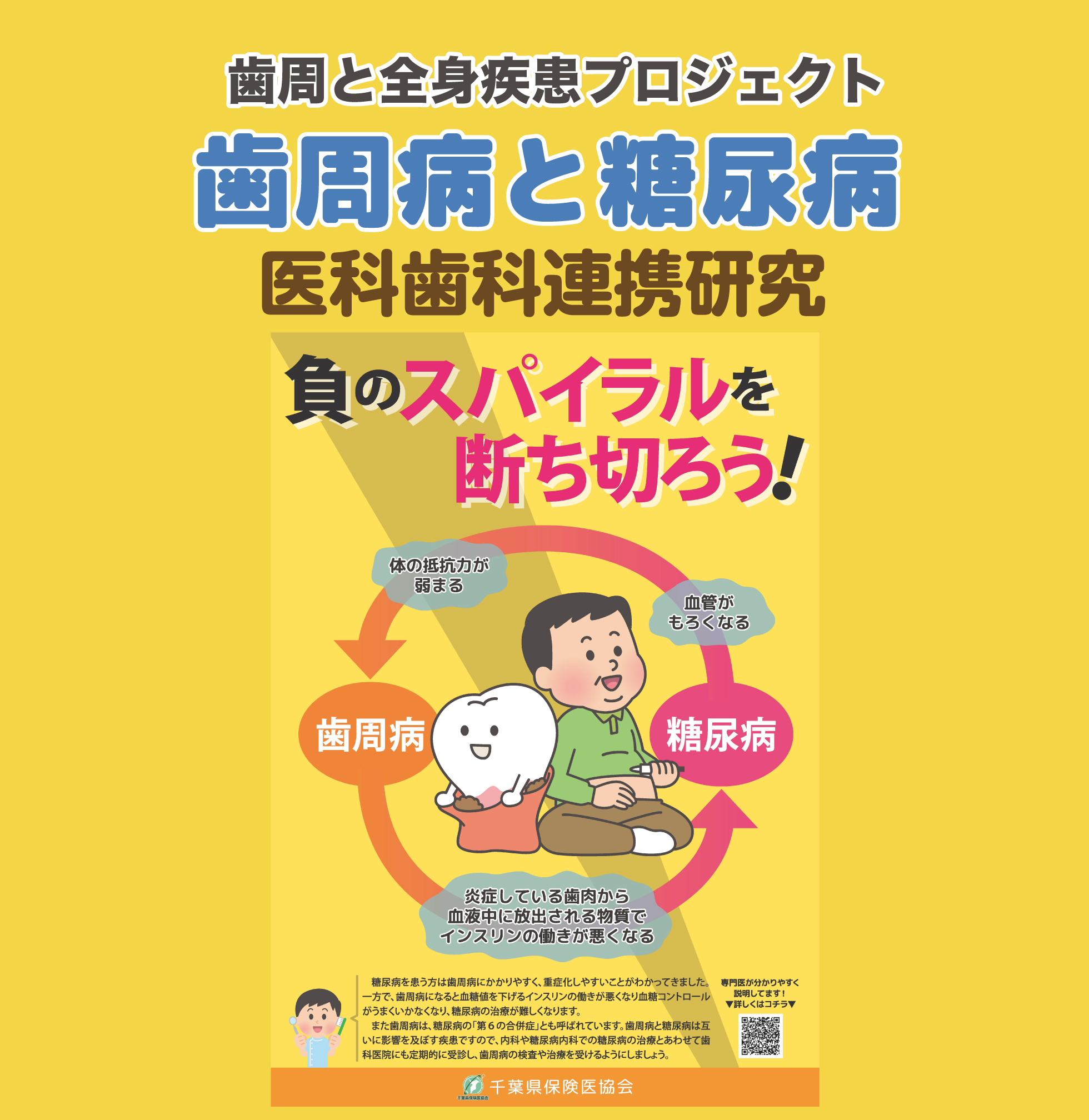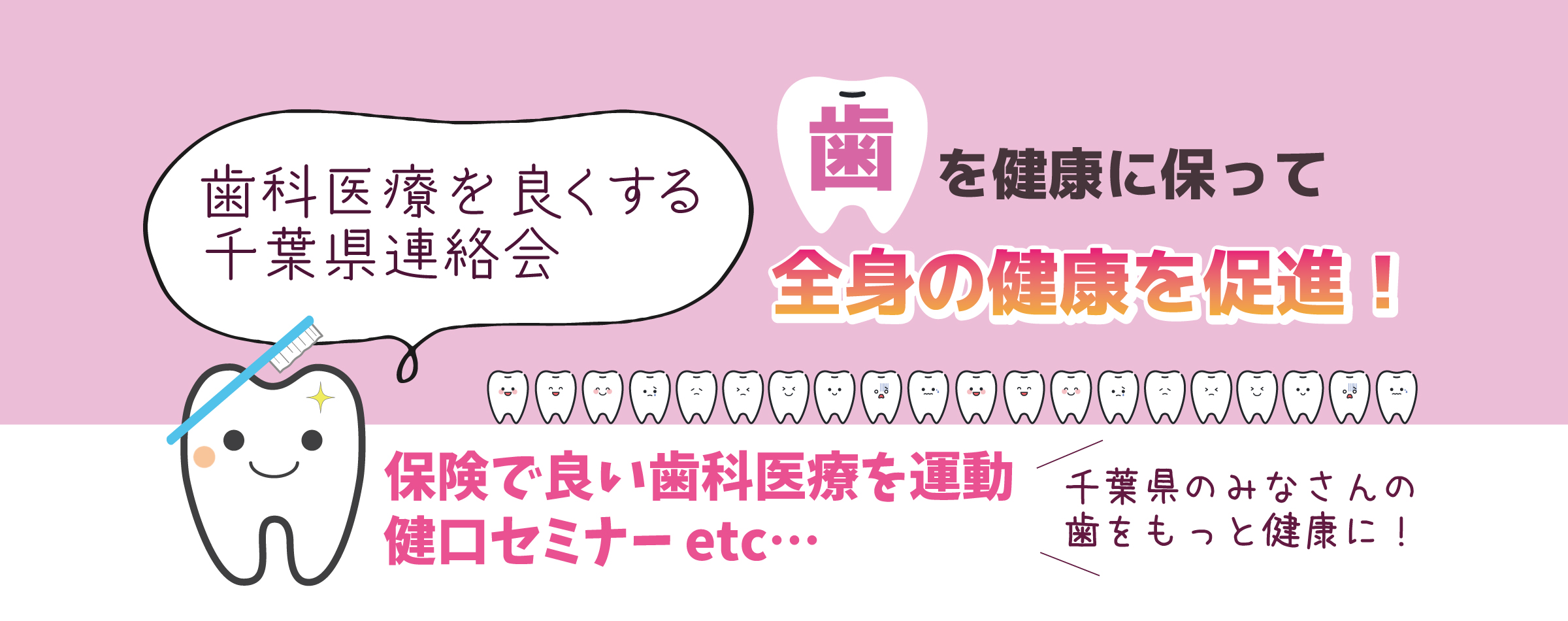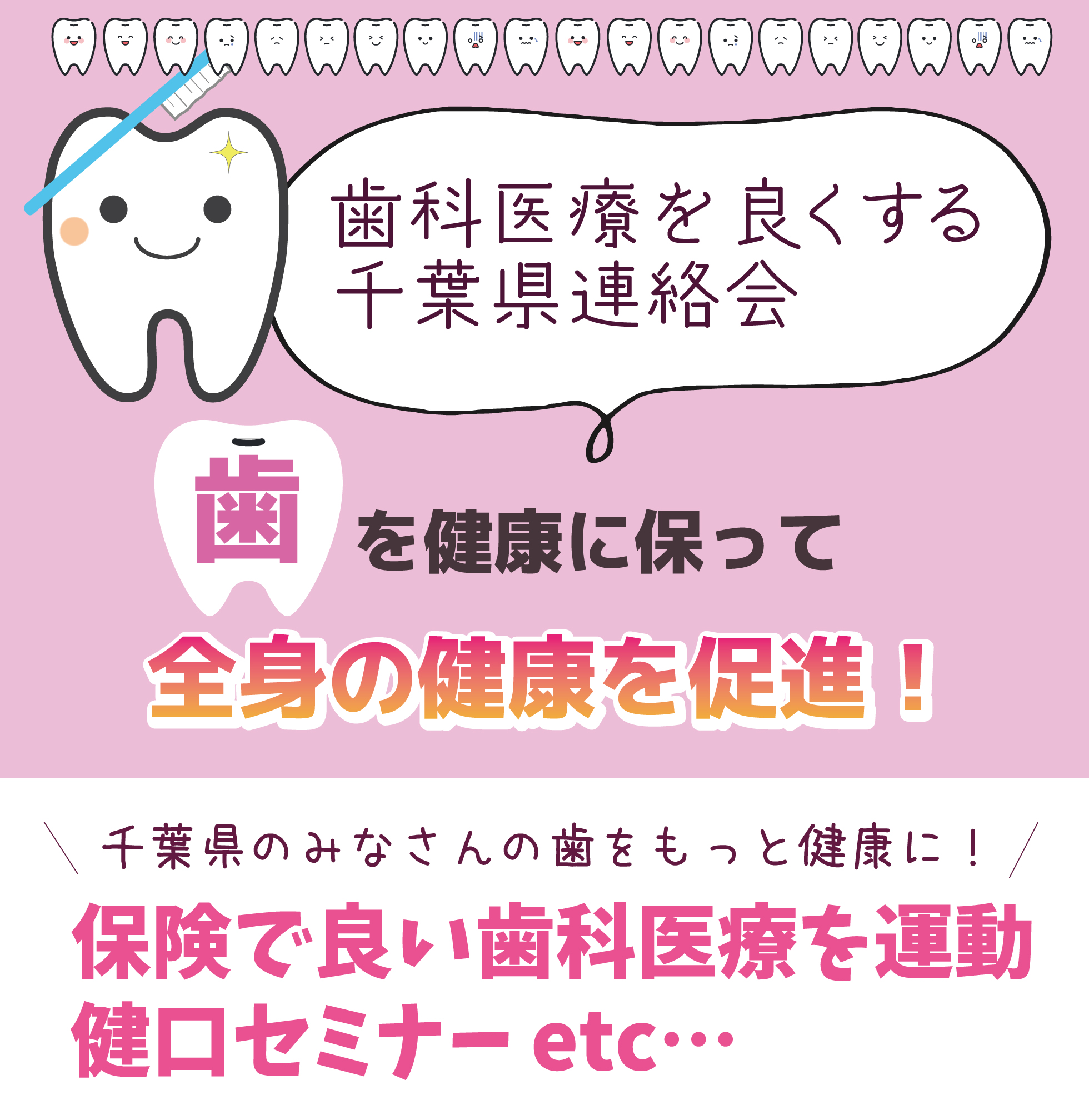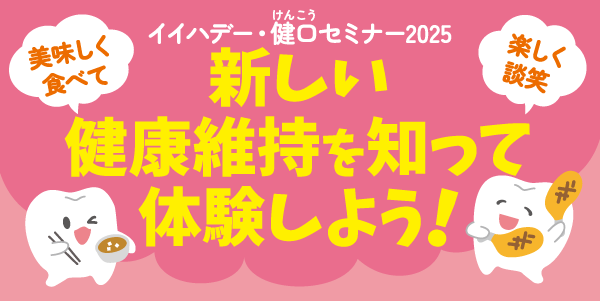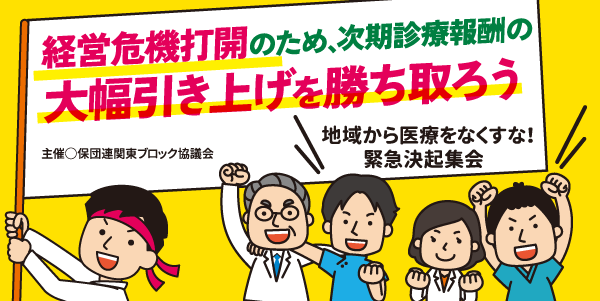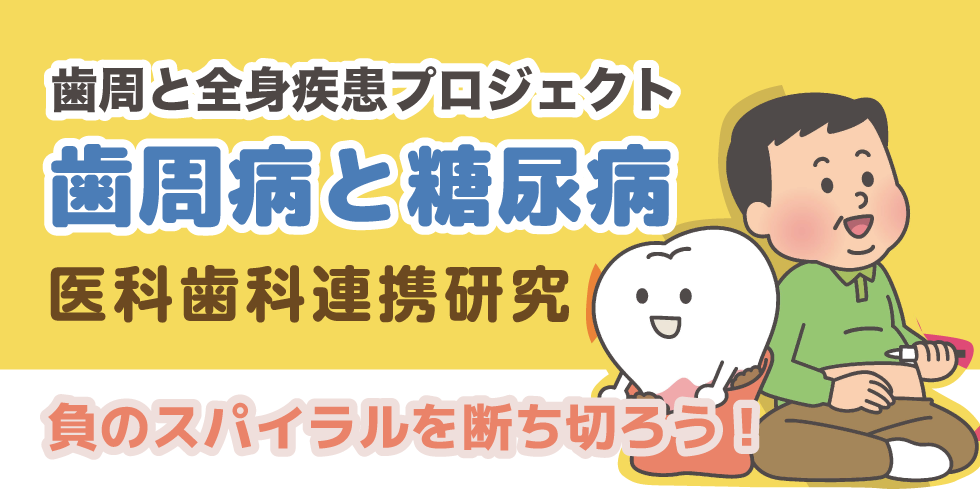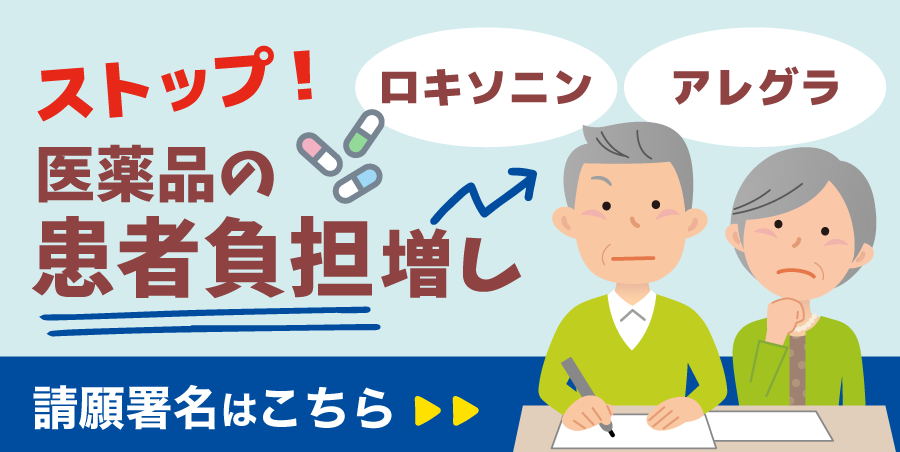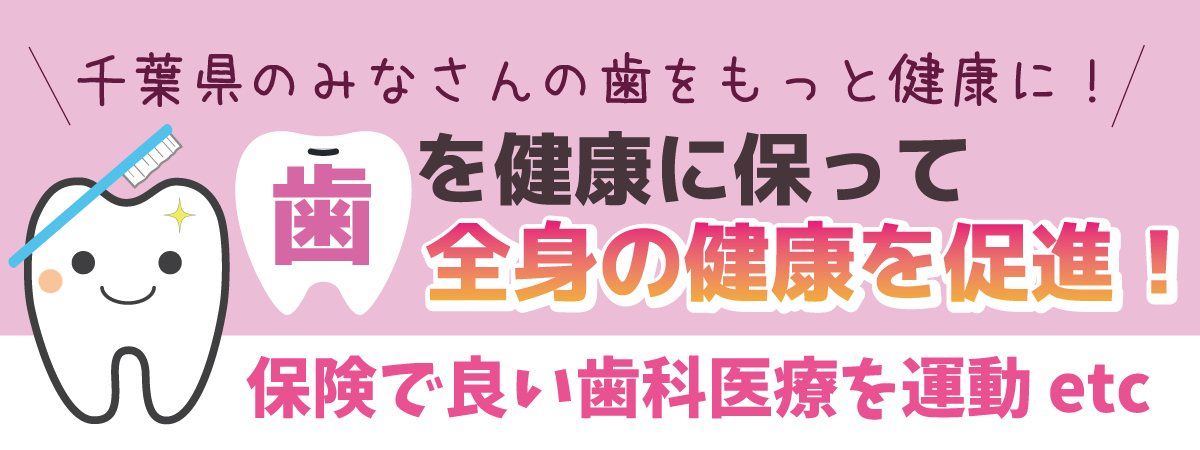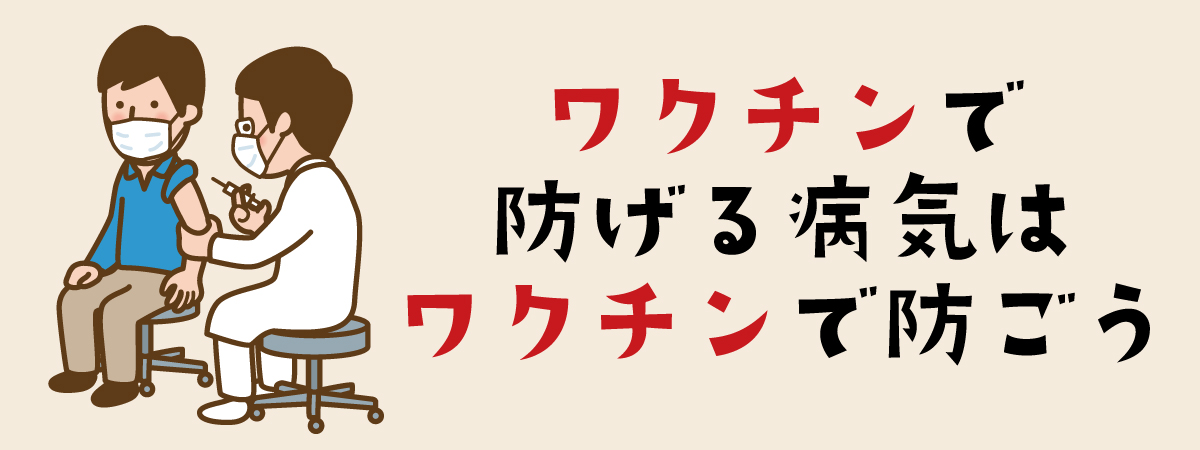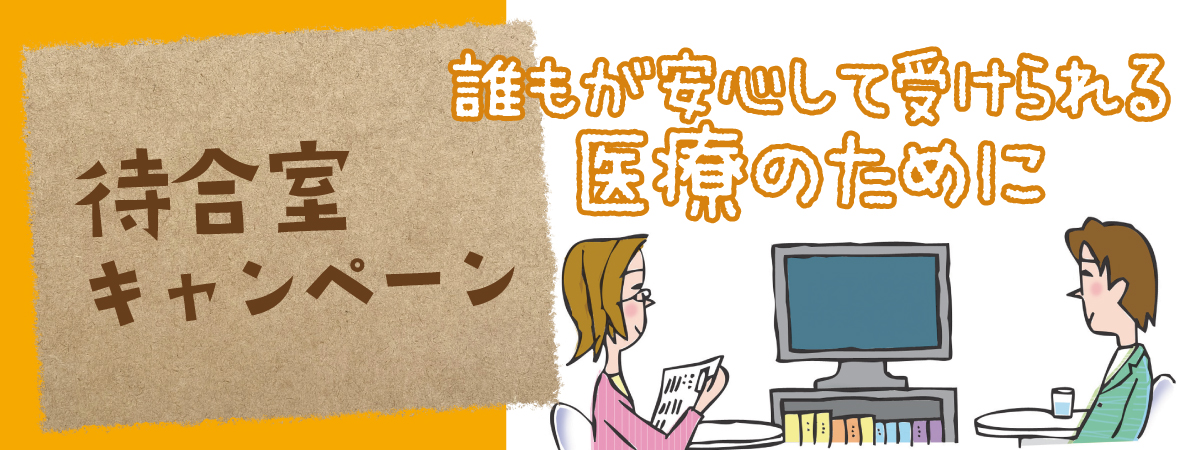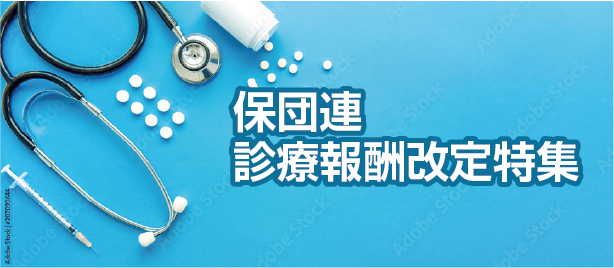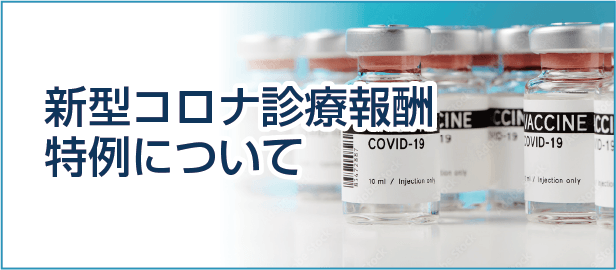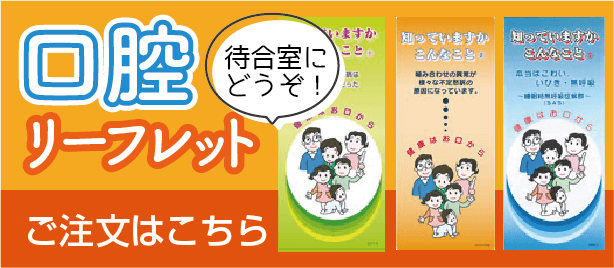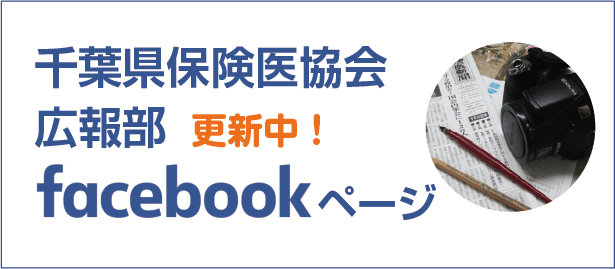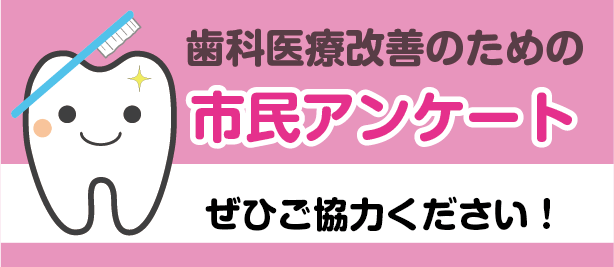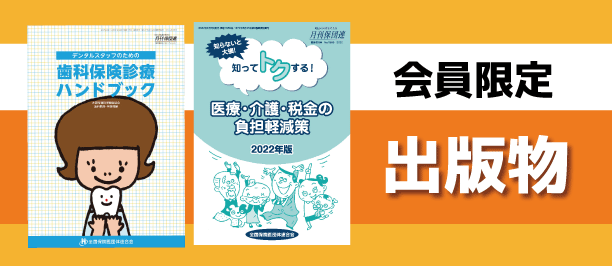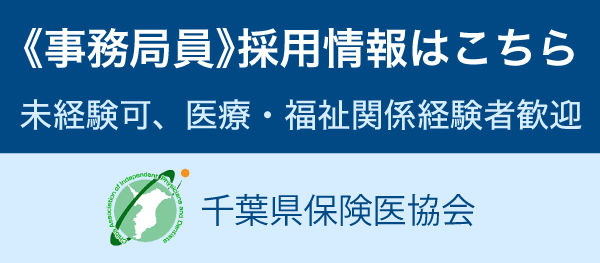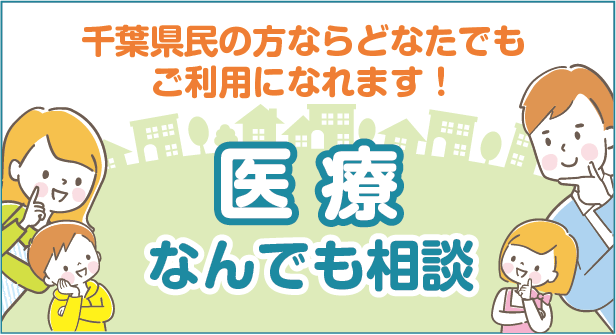新着情報
- 2026/02/22
- ちょっと待った!OTC類似薬保険外し ストップ!患者負担増請願書名にご協力ください。NEW!
- 2025/12/29
- 【談話】医療機関の経営実態に配慮しない2026年度診療報酬改定率に抗議する
- 2025/12/17
- 【重要】令和7年度「かかりつけ医機能報告」定期報告について
- 2025/12/14
- 《資格確認書をお持ちください》院内提示用・案内ポスター・A4チラシダウンロードはこちら
- 2025/11/27
- 千葉県から【第一種・第二種協定指定医療機関あて連絡した留意事項】のご連絡
現在、会員数4,251名(23年10月1日現在)保険医の生活と権利を守る取り組みを行っています。
千葉県保険医協会は、保険医の生活と権利を守り、国民医療の向上をはかることを目的として1972年(昭和47年)に誕生しました。
診療報酬請求、患者さんとのトラブル、税務関連、法律相談、共済制度への加入など、医院経営全般のご相談に対応しています。
レセプトに関して不明な点や疑問があるとき
患者さんとのトラブル、 または紛争が起きそうなとき
個別指導・監査や税務調査があるとき
税務・労務管理でわからないことがあるとき
共済制度へ加入したいとき
法律相談を受けたいとき
協会に入るメリット
協会のメリットとは、ひと口に言って、全ての活動が開業保険医に直接役立つ活動であるということです。
そしてその全ての活動に、先生方が自由に参加し、自由にものが言えるということです。
このことを前提に、協会ではこれからご紹介するような色々な事業を行っています。すべてが開業保険医の診療とくらしに必要なことばかりなので、協会のサポートをどんどんご利用いただき、メリットを先生ご自身でつかみ取って下さい。
協会の事業がここまで広がったのも、実は先生方の強いご要望とご支援があったからです。
声明・主張・談話すべての記事を見る >
- 2026.01.09 令和7年度一般会計補正予算事業の速やかな実施、 令和8年度予算策定で医療機関への継続的財政措置を
千葉県知事 熊谷 俊人 殿
千葉県保険医協会
会長 岡野 久
税経労務対策部長 森下 尚吾貴職におかれましては、千葉県民の健康増進、医療・歯科医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。
当会は、県内4,206名の会員で構成する医科、歯科の保険医の団体として、保険医療の充実、県民の健康向上のための様々な活動に取り組んでいます。
25年12月24日、診療報酬の改定率は+3.09%となりました。うち賃上げ分+1.70%、物価分+0.76%とされています。しかし、地域の医療機関の実情をみるとプラス改定とはいえ、不十分なものであると言わざるを得ません。全国保険医団体連合会や病院団体は、少なくとも10%以上のプラス改定を求めていたところです。
当会で取り組んだ医師・歯科医師要請署名には「物価高騰、人件費高騰により経営が厳しい状況です。診療報酬の引き上げを強く希望いたします」、「50年の長い間ご通院頂いた患者さん方も亡くなられたり、ご高齢で通院出来ない上、変な保険証改定や制度でさらに口腔内が悪化しております。担当歯科医師も最新の制度に合わず、1年以内に閉院を予定しています。医療崩壊残念!」など切実な声が寄せられ、閉院や廃院を考える医療機関も多く、苦しい経営状況が見えます。
重点支援地方交付金を用いて、これまで多くの自治体で医療機関への支援金、助成金が措置されてきたことは、医療機関と地域医療の支えとなっています。医療機関を取り巻く昨今の厳しい状況と著しく不十分な今回の診療報酬改定を踏まえると、引き続き、支援や助成の実施と対象範囲、規模の拡充が必要です。
千葉県におかれましては、25年12月23日に補正予算を編成し専決処分を行いました。
重点支援地方交付金を活用し早急に病院・診療所の別、医科・歯科の別を問わず医療機関に対する支援を実施していただきますよう、下記の通り要望いたします。記
- 令和7年度一般会計補正予算における事業について、千葉県内全ての医療機関を対象に迅速かつ簡便な手続きで実施すること。
- 令和8年度当初予算を策定するにおいて、千葉県内全ての医療機関を対象に県独自の補助金制度を設け、支援を継続すること。
以上
- 2026.01.15 急騰する歯科鋳造用金銀パラジウム合金の保険償還価格を 緊急改定することを強く求める
厚生労働大臣 上野 賢一郎 殿
千葉県保険医協会
会長 岡野 久
保険部長 石毛 清雄昨今の金・銀の相場価格の高騰を受け、歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金パラ)の価格も急上昇し、歯科医療現場は深刻な事態に陥っている。
メーカーにより価格差はあるものの、2026年1月5日時点で、とあるメーカーの金パラは30g税込み169,840円にまで高騰している。1gあたり5,661円で、保険償還価格は1g3,802円のため、グラム当たり1,859円の大幅な「逆ザヤ」が発生している。
大臼歯の金属冠を作製する場合、約3.5gの金パラを使う。金属代だけで19,813円かかるが、保険で償還される金属代は13,307円、歯科医院が6,506円もの大幅な持ち出しとなる。
厚生労働省は価格高騰に左右されない非金属歯冠修復の適用を拡大させてきた。
しかしCADCAM冠や高強度レジンブリッジなど、非金属材料による歯冠修復・欠損補綴はすべてのケースに適用できるわけではなく、歯科保険医は大幅な赤字を抱えることになっても金パラを使わざるを得ないケースが多く発生している。
非金属歯冠修復の適用拡大では対処できないケースも存在するのが現実だ。そこにこの間の価格急騰である。3月には随時改定、6月には基準材料価格改定を控えているが、もともと低診療報酬に苦しんでいる歯科保険医も多く、今回の大幅な「逆ザヤ」でさらに大変な苦境に陥っている。3月まで待つ余裕などない。
現在、経営体力のない歯科医院は倒産の危機にある。現状を放置してはならない。2022年5月のウクライナ危機の際と同様に、今回も保険償還価格の緊急改定を行うよう強く求める。
- 2025.12.29 【談話】医療機関の厳しい経営実態に配慮しない改定率に抗議する
地域医療の崩壊を食い止めるため、10%以上プラス改定を強く求める
千葉県保険医協会
会 長 岡野 久厚生労働省は 12 月 24日、2026年度診療報酬改定を発表した。「本体」部分を3.09%、「薬価等」を-0.8%、全体で+2.22%のプラス改定となった。本体部分のプラス改定は協会・保団連や多くの医療団体の粘り強い働きかけにより1996 年以来30年ぶりの水準へとつながったと一定評価されるが、この間の物価人件費の上昇や24年度改定で減収に追い込まれ厳しい医院経営状況を補う改定率にはなっておらず、医療界が求めてきた10%以上の引上げとは程遠い内容となっている。当会は医療機関の厳しい実態に配慮しない2026年度改定に抗議すると共に、地域医療の崩壊を食い止めるため、期中を含めた更なる改定を強く求めるものである。
■「賃上げ対応+1.07%」でも、人事院勧告(2025 年度)ベアに見合わず
本体部分 3.09%の内訳として、「賃上げ対応」に+1.07%、今後 2 年間の「物価対応分」に+0.76%、過去2 年間の「経営環境の悪化緊急対応分」に+0.44%、「入院時食費・光熱水費分」に+0.09%、 「後発医薬品、処方箋料等・在宅医療関係の適正化、長期処方・リフィル処方の取組み強化」は▲0.15%、 それ以外の 「政策改定」(使途を限定しない分) に+0.25%、薬価▲0.86%、材料価格で▲0.01%の計▲0.87%、全体で+2.22%となった。中でも「賃上げ対応」に+1.07%をあて、26 年度、27 年度でそれぞれ 3.2%分のベースアップ(看護補助者・事務職員は同 5.7%)を支援するとされているが、それでも人事院の給与勧告(2025 年)の3.62%よりも低い。
今でも医療関係職種(医師、歯科医師除く)の月給与平均(2024 年度)は産業全体を 5%弱下回っており、このままでは離職の抑制、人材確保は困難である。少なくとも 10%程度の賃上げが可能となるよう、財源の抜本的な上乗せが急がれる。
■届出制ではなく、すべての医療機関で賃上げ可能とする基本報酬引き上げを
また、煩雑な事務を要するため、ベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、医科診療所の4割、歯科診療所の3割半ばに留まっており、届け出による算定を前提とせず、すべての医療機関(医療従事者)において賃上げが可能となるよう、 「賃上げ対応」は初診料、再診料、入院基本料など基本報酬の引き上げで行うべきである。
■医療機関の閉院・廃止が加速、医療過疎・無医、無歯科医地区拡大の恐れ
今回の使途を限定しない「政策改定」は+0.25%であるが、「後発品等適性化・効率化」は▲0.15%であり、わずか+0.1%の財源によって疲弊した医療機関の経営悪化を改善は望めず、医科診療所においては実質マイナス改定となることが危惧される。このままでは地域の社会資源である医療機関の閉院・廃止が加速し、医療過疎・無医、無歯科医地区が拡大する恐れがある。当会は2026年診療報酬改定に抗議するとともに、更なる10%以上の改定を求めるものである。
以上