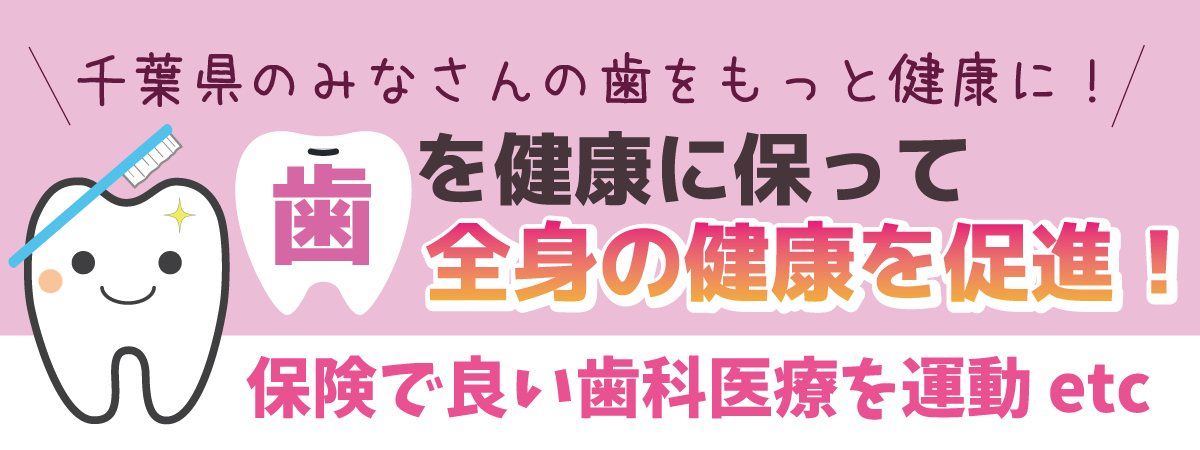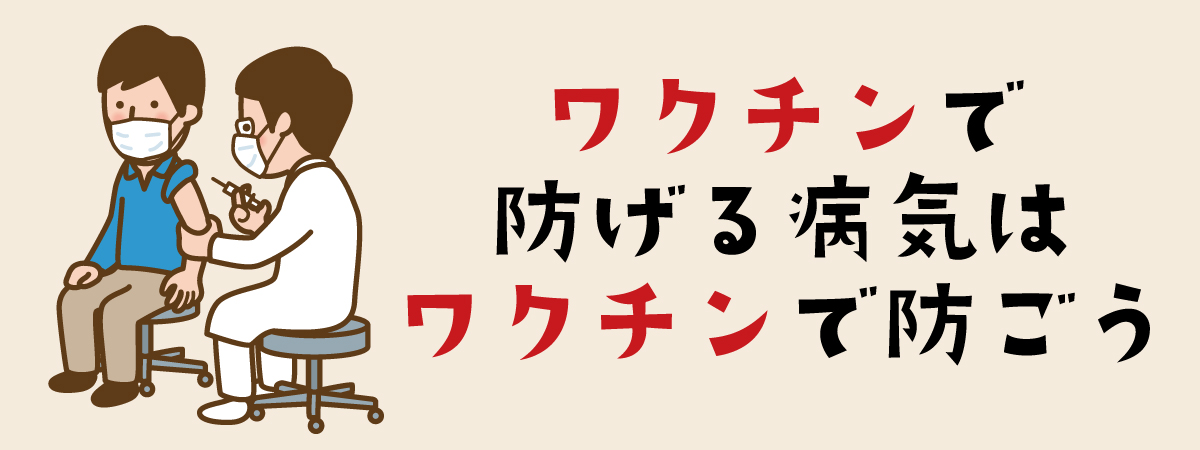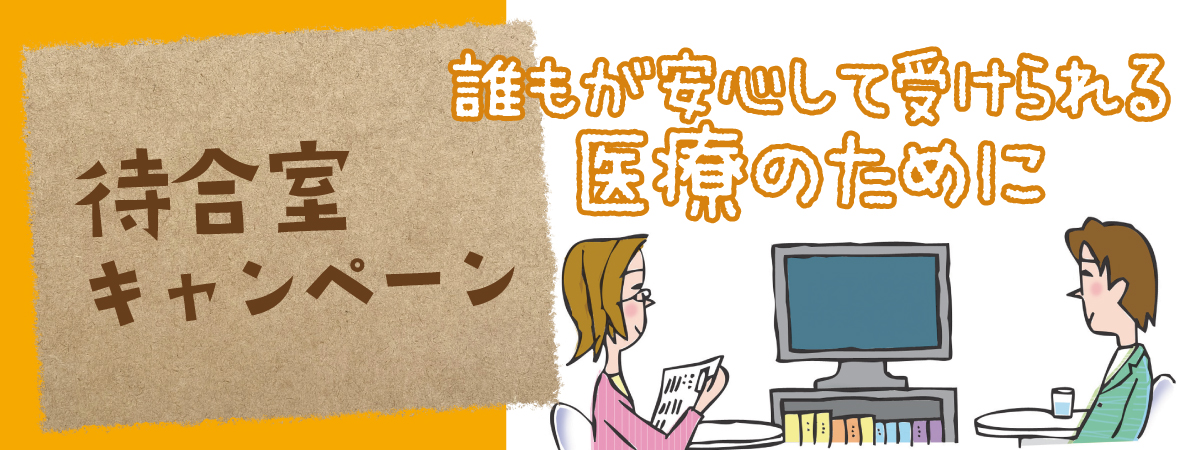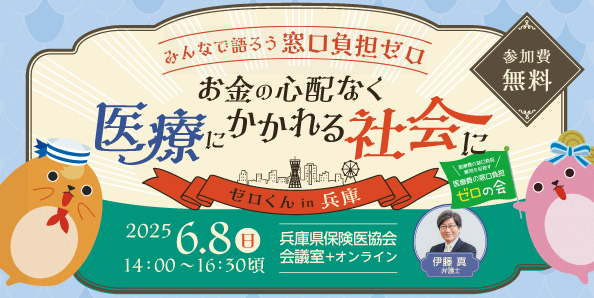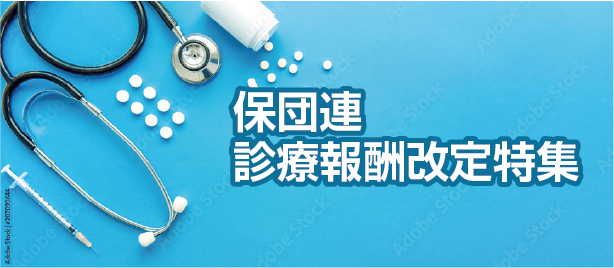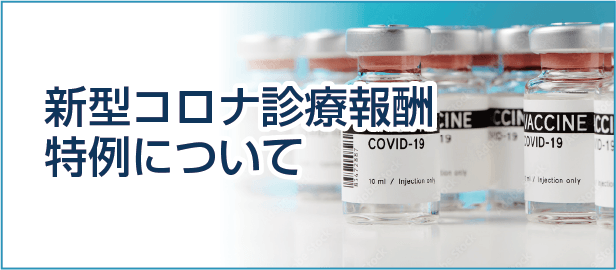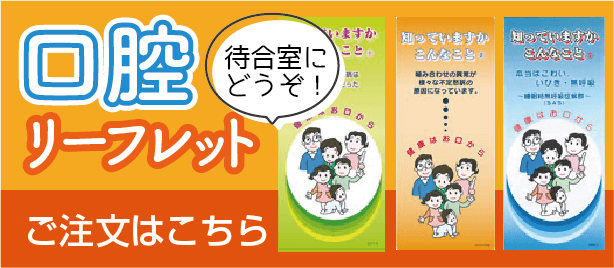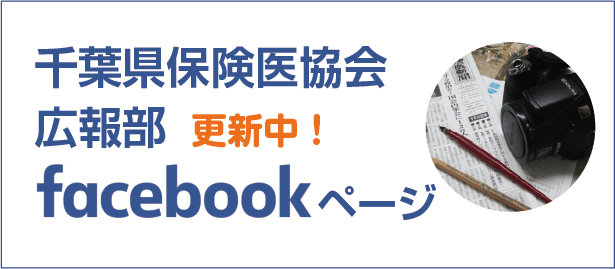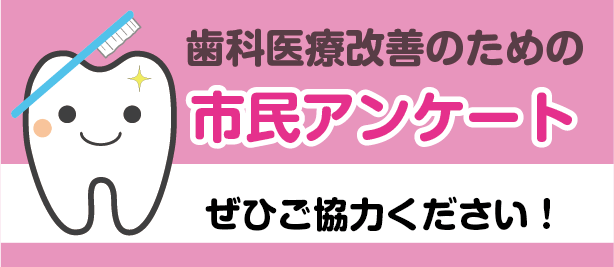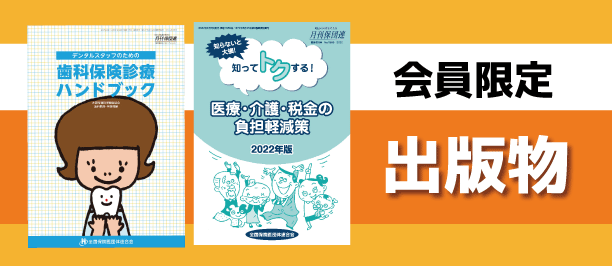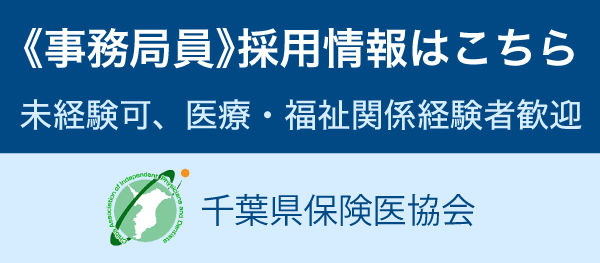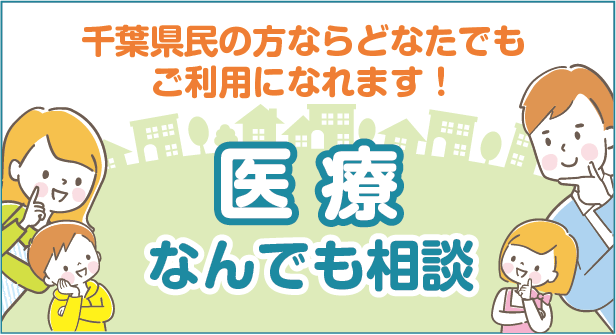神谷千葉千葉市長(右から2人目)と懇談したちばHPVero プロジェクトの代表=7月 22 日・千葉市役所
神谷千葉千葉市長(右から2人目)と懇談したちばHPVero プロジェクトの代表=7月 22 日・千葉市役所《ちばHPVzeroプロジェクト》神谷千葉市長と懇談
小学6年からの接種開始を
協会が団体加盟する「ちばHPVzeroプロジェクト」(代表:千葉県産婦人科医学会水谷敏郎会長)は、7月22日、千葉市役所本庁舎で神谷俊一千葉市長と懇談。同プロジェクトから甲賀かをり氏(千葉大学大学院医学研究院産婦人科学教授、太田文夫氏(千葉市医師会副会長)、協会から吉川恵子事務局長が出席。懇談は、布施貴良元市議の尽力で開いたもの。
冒頭、甲賀氏は、千葉大学で取り組んでいるプレコンセプション外来など女性や新しく生まれてくる子どもたちへの取組みを紹介。
また、昨年のHPVワクチン(子宮頸がん予防ワクチン)キャッチアップ接種での個別通知等の宣伝強化により千葉市は県平均を上回る接種率となり、今年は定期接種の接種率を更に上げるための提案を行った。
太田氏からは日本脳炎ワクチンについて、基本的に3歳から標準接種であるが、千葉市は6ヵ月からの接種を推奨しているとしている。ただし、個別通知が届かないこともあり、知らない保護者もいる。現在、市内の医療機関には予診票を置いており、接種しやすい環境が整っている。市としてもさらにHP等で6ヵ月からの接種を宣伝して欲しいと求めた。
その後、甲賀氏はちばHPVzeroプロジェクトで作成した新ポスターを紹介。「予防接種法上は小6から接種できるとなっており、年齢が低い方が免疫が付きやすく、有害事象も起こりにくいといわれている。
千葉市においても定期の予防接種率を上げていくために接種開始を進めていただきたい」と提案した。
接種開始時期を検討
神谷市長は、「HPVワクチンの定期接種の個別通知送付時期について、現在中学1年生から接種開始としているが、医学的な根拠はなく、合理的な理由がないこともわかった。
今後来年度に向けて千葉市医師会とも相談しながら適切な時期を検討し、接種率が上がるように発送方法等も検討していきたい。ワクチンで防げる病気に対して、しっかり市としても取り組んでいきたい」と抱負を述べた。
歯初診・外感染・外安全に対応
歯科施設基準研修会開く
協会は6月28日、千葉市文化センターで「院内感染防止対策および新興感染症対策、最新の感染症発生動向と対策研修会」と「歯科外来診療安全対策加算に係る研修会」を開催。71人が参加した。
「院内感染防止対策および新興感染症対策、最新の感染症発生動向と対策研修」は柴原孝彦氏(東京歯科大学名誉教授・客員教授、東京歯科大学千葉歯科診療センター長補佐)が講師を務め、「歯科外来診療安全対策加算に係る研修」では福田謙一氏(東京歯科大学口腔健康科学講座教授)と石毛清雄協会保険部長が務めた。
■感染防止対策研修
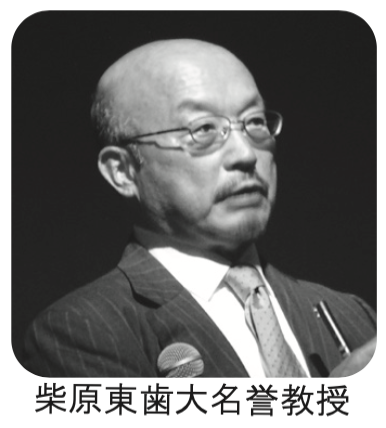 柴原氏は、歯科医療において患者の体液が飛散しやすいため、感染対策の徹底が不可欠であると説明。新型コロナウイルスなどの感染症対策の基本は、スタンダード・プレコーション(標準予防策)の徹底であり、感染経路の特性を理解し、それぞれに応じた対応が求められると述べた。
柴原氏は、歯科医療において患者の体液が飛散しやすいため、感染対策の徹底が不可欠であると説明。新型コロナウイルスなどの感染症対策の基本は、スタンダード・プレコーション(標準予防策)の徹底であり、感染経路の特性を理解し、それぞれに応じた対応が求められると述べた。
過去の感染事例を挙げながら、手洗いや器具の滅菌、個人防護具(PPE)の使用、診療環境の衛生維持の重要性を解説し、常に新しい感染症の発生に備える「永遠の備え」が医療従事者にとって重要であることを強調した。
■外安全に係る研修
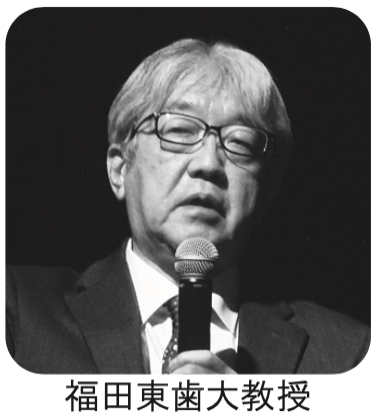 続いて、福田氏が「偶発症に対する緊急時の対応」と題し講演。医療現場での事故は、最善の注意を払っていても、人間のミスやシステムの不備が重なり発生する可能性があると指摘。一連の確認不足や意識の欠如が事故を招くと説明した。実際に起こった症例を挙げながら、緊急時の酸素供給や気道確保、胸骨圧迫(心臓マッサージ)の実施やAEDの使用の重要性を強調。
続いて、福田氏が「偶発症に対する緊急時の対応」と題し講演。医療現場での事故は、最善の注意を払っていても、人間のミスやシステムの不備が重なり発生する可能性があると指摘。一連の確認不足や意識の欠如が事故を招くと説明した。実際に起こった症例を挙げながら、緊急時の酸素供給や気道確保、胸骨圧迫(心臓マッサージ)の実施やAEDの使用の重要性を強調。
日頃からシミュレーションや訓練を重ねる事で、対応力を高める必要があると述べた。
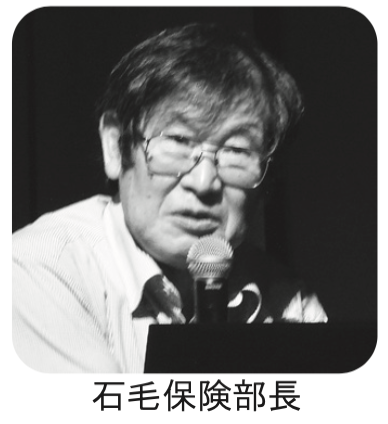 最後に、石毛氏は実際に発生した医療事故やヒヤリハット事例をもとに、安全対策の重要性について説明。事故発生の要因とその改善策について具体的に説明し、事故を未然に防ぐには、スタッフがヒヤリハットを共有できる環境を整えることが不可欠であると指摘。怒りや責任追及ではなく、解決策を共に考える姿勢が重要であると述べた。また、スタッフ全員が安全対策の重要性を理解し、定期的に講習会に参加して知識や意識を高めることを推奨した。
最後に、石毛氏は実際に発生した医療事故やヒヤリハット事例をもとに、安全対策の重要性について説明。事故発生の要因とその改善策について具体的に説明し、事故を未然に防ぐには、スタッフがヒヤリハットを共有できる環境を整えることが不可欠であると指摘。怒りや責任追及ではなく、解決策を共に考える姿勢が重要であると述べた。また、スタッフ全員が安全対策の重要性を理解し、定期的に講習会に参加して知識や意識を高めることを推奨した。