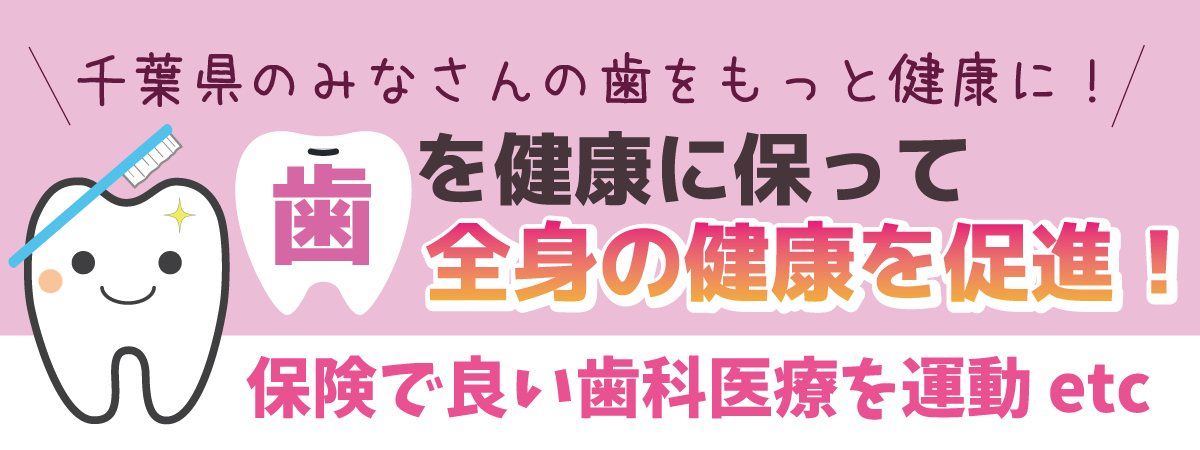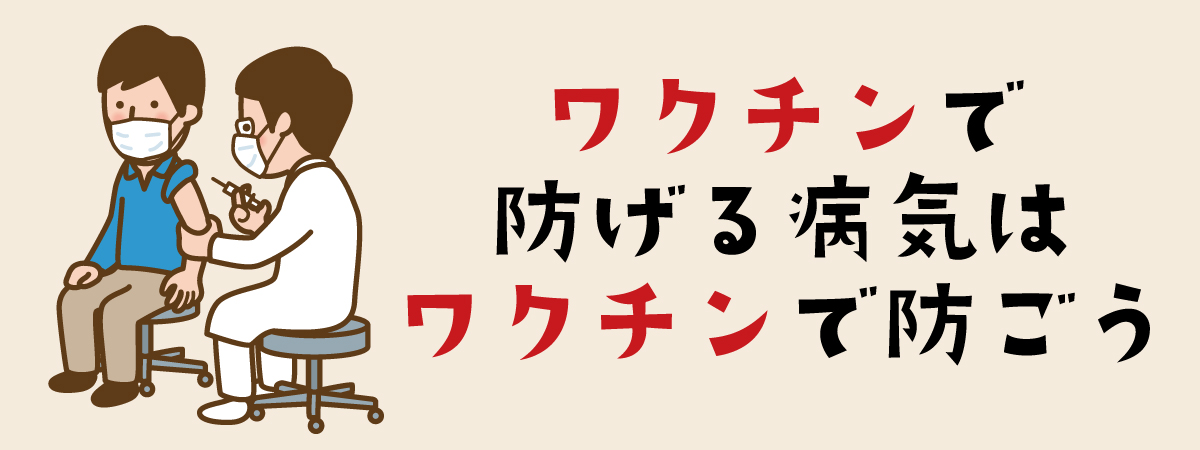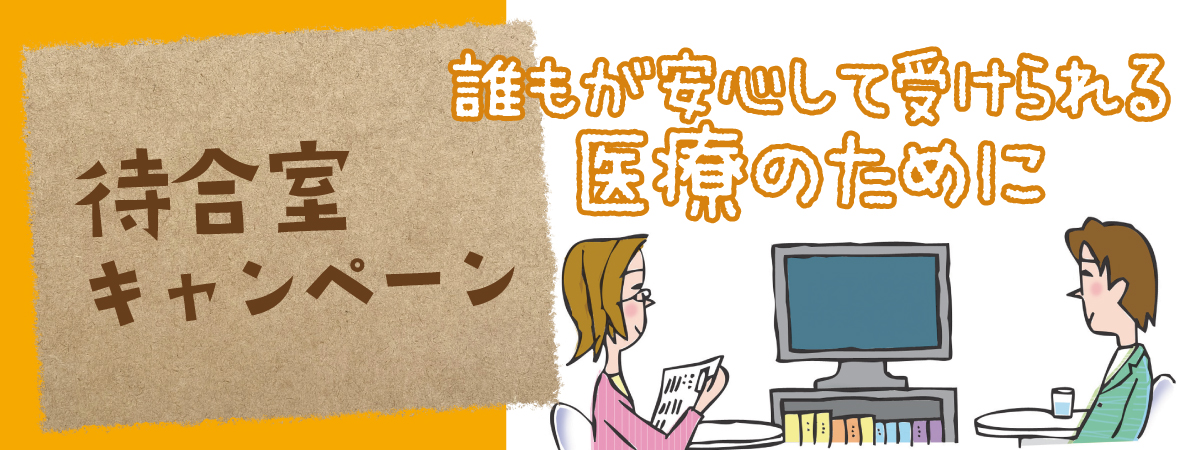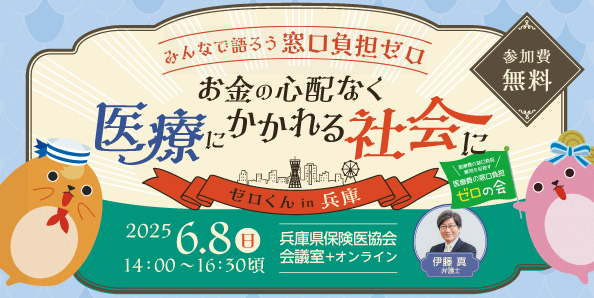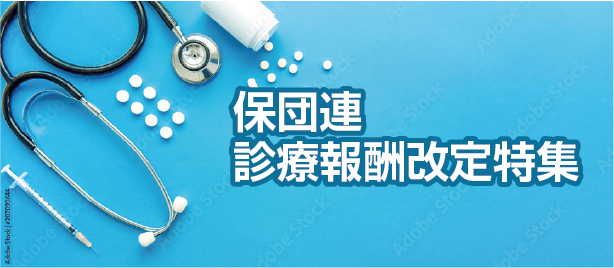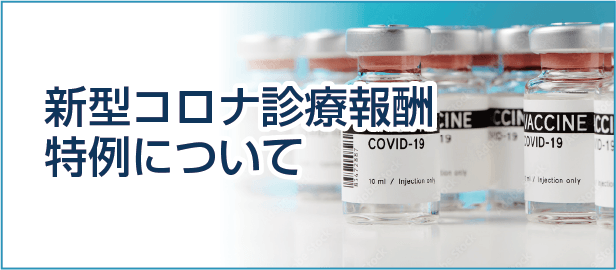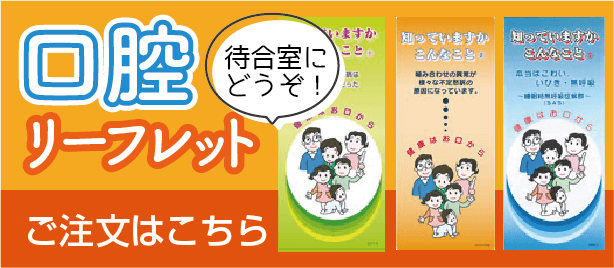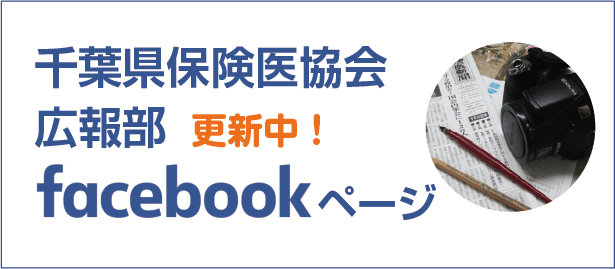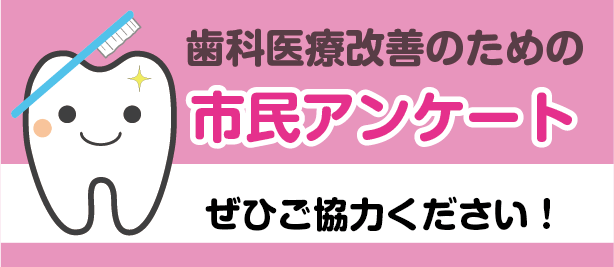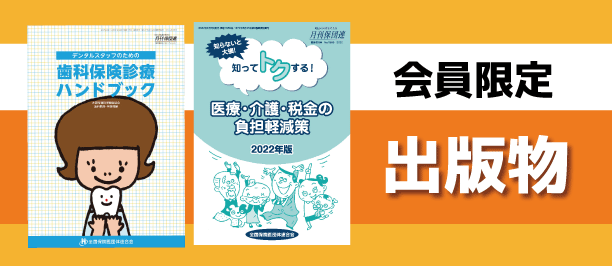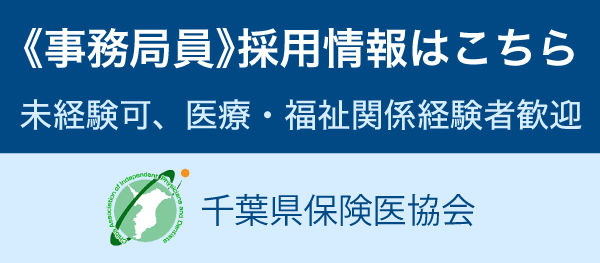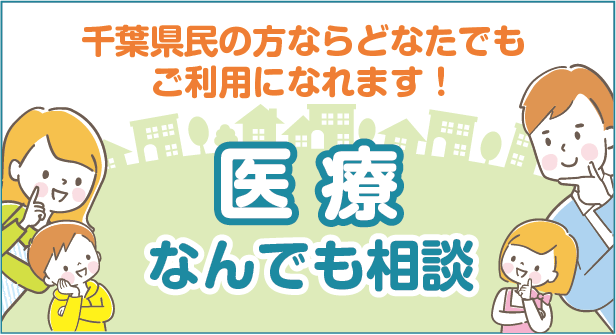保団連関東ブロック協議会(千葉を含む9つの保険医協会で組織)は10月12日、東京都内の都市センターホテル「コスモス」で「地域から医療をなくすな!緊急決起集会」を開催し、医師・歯科医師・事務局ら194人が会場に結集した。
集会では、関東ブロック各協会会員を対象に行った「医療機関経営実態調査」のまとめが報告され、医療機関がおかれている厳しい現状を明らかにした。
各協会からは医療現場の実態報告、運動提起等の発言が行われた。経営危機打開のため、次期診療報酬の大幅引き上げを求める決議を採択した。
また、小池晃参議院議員、谷田川はじめ衆議院議員が駆け付け、激励と医療提供体制の充実に向けた連帯の来賓挨拶が行われた。
集会には保団連関東ブロック協議会9協会から医師、歯科医師、保団連役員50人、事務局66人、関連団体7人、Web参加71人の総勢194人が集結。
「医療機関の経営危機打開」、「次期診療報酬の大幅引き上げを勝ち取ろう」、「皆保険制度の堅持を」など連帯した行動を訴えた。
集会に際し、栃木県医師会、横浜市医師会、川崎市医師会他、自由民主党、立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組、国民民主党等、多くの国会議員からメッセージが届き、会場には小池晃参議院議員(共産)、谷田川一衆議院議員(立憲)が来場し、激励の挨拶が、また国光文乃衆議院議員(自民)、阿部知子衆議院議員(立憲)、梅村聡衆議院議員(維新)、上月良祐参議院議員(自民)、小西洋之参議院議員(立憲)からはビデオメッセージが寄せられた。
各議員からは党派を超えて「医療機関を守るために、早急に補正予算を執行させて、公定価格を上げる必要がある。
次期診療報酬は大幅引き上げを行うべきだ! 頑張りましょう!」と力強い決意が述べられ、その後、関東ブロック協議会9協会の代表役員から小池晃議員、谷田川一議員に当日会場に持参した3425筆(8協会分)の会員署名を提出した。
来賓の竹田智雄保団連会長から連帯挨拶ののち、今回実施した関東ブロック9協会の医療機関経営実態調査を二村哲神奈川協会副会長が報告した。


関東の9協会で構成する「保団連関東ブロック協議会」主催で開いた『地域から医療をなくすな!緊急決起集会』。
医師・歯科医師が白衣でアピール(上)/集会の模様(下)=10月12日・都市センターホテル内「コスモス」。
内科では減収率18%、医業全体が厳しく、早急な対策が必須
二村氏は、無床診療所では2023年度から24年度にかけて事業所得の減収率は平均14%に及ぶことが明らかとなり、中でも内科は減収額が510万円(減収率は18%)と落込みが大きく24年度改定の医学管理料の組み換えの影響が大きいと評価。
医療経営の実態は日本医師会などの他の医療団体の調査や、レセプト平均点数の推移でも共通しており、関東ブロック共同調査によって診療所の減収状況が明示できたとし、「診療報酬の期中改定や、国の責任による補助金等での緊急財政措置を早急に行うこと、また26年診療報酬改定で、基本診療料を中心に少なくとも10%以上の大幅な引き上げを行うこと、併せて、患者窓口負担の大幅軽減を求めていく」と報告した。
続いて、地域の切実な現状や運動提起等9人の弁士(群馬:小山敦氏「歯科医療の材料について」、千葉:石毛清雄氏「歯科医療の危機的状況、材料、技工士問題について」、東京:日下部浩氏「整形外科の現状と課題」、東京歯科:加藤開氏「物価高騰アンケートからみた歯科の現状」、山梨:伊藤龍吾事務局長「会員署名によせられた声を紹介」、茨城:櫻井岳史氏「医療機関の現状と課題」、神奈川:宮澤由美氏「地域医療を守ろう署名について」、千葉:中村健一氏「皮膚科医の立場からOTC類似薬の保険外しの問題について」、埼玉:土田昌巳氏「2024年内部分留保、過去最高をまたも更新・次期大幅改定の財源はある」(発言順)を訴えた。
次に、栃木協会天谷副会長から緊急決起集会決議(案)が提案され、拍手で採択した。
その拍手に包まれる中、司会の細部千晴東京協会理事より「頑張ろうコール」の呼びかけがあり、全員白衣で立ち上がり「次期診療報酬の大幅引き上げを目指し、頑張ろう!」「ガンバロー!」と力強く拳を高らかにあげて一致団結し唱和した。
最後に高橋秀夫茨城協会会長より閉会の挨拶を行い、2時間の集会を終了した。
【歯科学術研究会】どう入れるのか?「命のスイッチ」摂食嚥下障害の対応を学ぶ
 森氏は症状に応じた摂食嚥下 訓練について詳細に解説した。=9月 27 日・協会会議室協会研究部は、9月27日、協会会議室で「開業医・歯科医による摂食嚥下障害の対応と具体例」をテーマに歯科学術研究会をWeb併用で開催した。
森氏は症状に応じた摂食嚥下 訓練について詳細に解説した。=9月 27 日・協会会議室協会研究部は、9月27日、協会会議室で「開業医・歯科医による摂食嚥下障害の対応と具体例」をテーマに歯科学術研究会をWeb併用で開催した。
講師は、森宏樹氏(八千代市開業・森歯科クリニック)が講師が務め、101人が参加した。
森氏は食事を複合的な要素・機能から成り立つものと指摘し、摂食嚥下障害は「何らかの原因で食べることに困っている状態」と定義した。
原因は患者によって様々なもので、診断の場面においては主に自覚症状のある患者にしか口腔機能検査が行われない。
そのため、スクリーニング検査の機能を果たせず、自覚症状のない患者を見つけ出す困難さを指摘した。
診断が確定した患者に対しては、定期なVE検査(嚥下内視鏡検査)等を行いながら、状態の変化にあわせ、リハビリ方法を検討する柔軟な診療形態について説いた。
続いて森氏が長年に渡り診療研究に基づいて作成した摂食嚥下機能評価シートを紹介。その項目に従って患者の状態評価を行う流れを解説した。
講演後半では4つの症例が取りあげ、初診時からの経過を詳細に説明した。
その中でも特に、呼吸訓練のために医療従事者も楽しみながら、いかに意欲を引き出すかを重視した「吹き矢の自作ゲーム」の事例を紹介し、個々の症状に合わせたリハビリから映し出される創意工夫には参加者から感嘆の声が上がった。
また「噛む」ことの重要性についても言及。
歯を噛みあわせるだけの『咬合』と、『噛んで食べることができる』は別物であると指摘すると共に、噛んで食べることができると『命のスイッチ』が入り、食事への意欲・楽しみが状態の改善に繋がることが実際の症例から示した。
【千葉支部】会員向け諸活動と地域への貢献を確認
健康保険資格確認と医療DXを学習
10月9日、千葉支部は協会会議室で、支部総会・記念講演を会場とWeb併用で行い、併せて25人が参加した。
総会では、2024年度活動報告と会計報告が行われ、25年度の活動方針案では、① 会員に密接した諸活動として、会員自身の意識向上を図る学術研究会、社保講習会、個別指導学習会、日常診療にかかわる問題点などの解決相談、最新の医療情報、時局問題等の情報提供を行う。また、会員拡大および会員相互の親睦をはかり、支部役員増員に向けて活動をすすめること。
② 社会の一員として、医師・歯科医師として、地域住民に貢献するための活動として、公民館などでの健康講話活動や、老人ホーム・認可外保育所等での健診・相談活動を行う。
また、医療行政の問題点などを話し合い、改善を求める運動を行うこと。を提案し、採択した。
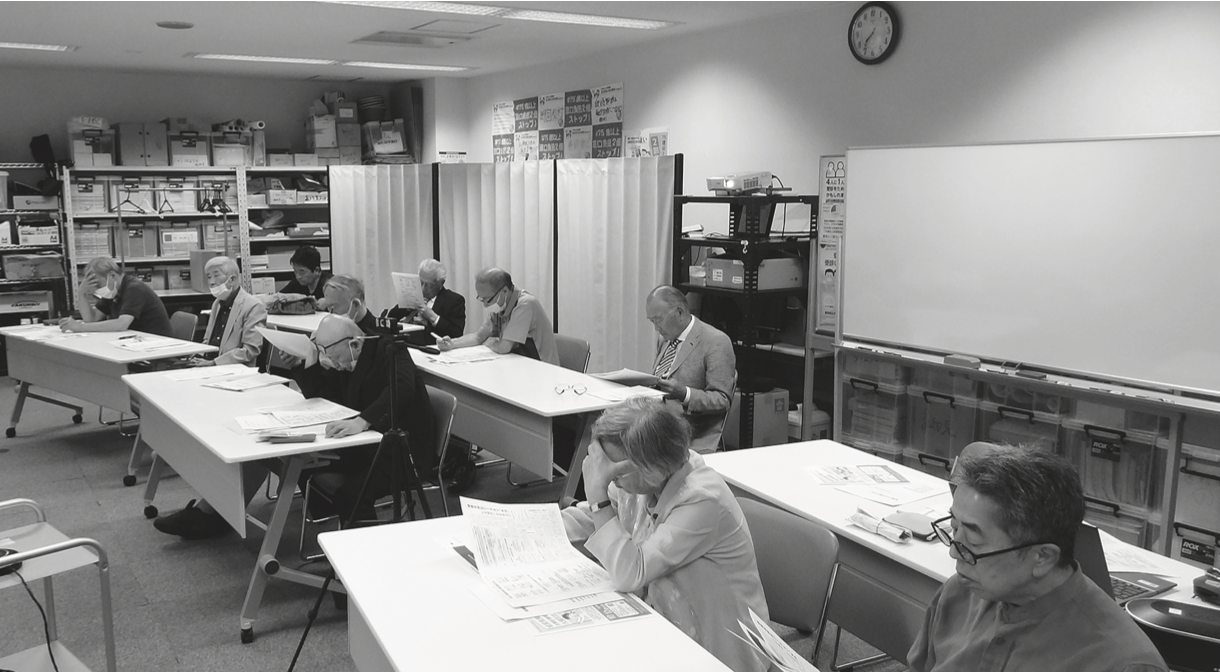
支部総会後の記念講演では、協会事務局宮崎博幸事務局主任が「今後の健康保険資格確認に関する医療機関の対応」をテーマに、健康保険証や資格確認証の今までの経緯を振り返り、現状での問題点などについて、以前協会で行ったアンケート結果を用いながら解説を、川井貴裕事務局次長が「今後の医療DXの方向」をテーマに、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ共有サービス、診療報酬改定DXなど医療DXの今後の見通しについての解説を行った。
木島肇雄支部長は「電⼦化がどんどん進み、我々は新しいシステムについていくのに精いっぱいになってしまいますが、診療を辞めるわけにもいきません。
保険医協会の事務局に協力してもらいながら、新しい知識をつけて、日々の診療も頑張っていきましょう」と締めくくった。