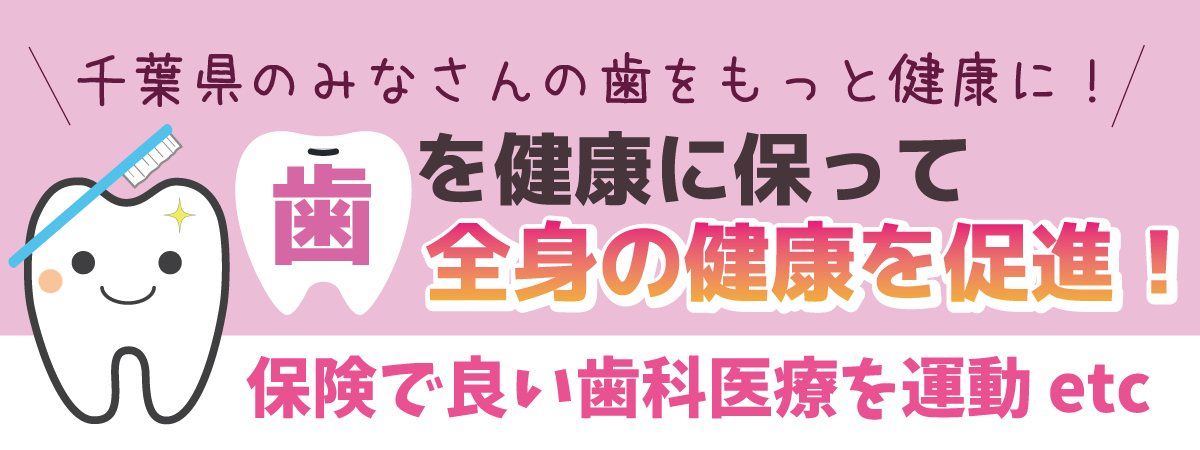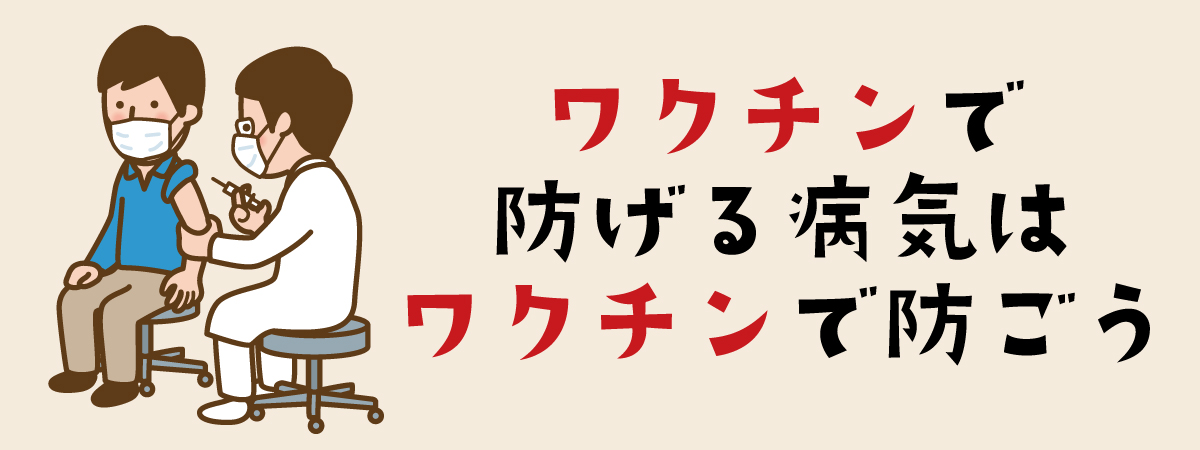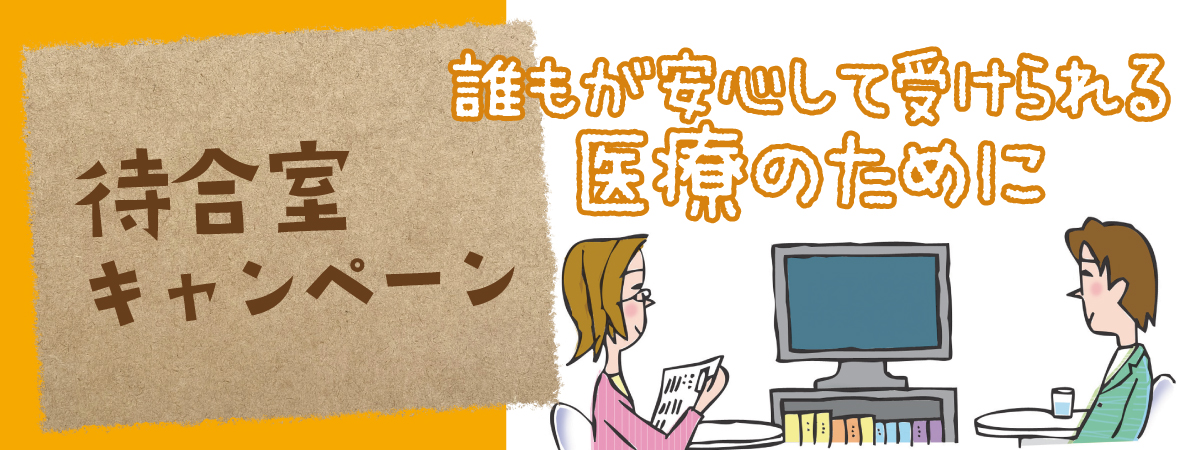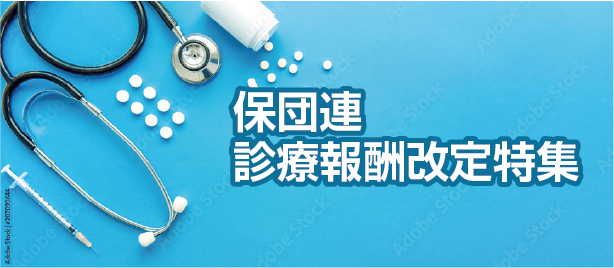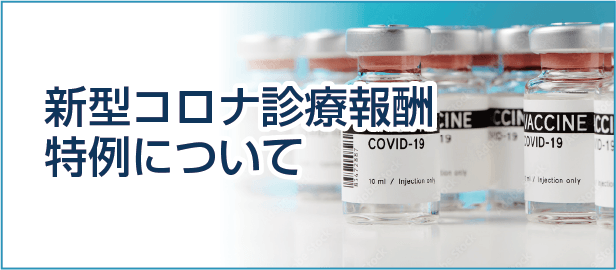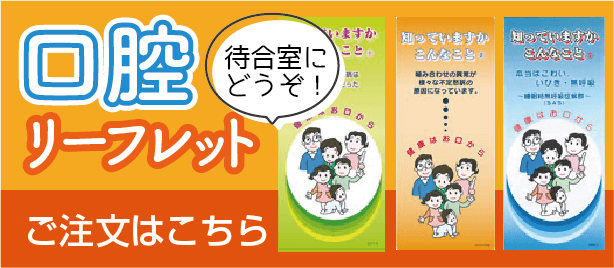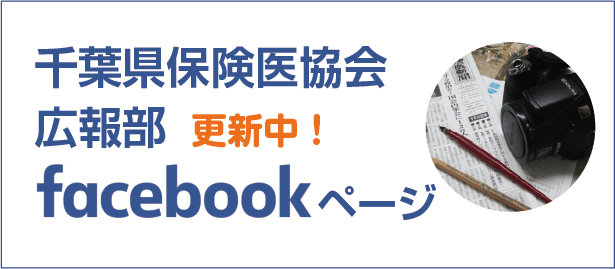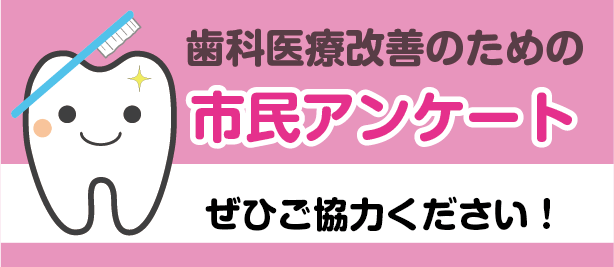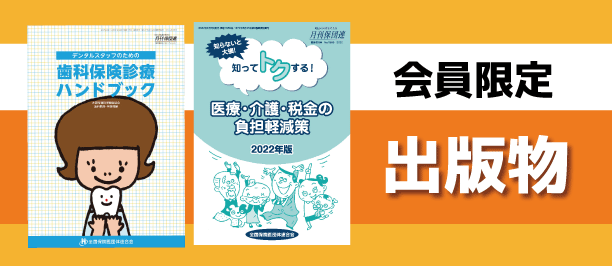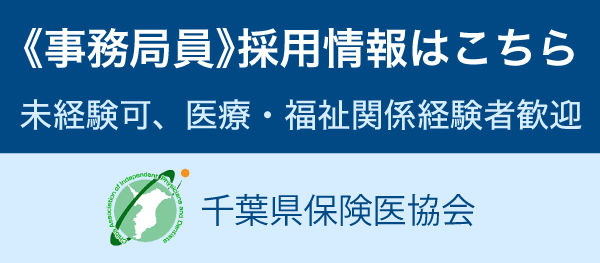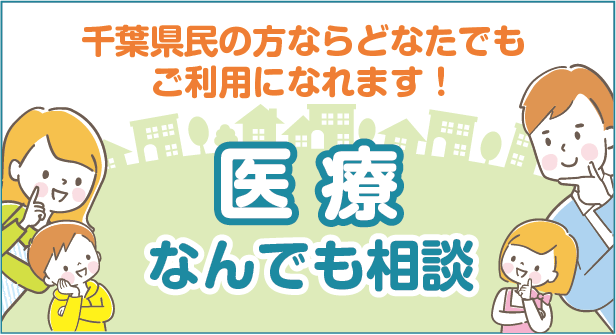社保Q&A(医科)
初・再診料
健康診断後の初診料
- 健康診断で疾患が見つかり、次回来院から保険診療に移行することとなりました。次回来院時、初診料は算定できますか。
- 算定できません。健康診断にて初診料を算定している扱いとなり、保険診療にて別途初診料を算定することはできません。次回来院時は、再診料より算定します。
同一月2回の初診料算定
- 月初に風邪様症状で診療開始した患者に対し初診料を算定し、1週間後に治癒を認めました。当該患者が月末に再び風邪様症状で受診した場合、再び初診料を算定できますか。
- 算定できます。ある傷病が治癒した後、同一月内に同一病名の診療開始となった場合でも、初診料は算定できます。
労災の初診料①
- 健康保険で定期受診している患者さんが、業務上の怪我で整形外科を受診しました。労災を使用することとなりましたが、整形外科で労災の初診料を算定することはできますか。
- 算定できます。労災の初診料は、支給事由となる業務上の怪我の発生の都度算定できます。既に健康保険で診療を行っている医療機関においても、労災となる傷病について初めて診療を行った場合、労災の初診料を算定できます。
労災の初診料②
- 業務上の怪我で既に労災による診療を行っている患者さんが、別の業務上の怪我で受診しました。この場合、再度労災の初診料を算定することはできますか。
- 業務上の怪我で既に労災による診療を行っている患者さんが、別の業務上の怪我で受診しました。この場合、再度労災の初診料を算定することはできますか。
GWの処方制限
- GWは5月1日から5月5日まで休診とする予定です。4月30日に来院した患者さんに対し、1回14日制限とされている薬を、30日分処方することはできますか。
- 処方できます。特殊の事情(海外への渡航、年末・年始及び連休に係るもの等)がある場合、投与日数が14日分までとされている薬を30日分まで処方できます。この特殊の事情には、GWも含まれます。なお、投与日数上限が30日分とされている薬に関しては、30日を超えての処方はできません。
GWの夜間・早朝等加算
- ゴールデンウィーク(以下、GWの休日の内、4月29日は通常診療を行います。診療時間内に診察した患者さんに対し、夜間・早朝等加算は算定できますか。
- 施設基準を満たしていれば算定できます。夜間・早朝等加算は休日に通常診療を行った場合、標榜する診療時間内に診察した患者に対して算定できます。施設基準について、詳しくは「保険診療の手引」をご参照下さい。なお、厚生局への届出は不要です。
年末年始の休日加算
- 当院は年末年始の12月29日から1月5日までを休診とします。12月29日に急患を診察した場合、初・再診料の休日加算を算定することはできますか。
- 算定できます。休日加算の対象となる休日は日曜日及び国民の祝日ですが、12月29日から1月3日も休日として扱います。これらの日を休診としている医療機関が急病等の理由により患者を診察した場合、初・再診料の休日加算(深夜加算の定める時間にあっては深夜加算)を算定できます。ただし、医療機関が自ら診療日とした場合は算定できません。
年末年始の診療
- 当院では12月29日と30日に通常通りに診療を行うこととしました。この場合、29日と30日に受診した患者さんについて初・再診料に係る休日加算を算定できますか。
- 算定できません。12月29日、30日は休日加算の算定対象となる休日に該当しますが、当該日を診療日として診療を行った場合には休日加算の算定対象とはなりません。自治体の輪番制の休日診療等のために当該日に診療を行った場合には休日加算を算定できますが、輪番等によらず自ら診療時間として診療を行った場合には休日加算は算定できません。
年末年始の夜間・早朝等加算
- 12月29日を診療日として診察を行います。診療時間内に診察した患者さんに対し、初・再診料の夜間・早朝等加算は算定できますか。
- 施設基準を満たしていれば算定できます。夜間・早朝等加算は時間外、休日、深夜加算の対象となる時間・日を診療時間・日とする場合で、標榜する診療時間内に診察した患者に対して算定できます。12月29日から1月3日は休日として扱うため、これらの日を診療日とした場合には算定できます。施設基準について、詳しくは「保険診療の手引」をご参照下さい。なお、厚生局への届出は不要です。
初・再診料の時間外加算①
- 当院は日曜日・祝日を終日休診、水・土曜日を午後休診としています。水曜日又は土曜日の午後1時に急患の診療を行った場合、初・再診料の時間外加算は算定できますか。
- 水曜日は算定できませんが、土曜日は算定できます。時間外加算の対象となる時間外の標準は、①概ね午前8時前と午後6時(土曜の場合は正午)以降、及び②休日加算の対象となる休日以外の休診日(終日休診日としている場合に限る)とされています。よって、終日休診としていない平日の午後については、土曜日は正午以降、月~金曜日は午後6時以降が対象となります。
初・再診料の時間外加算②
- 当該医療機関において、12月29日(土曜日)の午後1時に急患の診療を行った場合、前の設問と同様に初・再診料の時間外加算は算定できますか。
- 時間外加算ではなく、休日加算を算定します。休日加算の対象となる休日は、日曜日・祝日以外に1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日とされています。当該休日を診療日としている医療機関の診療時間以外の時間に診療を行った場合は、休日加算の対象となります。なお、前の設問のケースであっても、診療時間内に診療を行った場合は加算の対象となりませんのでご注意ください。
休日加算
- 当院は水曜日と日曜日を休診日としています。水曜日の昼前に発熱で初診の患者さんが来院されたため診療を行いましたが、初診料と休日加算を算定できますか。
- 休日加算は算定できず、時間外加算を算定します。休日加算の対象となる休日は、日曜日及び祝日、1月2日、1月3日、12月29日~31日とされております。医療機関の標榜する診療日以外の日に診療を行った場合であっても、これらに該当しない場合は休日加算ではなく時間外加算(深夜の時間帯にあっては深夜加算)を算定します。
トリガーポイント注射と外来管理加算
- トリガーポイント注射を実施し、外来管理加算を算定したところ減点されました。外来管理加算を算定できない項目に注射は該当せず、減点理由がわかりません。
- トリガーポイント注射を実施した場合は、外来管理加算は算定できません。トリガーポイント注射は点数表上、「注射」ではなく「麻酔」の部の項目となります。「麻酔」の部に該当する行為を行った場合は、外来管理加算は算定できないため、トリガーポイント注射を行った場合は、外来管理加算は算定できないこととなります。
鶏眼・胼胝処置と外来管理加算
- 月初に鶏眼・胼胝処置を行い、月末に同一部位に対して再度処置を行いました。2度目の処置実施時は処置料を算定しませんが、他に検査やリハビリ等を行わなかった場合、外来管理加算は算定できますか。
- 算定できません。処置の点数を算定しない場合であっても、実際に処置を行っているのであれば外来管理加算を算定できません。
訪問診療料算定時の外来管理加算
- 在宅患者訪問診療料(1)を算定している患者で、処置や検査等を行わずに計画的な医学管理を行っています。外来管理加算は算定できますか。
- 算定できません。外来管理加算は再診料に対する加算のため、再診料を算定出来ない場合は算定できません。往診を求められ、再診料と往診料を算定する場合であれば、要件を満たせば算定できます。
明細書発行体制等加算
- 患者さんから「明細書はいりません」と申出を受け、明細書を渡しませんでした。この場合でもA001再診料の明細書発行体制等加算を算定できますか。
- 算定できます。不要の申し出があった患者には、交付の必要はありません。なお、施設基準の届出は不要ですが、基準を満たしている必要があります。
入院料
入院中の患者の他医療機関受診
- 入院中の患者さんが歯科治療のため歯科医療機関を受診する場合も、入院中の患者の他医療機関受診の取扱い(入院基本料の減算等)となるのでしょうか。
- 入院中の患者の他医療機関受診の取扱いとはなりません。入院中の患者さんが当該入院の原因となった傷病以外の傷病に罹患し、入院している保険医療機関以外での診療の必要性が生じた場合は、原則として転院又は対診を求めることとされ、当該入院医療機関で診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限り、他の保険医療機関を受診することができるとされています。この場合、入院医療機関が算定している入院基本料等により具体的な取扱いはことなりますが、入院医療機関、外来医療機関共に入院中の患者の他医療機関受診の取扱いにより診療報酬を算定することとなります。ただし、歯科保険医療機関を受診する場合にはこの取扱いによることなく、入院医療機関、歯科保険医療機関ともに制限を受けることなく診療報酬を算定します。
生活保護単独の患者と平均在院日数
- 入院基本料等を届け出るに当たり平均在院日数を算出する際に、生活保護単独の患者さんは計算対象に含むのでしょうか。
- 含みません。入院基本料等を届け出る際に算出する平均在院日数は、保険診療にかかる入院患者が対象となります。したがって、生活保護単独の患者さんは平均在院日数の算出にあたっては除外します。同様に、労災や自賠責、人間ドック利用者、正常経過の妊産婦、正常新生児なども除外します。
療養病棟入院基本料と画像診断に係る加算
- 療養病棟入院基本料を算定する患者さんにエックス線の単純撮影を実施した場合、エックス線単純撮影に係る費用は入院基本料に含まれ算定できませんが、電子画像管理加算や画像診断管理加算1は算定できますか。
- 算定できません。「療養病棟入院基本料に含まれる画像診断」としての告示等には「電子画像管理加算や画像診断管理加算」は示されていませんが、これら加算点数を加算する所定点数となる写真診断や撮影の費用が算定できませんので、電子画像管理加算や画像診断管理加算1は算定できないとされています。
療養病棟入院患者の中心静脈カテーテル交換
- 療養病棟入院基本料を算定している患者さんに対して、中心静脈注射用カテーテルの交換を行いました。交換に係る手技料や材料料は算定できますか。
- 算定できません。療養病棟入院基本料には、特に定める注射に係るものを除き、注射の費用が包括されています。中心静脈注射用カテーテル交換の手技料はG005-2中心静脈注射用カテーテル挿入で算定するものであり、注射の点数であるため、材料料も含め別に算定できません。
再入院の診療所一般病床初期加算
- 有床診療所に入院していた患者さんが病状が安定したため退院し、自宅へ戻りましたが、月内に急性増悪で再入院となりました。前回の入院で有床診療所一般病床初期加算を算定していますが、入院起算日がリセットされる再入院の場合、有床診療所一般病床初期加算を算定できますか。
- 算定できます。入院起算日がリセットされる再入院の場合、有床診療所一般病床初期加算は、転院又は入院した日から起算して再び7日を限度に算定できます。
短期滞在手術基本料3
- 短期滞在手術基本料3の対象となる水晶体再建術を、6月10日に入院し11日に右側に実施、13日に退院しました。翌週の17日に再度入院し18日に左側にも実施、19日に退院した場合、退院後7日以内の再入院での同手術の実施となるため、いずれの手術に対しても出来高算定となるのでしょうか。
- 11日の手術に係る入院については短期滞在手術基本料3を算定し、18日の手術については、出来高で算定します。なお、2回目の手術に係る入院日が、1回目の手術のための入院に係る退院日から7日以上を経過した場合は、いずれの入院ともに短期滞在手術基本料3を算定します。
回復期リハビリテーション病棟入院料と抗悪性腫瘍剤
- 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に入院中の患者さんに抗悪性腫瘍薬を投与した場合、薬剤料は算定できますか。
- 算定できません。回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する場合、診療に係る費用は特に定められたものを除き別に算定することはできません。投薬や注射の費用は「除外薬剤・注射薬」を除き算定できません。回復期リハビリテーション病棟入院料における「除外薬剤・注射薬」は①インターフェロン製剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するものに限る)、②抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能若しくは効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る)、③血友病の治療に係る血液凝固因子製剤及び血液凝固因子抗体迂回活性複合体、の3つに限られ、抗悪性腫瘍剤は該当しません。なお、回復期リハビリテーション病棟入院料と同じく投薬・注射の費用が算定できない地域包括ケア病棟入院料においては、上記除外薬剤に加えて抗悪性腫瘍剤(悪性新生物に罹患している患者に対して投与された場合に限る)、疼痛コントロールのための医療用麻薬、エリスロポエチン・ダルベポエチン・エポエチンベータペゴル(人工腎臓又は腹膜灌流を受けている患者のうち腎性貧血状態にあるものに対して投与された場合に限る)も除外薬剤・注射薬とされており、別に算定できることとされております。「除外薬剤・注射薬」であっても対象となる薬剤が特定入院料によって異なる場合がありますので、ご注意ください。
医学管理等
特定疾患療養管理料
- 特定疾患療養管理料の対象疾患以外の疾患で受診し、初診料算定から1カ月経過した患者さんが、胃潰瘍を併発し治療と療養上の管理を行うことになりました。この場合、治療と療養上の管理を行った月から特定疾患療養管理料を算定できますか。
- 算定できます。特定疾患療養管理料は初診の日から1カ月を経過した日以降に、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者さんに療養上の管理を行った場合に算定できます。特定疾患療養管理料の対象疾患が確定診断された日が初診日より1カ月経過していれば、その日から特定疾患療養管理料を算定できます。
二科目初診と特定疾患療養管理料
- 高血圧症で特定疾患療養管理料を算定している患者さんが、外科疾患で外科にも受診し二科目初診料を算定しました。
この場合、レセプト請求では二科目初診料と特定疾患療養管理料が同じレセプトにでてきますが、それぞれ算定できますか。なお、内科と外科を標榜してそれぞれ別の医師が診療しています。
- それぞれ算定できます。特定疾患療養管理料は、初診料算定日又は退院日から1ヶ月以内は算定できませんが、本件では外科に対する初診行為であり、内科では算定要件を満たしています。
同じレセプトに二科目初診料と特定疾患療養管理料がでてきますが、摘要欄にはレセプト電算コードを使用して二つ目の診療科名を記載しますので状況はわかります。
慢性維持透析患者外来医学管理料と特定疾患療養管理料
- 慢性腎不全で人工透析を実施している患者さんが、悪性腫瘍に罹患しました。この場合、悪性腫瘍を主病と考え、特定疾患療養管理料と慢性維持透析患者外来医学管理料をそれぞれ算定できますか。
- 算定できます。特定疾患療養管理料と慢性維持透析患者外来医学管理料の併算定を制限する規定はありません。それぞれの算定要件を満たしていれば、併算定できます。慢性腎不全が主病の場合は、慢性腎不全が特定疾患療養管理料の算定対象の疾病ではないため特定疾患療養管理料は算定できませんが、お問い合わせの事例では悪性腫瘍が主病であり、特定疾患療養管理料の算定要件を満たすため、それぞれ算定できます。
特定薬剤治療管理料
- 毎月、薬剤の血中濃度等を測定し特定薬剤治療管理を実施していましたが、たまたま血中濃度測定検査を実施できない月がありました。この月は従来どおり薬剤を投与していますが、検査結果に基づいた管理指導を行っていません。この場合、特定薬剤治療管理料1は算定できますか。
- 算定できません。特定薬剤治療管理料1は、投与薬剤の血中濃度を測定し、その結果に基づき薬剤の投与量等を管理することが算定要件です。
したがって、何らかの事由で当該月に検査及びその結果を受けた管理指導が行われなかった場合は、算定要件を満たしていないため、算定できないことになります。
特定薬剤治療管理料①
- 2種類の抗てんかん剤を投与しているてんかんの患者さんに対して、それぞれの薬剤の血中濃度を測定し投与量を精密に管理しています。同一月に特定薬剤治療管理料は2回算定できますか。
- 算定できます。特定薬剤治療管理料は原則として月1回に限り算定しますが、2種類以上の抗てんかん剤を投与しているてんかん患者に限り、それぞれの薬剤について算定要件を満たした場合は月2回に限り算定できます。
特定薬剤治療管理料②
- 抗てんかん剤を投与しているてんかんの患者さんに対して特定薬剤治療管理料を初めて算定する月において、2種類の抗てんかん剤を投与し特定薬剤治療管理料を2回算定できる場合、初回月加算も2回算定できますか。
- 算定できません。2種類以上の抗てんかん剤を投与し特定薬剤治療管理料を2回算定できる月であっても、初回月加算の算定は1回に限られます。
特定薬剤治療管理料③
- 抗てんかん剤の投与に係る特定薬剤治療管理料を算定している患者さんに対して、躁うつ病の治療のためリチウム製剤も投与することになりました。リチウム製剤の血中濃度測定やその結果に基づいた投与量の管理を行う場合、特定薬剤治療管理料および初回月加算は算定できますか。
- 算定できます。すでに特定薬剤治療管理を行っている患者が新たに別の疾患を発症し、その治療のために投与する別の薬剤について特定薬剤治療管理料の算定要件を満たす場合には、当該管理料および初回月加算も算定できます。
特定薬剤治療管理料算定時の血液採取料
- 抗てんかん剤を投与している患者さんについて、薬剤の血中濃度測定等を行い特定薬剤治療管理料を算定しました。同時に他の血液検査を行った場合、血液採取に係る費用(B―V)は算定できますか。
- 算定できません。特定薬剤治療管理料には薬剤の血中濃度測定の費用が包括されており、血液採取に係る費用もこれに含まれます。血液を検体とした他の検査を同時に行ったとしても、血液採取の費用は別に算定できません。
グリベックと特定薬剤治療管理料
- 慢性骨髄性白血病の患者さんにグリベック錠(イマチニブ)を投与しています。当該薬剤の血中濃度を測定し、投与量等を管理していますが、特定薬剤治療管理料を算定できますか。
- 算定できます。「イマチニブを投与しているもの」は特定薬剤治療管理料の算定対象とされています。従って慢性骨髄性白血病等、イマチニブの適応疾患に対してイマチニブを投与し、血中濃度を測定し投与量等を精密に管理するなど算定要件を満たした場合は、特定薬剤治療管理料を算定できます。
メトトレキサートの血中濃度測定
- 関節リウマチに対してメトトレキサートを投与している患者で、メトトレキサートの血中濃度を測定しました。特定薬剤治療管理料は算定できますか。
- 算定できません。メトトレキサートは特定薬剤治療管理料の対象薬剤となっていますが、悪性腫瘍の患者に対して投与している場合が対象です。
悪性腫瘍特異物質治療管理料
- 継続的にがん疾患を管理し、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者さんについて、月に1度も腫瘍マーカーの検査を実施せずにその他の管理を行った場合も悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定できますか。
- 算定できません。悪性腫瘍特異物質治療管理料の算定要件は、腫瘍マーカーに係る検査を行いその結果に基づいて計画的な治療管理を行うこととされています。
悪性腫瘍特異物質治療管理料
- 悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定している患者さんに腫瘍マーカー検査と同日に心不全の病態把握のため、内分泌学的検査も実施しました。この血液検査に係る費用は別に算定できますか。
- 算定できます。悪性腫瘍特異物質以外の検査を行った場合は、悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に検査実施料と判断料を算定でき、本件では内分泌学的検査の実施料と生化学的検査(Ⅱ)判断料を算定します。
がん術後の悪性腫瘍特異物質治療管理料
- 大腸癌の術後の患者で、経過観察のためにCEAを行います。がん術後悪性腫瘍特異物質治療管理料は算定できますか。
- 算定できます。悪性腫瘍特異物質治療管理料は、悪性腫瘍であると確定診断がされた患者に腫瘍マーカー検査を行い、結果に基づいて計画的な治療管理を行った場合に算定しますが、がん術後の患者も確定診断された患者に含まれます。
悪性腫瘍特異物質治療管理料
- がんの確定病名がついている患者に対し、同日に腫瘍マーカー検査と生化学的検査(Ⅰ)を行いました。腫瘍マーカー検査の費用は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれますが、同日に行った血液学的検査の費用は別に算定できますか。
- 生化学的検査(Ⅰ)の実施料との判断料は別に算定できます。今回のケースでは腫瘍マーカー検査に係る検査実施料、生化学的検査(Ⅱ)の判断料、採血料は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれますが、それ以外のものについては別に算定できます。
悪性腫瘍特異物質治療管理料と腫瘍マーカー①
- 大腸がん(術後)の患者さんに対して癌胎児性抗原(CEA)検査を行いました。大腸がんの切除術は3年前に行い、以来再発することなく術後病名のままです。術後長期間経過している場合、生化学的検査(Ⅱ)の腫瘍マーカーで算定できますか。
- 算定できません。一度がんが確定した患者さんに対して腫瘍マーカー検査を行った場合、術後時間が経っていたとしても例外規定を除き腫瘍マーカー検査は算定せず、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定します。
悪性腫瘍特異物質治療管理料と腫瘍マーカー②
- 肝がんの患者さんに対し、膵がんの疑いでCA19-9検査を行いました。この場合、生化学的検査(Ⅱ)の腫瘍マーカーで算定できますか。
- 算定できません。一度がんが確定した患者さんに対して、他の部位のがんを疑い他の部位の腫瘍マーカー検査を行った場合でも、例外規定を除き腫瘍マーカー検査は算定せず、悪性腫瘍特異物質治療管理料を算定します。
悪性腫瘍特異物質治療管理料と腫瘍マーカー③
- 胃がんで慢性C型肝炎を併発している患者さんに対して、癌胎児性抗原(CEA)、α-フェトプロテイン(AFP)検査を行いました。この場合、悪性腫瘍特異物質治療管理料(2項目以上)での算定となりますか。
- 悪性腫瘍特異物質治療管理料(1項目・CEA)と腫瘍マーカー(1項目・AFP)で算定します。がんの確定以降に行った腫瘍マーカー検査の費用は悪性腫瘍特異物質治療管理料に含まれ同一月に併せて算定できませんが、次に掲げる場合においては悪性腫瘍特異物質治療管理料とは別に腫瘍マーカーの検査料を算定できます。ア.急性および慢性膵炎の診断および経過観察のためにエラスターゼ1を行った場合、イ.肝硬変、HBs抗原陽性の慢性肝炎又はHCV抗体陽性の慢性肝炎の患者について、α-フェトプロテイン(AFP)、PIVKA-Ⅱ半定量又は定量を行った場合(月1回に限る)、ウ.子宮内膜症の診断又は治療効果判定を目的としてCA125又はCA602を行った場合(診断又は治療前及び治療後の各1回に限る)、エ.家族性大腸腺腫症の患者に対して癌胎児性抗原(CEA)を行った場合
糖尿病合併症管理料
- 高血圧症、脂質異常症の基礎疾患がある患者さんに糖尿病の疑い、閉塞性動脈硬化症の診断も加わりました。糖尿病の確定診断はなされていませんが、医師が足の状態のセルフケアの方法などの指導を行う場合、糖尿病合併症管理料を算定できますか。
- 算定できません。糖尿病合併症管理料の算定対象者は糖尿病であり、糖尿病足病変ハイリスク要因を有する患者さんで、医師が糖尿病足病変に関する指導の必要性を認めた場合が要件です。
小児特定疾患カウンセリング料と小児科療養指導料
- 小児特定疾患カウンセリング料と小児科療養指導料は同一月に算定できますか。
- 算定できません。小児特定疾患カウンセリング料と小児科療養指導料は、各々の点数や医学管理等の告示・通知では同一月の併算定を禁止する規定はありませんが、特掲診療料に関する通則で、同一月に算定できない旨が規定されているため、同一月には算定できません。同様に、在宅自己注射指導管理料や在宅小児低血糖患者指導管理料等の在宅療養指導管理料についても特掲診療料に関する通則で、小児特定疾患カウンセリング料や小児科療養指導料等と同一月に算定できない旨が規定されておりますので、ご留意ください。
難病外来指導料と特定疾患療養管理料
- 主病を複数有し、難病外来指導料と特定疾患療養管理料のそれぞれの対象疾患を主病とする患者さんがいます。月1回のみの受診だった場合は難病外来指導料を算定し、月2回以上受診があった場合は特定疾患療養管理料を算定しても良いのでしょうか。
- 月の受診回数によって難病外来指導料と特定疾患療養管理料を使い分けることは適切ではないと考えます。レセプト上、主病を複数指定することはできますが、診療報酬算定に際しては主病はひとつのみとされています。従って、難病外来指導料と特定疾患療養管理料の双方の算定要件を同時に満たすことはありません。患者さんの病状の変化等により主病が変更となる場合は、難病外来指導料を算定した翌月に特定疾患療養管理料を算定する、または特定疾患療養管理料を算定した翌月に難病外来指導料を算定するケースはありえますが、受診回数に応じて使い分けることは点数の趣旨などから鑑みても適切ではないと考えます。
診療継続中患者への新たな食事指導
- 数年前に脂質異常症の治療食に係る外来栄養食事指導を行い、診療継続中の患者さんに対して、新たに糖尿病に対する食事指導を開始することになりました。この場合、外来栄養食事指導料は「初回」の点数を算定できますか。
- 算定できません。何らかの疾病に係る外来栄養食事指導を実施済みの患者さんに対して、新たに別の疾病に係る食事指診療継続中患者への新たな食事指導導を行っても、外来栄養食事指導料は2回目以降の取扱いとなります。ただし、既に外来栄養食事指導を実施済みであっても、その患者さんに対する診療(複数疾病治療中の場合はそのすべてに対する診療)が終了した後、新たに他の疾病に対する診療を開始し、当該疾病に係る食事指導を開始した場合は、この限りではありません。
退院後の外来栄養食事指導料
- 入院中の患者さんに食事指導を行い、入院栄養食事指導料を算定しました。退院後、当院で引き続き食事指導を行っていく場合、外来栄養食事指導料の算定は2回目以降の扱いになりますか。
- 自院において、その患者さんに対する外来栄養食事指導の実施が初めてであれば、外来栄養食事指導料の「初回」の場合の点数を算定できます。
小児科外来診療料
- 当院では小児科外来診療料を算定しています。当院に受診中の患者さんが月の途中で6歳の誕生日を迎えた場合、誕生日前の受診分は小児科外来診療料で算定、誕生日以後の受診分は通常の出来高算定となるのでしょうか。
- 6歳の誕生日を迎える月の小児科外来診療料の算定は、当該月に誕生日前に受診があり小児科外来診療料を算定した場合は、当該月の誕生日以後の受診分も全て小児科外来診療料を算定します。当該月の誕生日前に受診がない場合は、誕生日後の受診分から出来高算定となります
小児科外来診療料
- 当院は小児科外来診療料を算定しています。午前中に6歳未満の患者さんが受診し、小児科外来診療料を算定しました。同日の夕方に再度受診された場合、小児科外来診療料を再度算定できますか。
- 算定できません。小児科外来診療料は「1日につき」算定する点数です。同日再診があった場合でも、小児科外来診療料は1回のみの算定となります。
小児科外来診療料の同日再診
- 小児科外来診療料を算定した患者の同日再診について、同日再診を行った時間が①時間内の場合、②時間外の場合、診察料等はそれぞれどのように算定しますか。
- ①小児科外来診療料のみ算定、②小児科外来診療料と同日再診に係る(再診料の)時間外加算を算定します。小児科外来診療料を算定する場合、当該患者に対し同一日に2回以上診察を行ったとしても、1日につき当該診療料を1回のみ算定します。ただし、それらの診察が初再診料の時間外加算等の対象となる場合、当該加算は診療料とは別に算定できます。なお、同日再診が電話等によるものだった場合も同様ですが、外来受診がなく電話再診のみ行った日は、小児科外来診療料は算定せず再診料(乳幼児加算又は時間外加算等を含む)を算定します。
小児科外来診療料の例外
- 当院は小児科外来診療料を算定している医療機関です。この場合、原則として6歳未満のすべての外来患者に対して小児科外来診療料を算定することとされていますが、例外となるのはどのような場合が該当しますか。
- 電話等による再診の場合、パリビズマブ(シナジス)を投与している場合(投与当日に限る)、自院で小児かかりつけ診療料を算定する場合、自院又は他院で在宅療養指導管理料を算定している場合等が該当します。これらの場合は6歳未満の外来患者であっても小児科外来診療料を算定せず、出来高点数で算定します。
ニコチン依存症管理料と敷地内禁煙
- ニコチン依存症管理料を届け出る場合に、施設基準で「敷地内が禁煙であること」が求められますが、クリニックの屋上や職員駐車場など、患者さんが立ち入らない場所に喫煙コーナーを設けることは認められますか。
- 認められません。「屋内禁煙」の場合は、屋上や患者さんが立ち入らない別棟の建物等に喫煙コーナーを設けることができますが、「敷地内禁煙」の場合は認められません。なお、正式に「喫煙コーナー」として設置していなくても、実態として喫煙場所として使用されている実態がありそれを黙認していた場合、敷地内禁煙が実施されていないとみなされた事例がありますのでご留意ください。
禁煙成功後の補助剤の処方
- ニコチン依存症でチャンピックスを投与し、ニコチン依存症管理料を算定している患者さんの禁煙治療が成功しました。その後この患者さんから「不安なのでチャンピックスを延長して投与してほしい」旨の希望があった場合、どのように保険請求をするのでしょうか。
- 本件は保険診療で算定するのではなく、自費診療になります。ニコチン依存症の治療が成功し保険診療は終了しましたので、予防医療として行う場合は保険診療の範囲外です。
救急救命管理料
- 救急隊の救急救命士に、患者さんの救命に必要な処置を指示しました。この場合、救急救命管理料は算定できますか。
- 算定できません。救急救命管理料は、「患者の発生した現場に『医療機関の』救急救命士が赴いて必要な処置等を行った場合において、当該救急救命士に対して必要な指示を行った場合に算定する」とされています。算定対象となるのは医療機関に所属する救急救命士に処置等の指示を行った場合であり、救急隊など医療機関以外に所属する救急救命士に指示等を行った場合は算定対象とはなりません。なお、医療機関に所属する救急救命士であれば、自院だけではなく他の保険医療機関に所属する救急救命士に処置等を指示した場合も救急救命管理料を算定することができます。この場合、指示等を行った医師の所属する医療機関が当該管理料を算定し、救急救命士の処置等にかかる費用については、医療機関相互の合議により精算します。
薬剤総合評価調整管理料
- 当院に外来通院し6種類の内服薬を処方していた患者さんが他院に入院し、入院先医療機関で3種類に減薬されました。退院後再び自院に通院し、その3種類の内服薬を処方していくことになりました。この場合、薬剤総合評価調整管理料は算定できますか。
- 算定できません。薬剤総合評価調整管理料は6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、当該処方の内容を総合的に評価及び調整し、当該患者に処方する内服薬が2種類以上減少した場合に算定するものです。実際に減薬を行ったのは入院先医療機関であるため、減薬後の患者を受け入れただけでは算定できません。
宛名のない紹介状
- 当院かかりつけの患者さんが転居するため、宛名をつけずに診療情報提供書を作成しました。診療情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。
- 算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)は別の医療機関での診療の必要を認め、紹介先に文書を添えて患者を紹介した場合に算定し、医療機関の指定が必須です。
診療情報提供料
- 他医療機関から紹介状を持って来院した患者さんについて、紹介元医療機関に返書を作成しました。診療情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。
- 算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)は、診療にもとづき他の医療機関での診療の必要を認め、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った際に算定できるものです。紹介に対する単なる返書の作成は算定要件を満たしません。
診療情報提供料(Ⅰ)の同月2回算定
- 1人の患者に対し、2つの医療機関宛に診療情報提供書を書くことになりました。診療情報提供料(Ⅰ)は同月に2回算定できますか。
- 算定できます。診療情報提供料(Ⅰ)は医療機関ごとにそれぞれ月1回算定することができます。
診療情報提供料Ⅰ
- 同一月内で、同一保険医療機関の複数の診療科に一人の患者さんを紹介しました。診療情報提供料はそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)は紹介先医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定するものです。診療科が異なったとしても同一の医療機関として取り扱うため、算定は月1回に限られます。
他院からの診療情報提供依頼
- 当院かかりつけの患者さんが転んで骨折し、自院の紹介によらず他院に入院しました。入院先の医療機関から、患者さんの診療に関する情報を送ってほしいと言われたため、診療情報提供書を作成して送付しました。この場合、診療情報提供料(Ⅰ)は算定できますか。
- 算定できません。診療情報提供料(Ⅰ)の算定要件は診療に基づき紹介ですので、要件に合致しないため算定することはできません。また、他の医療機関から診療情報提供の求めがあった場合、療養担当規則では適切に対応しなければならないとされています。
療養情報提供加算
- 訪問看護ステーションによる訪問看護を行っている患者さんの入院が決まりました。入院先医療機関へ紹介するにあたり、診療情報提供書に訪問看護ステーションから提供された訪問看護報告書を添付して情報提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)の療養情報提供加算を算定できますか。
- 単に訪問看護報告書を添付しただけでは算定できません。療養情報提供加算においては、「訪問看護ステーションから得た訪問看護に係る情報を診療情報提供書に添付する」ことが求められていますが、当該「訪問看護に係る情報」には、「ケア時の具体的な方法や留意点」、「継続すべき看護」等の情報が必要とされています。具体的には、訪問看護療養費の訪問看護情報提供療養費3において用いられる様式(別紙様式4)又はこれに準ずるものの添付が必要です。
傷病手当金意見書交付料
- 先月まで受診していた患者さんから先月の期間に対する傷病手当金意見書の交付を求められました。今月は診療をしていませんが、先月まで患者が労務不能だったことを証明し、傷病手当金意見書交付料を算定できますか。
- 算定できます。傷病手当金意見書交付料は医師が労務不能と認め証明した期間ごとに算定できます。本件では、レセプトは、診療実日数は0日、傷病名欄、診療開始日を記載し、傷病手当金意見書交付料のみを請求します。
傷病手当金意見書交付料
- 患者から傷病手当金に係る意見書の交付を求められました。意見書に記載する期間に加入していた保険者と、意見書交付時点で加入している保険者が違う場合、傷病手当金意見書交付料はどちらの保険者に請求を行うのですか。
- 意見書を交付した時点で加入している保険者に請求を行います。例えば、現在国保加入者で社保加入時の療養に関する意見書を交付した場合、国保に請求します。
精神通院医療と傷病手当金意見書
- 精神通院医療(21公費)の受給者証をお持ちの患者さんに、精神障害による業務不能期間に係る傷病手当金意見書を交付しました。傷病手当金意見書交付料は公費の給付対象となりますか。
- 対象となりません。精神通院医療の公費が給付される範囲は、「対象の精神障害及び精神障害に起因して生じた病態に対して医療機関に入院しないで行われる医療」と定められています。対象の精神障害による業務不能期間に係るものであっても、傷病手当金意見書の交付は当該精神障害に対する治療行為ではないため、公費の対象となりません。
被保険者死亡後の傷病手当金意見書交付料
- 亡くなった患者さんの遺族から、傷病手当金を受けるための意見書交付を求められ、交付しました。傷病手当金意見書交付料はどのように請求すればよいですか。
- 遺族から、亡くなった患者の傷病手当金意見書の交付を求められた場合、傷病手当金意見書交付料はその遺族が加入している保険者に対して請求します。
請求方法は、まず遺族のレセプトの摘要欄に「相続」と記載します。次に傷病名欄には、遺族が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名のみを、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と、意見書の対象となった傷病名の両方を記載します。
保険診療と療養費同意書
- 亡くなった患者さんの遺族から、傷病手当金を受けるための意見書交付を求められ、交付しました。傷病手当金意見書交付料はどのように請求すればよいですか。
- 遺族から、亡くなった患者の傷病手当金意見書の交付を求められた場合、傷病手当金意見書交付料はその遺族が加入している保険者に対して請求します。
請求方法は、まず遺族のレセプトの摘要欄に「相続」と記載します。次に傷病名欄には、遺族が他に療養の給付を受けていない場合は意見書の対象となった傷病名のみを、他に療養の給付を受けている場合は遺族自身の傷病名と、意見書の対象となった傷病名の両方を記載します。
保険診療と療養費同意書
- 腰痛症の患者さんに対し、保険診療による適当な治療手段がないと判断し、鍼灸における療養費同意書を発行しました。この患者さんについては当院で糖尿病の治療も行っているのですが、糖尿病に対する保険診療は継続できますか。
- 継続できます。鍼灸の施術は保険診療と並行して保険給付を受けることが禁止されているため、同意書の発行以降鍼灸の施術を受ける疾患に対して保険診療を行うことはできませんが、その他の疾患についてはその限りではありません。糖尿病の治療を続けていく中で腰痛症に対する治療行為(痛み止めの処方等も含む)が無いようご注意ください。
療養費同意書交付料
- 腰痛症の患者さんに対して、鍼灸の施術に係る療養費同意書を交付しました。療養費同意書交付料の算定にあたり、レセプトの摘要欄にどのような記載が必要ですか。
- 摘要欄に交付年月日及び同意書の病名欄に記載した病名を記載する必要があります。以前から交付年月日の記載は必要とされていましたが、これに加えて18年4月から療養費の支給対象となる病名の記載も必要となっています。
退院時薬剤情報管理指導料
- 退院時薬剤情報管理指導料は、入院中に使用した主な薬剤の名称等を患者さんの手帳に記載し、退院後の薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合に算定しますが、患者さんが手帳を所有していない場合は、新たに手帳を作成し患者さんから実費徴収してよいでしょうか。
- 実費徴収はできず、無償で交付します。なお、交付する手帳は医療機関が任意の様式で作製して差し支えありませんが、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ「患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録」、「患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録」「患者の主な既往歴等疾病に関する記録」を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳である必要があります。
薬剤情報提供料
- 6月1日に3種類の内服薬を7日分処方し、6月8日来院時に6月1日と同じ3種類の内服薬を14日分処方し、薬剤に対する情報提供を行った場合、6月8日に薬剤情報提供料を算定できますか。
- 算定できません。薬剤情報提供料は処方内容に変更があった場合にその都度算定できますが、薬剤の処方日数のみの変更の場合は算定することはできません。
在宅医療
訪問看護と同日の往診
- 定期的に訪問診療を行い訪問看護指示を出している患者さんが、訪問看護ステーションによる訪問看護を受けた後、同日に症状が急変し家族から依頼を受け往診しました。この場合に往診料を算定できますか。
- 算定できます。医療保険による訪問診療や訪問看護等は同一日に複数を実施しても主たるもののみを算定することとされていますが、訪問看護の後、患者の症状の急変等により依頼を受け往診を行った場合は、先の規定に関わらず往診料が算定できます。
強化型支援診
- 強化型の在宅療養支援診療所の届出を検討しています。施設基準の中の「緊急の往診」の件数は、往診料の緊急往診加算を算定した件数でよいのでしょうか。
- 往診料の緊急往診加算と、夜間加算、深夜加算を算定した件数をカウントします。例えば過去1年間に緊急往診加算を算定した実績が6件、夜間加算が3件、深夜加算が2件だった場合、緊急往診加算のみでは10件に満たないですが、夜間加算と深夜加算の算定件数を加えると11件となり、10件以上の実績を満たすこととなります。
在宅療養支援診療所
- 在宅療養支援診療所の届出を検討しています。施設基準の「緊急の往診」とは、どのような往診を指すのでしょうか。
- 在宅療養支援診療所の施設基準に定められている「緊急の往診」とは、「C000往診料に規定する緊急又は夜間若しくは深夜に行う往診をいう」とされております。具体的には、往診料の「緊急往診加算」、「夜間加算」、「深夜加算」を算定する往診を指しています。
皮膚欠損用創傷被覆材
- 外来受診した患者さんに、処置でデュオアクティブETを使用しました。自宅で交換してもらうため、処置で使った分とは別に渡しましたが、患者さんに渡したものも算定できますか。
- 皮膚欠損用創傷被覆材は原則、処置で使用したもの以外は別に算定出来ません。ただし、在宅療養指導管理料を算定している患者であって、在宅での療養を行っている通院困難な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む)(DESIGN―R分類D3、D4及びD5)を有する患者の褥瘡に対して使用した場合は在宅の項で算定できます。
往診料の休日加算
- 当院は日曜日は休診日です。日曜日の午前10時頃に、往診依頼があり、往診に出向きました。この場合、初診料と往診料のそれぞれに休日加算を算定できるのでしょうか。
- 算定できます。初診料には休日加算を、往診料には夜間・休日加算を算定します。それぞれの加算における「休日」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日と、1月1日、2日、3日、12月29日、30日、31日とされています。これらの日に往診を行った場合は、「夜間・休日加算」を算定できます。
往診料の同一建物居住者の取り扱い
- 同一マンションの2つの住戸のそれぞれの患者さんから同日に往診を求められました。往診料はそれぞれの患者に算定できますか。
- 算定できます。往診料には、同一建物居住者の取り扱いはありません。住戸の異なる患者からそれぞれ診療の求めがあった場合、それぞれに対して往診料を算定できます。
訪問診療の明細書記載
- 前月に往診と訪問診療を行い、当月は訪問診療のみを行いました。前月のレセプトには訪問診療日と往診日を記載しましたが、当月は記載しなかったところ返戻されました。記載する必要があるのでしょうか。
- 記載する必要があります。訪問診療を算定した月又は前月に往診料を算定している場合は、当該訪問診療及び往診を行った日を摘要欄に記載することとされています。
看取り加算
- これから訪問診療を行っていくものとして同意書の取り付け及び訪問診療の計画を作成した患者さんの病状が初回訪問診療の前に急変し、往診で看取りを行いました。この場合、看取り加算3000点は算定できますか。
- 算定できません。在宅患者訪問診療料の看取り加算は、往診または訪問診療を行い在宅で患者を看取った場合に算定できますが、今回は在宅患者訪問診療料を算定していない患者のため、訪問診療料の加算である看取り加算は算定できません。往診料と死亡診断加算を算定します。
在医総管の包括的支援加算
- 在宅時医学総合管理料の包括的支援加算の対象のひとつに、「訪問診療又は訪問看護において注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を受けている状態」があります。ここでいう経管栄養とは鼻腔栄養に限らず、胃瘻や腸瘻から栄養投与されている状態も該当しますか。
- 該当します。
在宅時医学総合管理料
- 在宅半固形栄養経管栄養法指導管理を行っている患者さんは、在宅時医学総合管理料の月2回以上訪問した場合における「別に定める状態」に該当しますか。
- 該当しません。在宅時医学総合管理料等の点数は「(1)別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」、「(2)月2回以上訪問診療を行っている場合[(1)の場合を除く]」、「(3)月1回訪問診療を行っている場合」に区分されており、(1)の点数における「別に定める状態」は別表第8の2に掲げられています。別表第8の2では、ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態がありますが、胃ろうカテーテルを使用している患者までは含まないものとされているため、在宅半固形栄養経管栄養法指導管理を行っている患者は該当しません。
在宅時医学総合管理料と在宅寝たきり患者処置指導管理料①
- 在宅時医学総合管理料を算定している患者さんに対し、鼻腔栄養や留置カテーテル設置等について在宅療養指導管理を実施しました。在宅時医学総合管理料を算定する場合は在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できませんが、用いた薬剤や特定保険医療材料も算定できないのでしょうか。
- 算定できます。在宅時医学総合管理又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定した月は在宅寝たきり患者処置指導管理料は算定できないこととされておりますが、指導管理に用いた薬剤及び特定保険医療材料は「⑭在宅」の項で算定できます。
在宅時医学総合管理料と在宅寝たきり患者処置指導管理料②
- 在宅時医学総合管理料を算定している患者さんに対し、患者さんやご家族、看護に当たる方に対して在宅療養指導管理は実施せず、医師が訪問診療時に鼻腔栄養や留置カテーテル設置等を実施した場合、処置料や処置に用いた薬剤、特定保険医療材料は算定できますか。
- 算定できません。平成27年6月30日付の厚生労働省の事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その14)」で、「C002在宅時医学総合管理料又はC002―2特定施設入居時等医学総合管理料が算定されている月において、C109在宅寝たきり患者処置指導管理料は別に算定できないこととされているが、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれる処置(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む)についても、別に算定できないのか」との問いに対し、「(答)算定できない」との答えが示されております。このため、在宅寝たきり患者処置指導管理実施の有無に関わらず、在宅寝たきり患者処置指導管理料に含まれるとされる処置料並びに薬剤料、特定保険医療材料料は算定できません。
在宅時医学総合管理料と特定疾患療養管理料
- 月2回の訪問診療を実施している患者さんに対し、月の1回目の訪問診療時に特定疾患療養管理料を算定し、2回目の訪問診療時に在宅時医学総合管理料を算定できますか。
- 算定できません。在宅時医学総合管理料は告示で「在宅時医学総合管理料を算定すべき医学管理を行った場合においては、別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用及び投薬の費用は、所定点数に含まれるものとする」とされており、特定疾患療養管理料は、この「別に厚生労働大臣が定める診療に係る費用」に該当するため、同月に算定できません。
在宅時医学総合管理料と特定保険医療材料料
- 在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料には創傷処置等の点数が包括され別に算定できませんが、包括される処置等に使用する薬剤や特定保険医療材料の費用は別に算定できますか。
- 算定できます。当該処置等に伴い在宅で必要となる薬剤(投薬を除く)及び特定保険医療材料(在宅の部に規定するものに限る)は「⑭在宅」の欄で算定できます。
看護師による皮下注射
- 週3日以上の訪問点滴注射の必要性がなく、週1日のみ看護師による皮下注射を実施した場合、在宅の部に規定されている注射薬であれば使用した薬剤の費用は算定できますか。
- 算定できます。週2日以下の注射指示であるため在宅患者訪問点滴注射管理指導料の対象とならず、使用した薬剤の費用は「33その他の注射」欄では算定できませんが、在宅の部に規定されている注射薬であれば「14在宅」欄で算定できます。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料
- 在宅で療養している患者さんに点滴注射の必要性を認め、週3日の訪問点滴注射を看護師に指示しました。しかし、3回目の訪問点滴を予定した日に患家からの求めに応じ往診を行ったため、往診時に医師が点滴をしました。訪問看護2回、往診1回で在宅患者訪問点滴注射管理指導料と使用した薬剤料を算定したところ、在宅患者訪問点滴注射管理指導料のみが減点されました。何故でしょうか。
- 在宅患者訪問点滴注射管理指導料は看護師等による週3日以上の訪問点滴注射を指示し、実際に看護師等により週3日以上の訪問点滴が実施された場合に算定できることとされております。結果として看護師等による週3日以上の訪問点滴が実施されなかった場合は、使用した薬剤料は算定できますが在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できません。お問い合わせの事例では、看護師等による訪問点滴が週2日に留まるため、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できず使用した薬剤料のみを算定することとなります。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料①
- 在宅で療養している患者さんに、医師の指示に基づき、自院の看護師による週3日の訪問点滴を行うことにしました。その際に使用した薬剤の費用は算定できますか。
- 算定できます。在宅患者訪問点滴注射管理指導料の対象となり、使用した薬剤の費用も算定できます。この場合、薬剤料は「33その他の注射」欄で算定し、在宅の部に規定されている注射薬以外も算定できます。
在宅患者訪問点滴注射管理指導料②
- 看護師に週3日の点滴指示を行いましたが、結果として看護師による点滴の実施が週2日以下となった場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できませんが、使用した薬剤の費用は算定できますか。
- 算定できます。患者の状態の変化等により週2日以下の実施となった場合、在宅患者訪問点滴注射管理指導料は算定できませんが、使用した薬剤の費用は算定できます。この場合も薬剤料は「33その他の注射」欄で算定します。
訪問点滴注射管理指導料と回路の費用
- 在宅患者さんに週3日の訪問点滴注射の必要性があり、訪問看護ステーションの看護師へ使用する薬剤、回路等を渡し、訪問点滴注射の指示を出し実施しましたが、在宅患者訪問点滴注射管理指導料、薬剤料とは別に回路の費用を算定できますか。
- 算定できません。在宅患者訪問点滴注射管理指導料及び使用した薬剤料は算定できますが、回路等の費用は在宅患者訪問点滴注射管理指導料の所定点数に含まれ、算定することはできません。また患者さんから自費で徴収することも認められていませんのでご注意ください。
なお、訪問看護指示書の交付にあたって必要な衛生材料や保険医療材料を訪問看護ステーション等に提供した場合は、衛生材料等提供加算として患者1人につき月1回に限り訪問看護指示料の所定点数に加算することができます。
7日を超える訪問点滴注射の指示
- 訪問診療を行っている患者さんの容態が急性増悪し、往診の結果、看護師による訪問点滴が2週間必要と判断しました。一度の指示書で2週間分の訪問点滴注射を指示した上で、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定できますか。
- 算定できません。在宅患者訪問点滴注射管理指導料は、週(指示日より7日間)に3日以上の訪問点滴指示を行うことが要件とされています。つまり、当該指導料における訪問点滴指示の有効期間は、医師が看護師等に指示を行った日から7日間です。7日を超える訪問点滴の指示が必要な場合は、医師の診察に基づき新たな訪問点滴の指示をすることが必要です。
医療保険による訪問看護
- 要介護認定を受けている患者さんについて、留置カテーテルを使用しているため別表第8に掲げる状態に該当していますが、医療保険による訪問看護の対象となりますか。
- 対象となりません。要介護・要支援認定を受けている患者さんは原則として介護保険による訪問看護の対象となります。例外として、別表第7(末期がんや一部の神経難病等)に該当する患者さん又は急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者さんは医療保険による訪問看護が優先されますが、別表第8はその対象とされていません。
在宅移行管理加算
- 在宅患者訪問看護・指導料の在宅移行管理加算の対象として、留置カテーテルを使用している状態にある者とありますが、ドレーンチューブを留置している者は該当しますか。
- 該当します。ただし、単に留置しているだけではなく、ドレーン又は留置カテーテル等からの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合に限り算定できます。
同日複数回訪問看護①
- 自院の看護師による訪問看護を行っている患者さんが、急性増悪により一時的に頻回の訪問看護が必要になりました。1日に複数回訪問看護を行う場合、どのように算定すれば良いですか。
- 1日に複数回訪問した場合は、訪問看護・指導料の所定点数に、難病等複数回訪問加算の訪問回数に応じた点数を加算します。難病等複数回訪問加算は、訪問看護を週4回以上行える場合(急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者、末期の悪性腫瘍等「別表第7」に規定される患者、重度褥瘡等「別表第8」に規定される患者)が対象となります。
同日複数回訪問看護②
- 急性増悪により一時的な訪問看護が必要な患者さんに対して、1日に複数回訪問看護を行い難病等複数回訪問加算を算定する場合、レセプトの「摘要」欄に特に記載が必要な事項はありますか。
- 頻回な訪問看護が必要と認めた診療日、訪問看護を行った日及びその必要を認めた理由を記載します
訪問看護時の在宅療養指導料
- 留置カテーテルを設置し在宅で療養中の患者さんに対して、自院の看護師が訪問看護の際に療養上必要な指導を30分以上行いました。B001・13在宅療養指導料(170点)は算定できますか。
- 算定できません。在宅療養指導料は、在宅療養指導管理料を算定する患者さんや器具を装着しその管理に配慮が必要な患者さんについて、療養上の指導を行うことを評価する点数ですが、「指導は患者のプライバシーが配慮されている専用の場所で行うことが必要であり、保険医療機関を受診した際に算定できるものである」とされています。よって患家で指導を行った場合は算定できません。
訪問看護指示書
- 有効期間が4月から6月にわたる訪問看護指示書を発行し、4月に訪問看護指示料を算定しました。5月に入ってから急性増悪のため頻回の訪問看護の必要性を認め、特別訪問看護指示書を発行しました。この場合、5月に特別訪問看護指示加算のみを算定できますか。
- 特別訪問看護指示加算のみの算定はできません。複数月にわたる有効期間の指示書を発行した後、有効期間内に患者の病態の変化に伴い指示内容の変更が生じた場合、改めて指示書の発行ができ、月が変わっていれば訪問看護指示料も改めて算定できます。今回のケースでは、新しい指示内容を記載した訪問看護指示書と特別訪問看護指示書を発行し、訪問看護指示料と特別訪問看護指示加算を算定します。
同一月2回目の訪問看護指示書の交付
- 訪問看護指示書を訪問看護ステーションに交付した後、同月内に患者の病態の変化に伴い改めて訪問看護指示書を発行しました。この場合、月2回訪問看護指示料を算定できますか。
- 算定できません。訪問看護指示料は、訪問看護ステーション等に交付した場合で患者1人につき月1回に限り算定します。したがって、患者の病態の変化に伴い指示内容を変更するため改めて訪問看護指示書を交付した場合でも同月内であれば1回分の点数のみとなります。
ただし、急性増悪、終末期等の事由により週4回以上の頻回の訪問看護の必要性を認め、特別訪問看護指示書を交付した場合は、特別訪問看護指示加算(100点)を加算することができます。
在宅自己注射指導管理料①
- 別の医療機関による指導管理のもと在宅自己注射を行っている患者さんが転院してきました。当院でも教育期間を経なければ、在宅自己注射指導管理料は算定できないのでしょうか。
- 算定できます。在宅自己注射指導管理料は、導入前に入院または2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定できますが、もともと在宅自己注射を行っていた患者さんが転院してきた場合はすでに教育期間を経ているので改めて自院で行う必要はなく算定できます。その際は、転医である旨のコメントを入れることが望ましいでしょう。
在宅自己注射指導管理料②
- 別の医療機関から紹介を受けた骨粗しょう症の患者さんで、在宅自己注射が必要と判断し、在宅自己注射指導管理を行った上でフォルテオ皮下注キットを処方しました。この方は糖尿病に対する在宅自己注射も行っており、当月初めに紹介元医療機関において在宅自己注射指導管理を算定しています。この場合、当院で行った骨粗しょう症に対する在宅自己注射指導管理の費用は算定できますか。
- 算定できます。在宅自己注射指導管理については、同一の患者について、2以上の医療機関が異なる疾患に対して当該指導管理を行った場合に限り、同一月であってもそれぞれの医療機関で当該指導管理料を算定できます。
在宅療養指導に用いる注射薬の処方
- 在宅自己注射指導管理料を算定しています。当該指導管理に係る注射薬のみを処方箋に記載し院外処方した場合、処方箋料は算定できますか。
- 算定できません。在宅療養指導に係る薬剤は投薬には該当しないため、処方箋料は算定できません。なお、内服薬・外用薬と一緒に注射薬を処方箋にて処方した場合、処方箋料の算定は可能です。
在宅自己注射指導管理料の導入初期加算
- インスリンの自己注射を先々月から開始した患者さんで、先月は来院しませんでした。今月来院した際、導入初期加算を先月分と併せて2月分算定することはできますか。
- 算定できません。導入初期加算は初回の指導を行ってから月1回、3月に限って算定することができますが、1月に1回算定の算定となります。
導入初期加算
- 在宅自己注射指導管理料の導入初期加算について、処方の内容に変更があった場合は1回に限り算定できる取り扱いがありますが、同じ製剤で一般的名称の異なる薬剤へ変更した場合は算定できますか。
- 算定できません。2020年改定より、別表第9に掲げる注射薬に変更があった場合に算定できることとされました。これにより一般的名称が異なるインスリン製剤の変更等、同じ製剤の中で一般的名称の変更では算定できないこととなりました。
導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算
- 2020年改定より、在宅自己注射指導管理料の加算としてバイオ後続品導入初期加算が新設されました。導入初期加算とバイオ後続品導入初期加算は併算定できますか。
- 併算定できます。バイオ後続品導入初期加算は、バイオ後続品の有効性や安全性の説明を行い処方した場合に初回算定月から3月を限度として月1回算定します。それぞれ算定要件を満たしていれば併算定できます。
トルリシティ皮下注
- 2型糖尿病の患者さんで、トルリシティ皮下注の自己注射を指導しています。1カ月間の指導管理を行った場合、在宅自己注射指導管理料は「月27回以下の場合」と「月28回以上の場合」のどちらの点数を算定しますか。
- 「月27回以下の場合」の点数を算定します。トルリシティ皮下注在宅自己注射指導管理料の「2」(複雑な場合以外の場合)は、在宅で実施するよう指示した自己注射の総回数に応じて点数を算定します。トルリシティ皮下注は週1回の投与であり、1カ月間の注射回数は4回又は5回となるため、当該点数の算定となります。
血糖自己測定器加算①
- 前問の患者さんに対し、血糖自己測定のためのセンサーやチップを支給し、自己測定した血糖値の管理をしています。在宅自己注射指導管理料に血糖自己測定器加算は算定できますか。
- 算定できます。グルカゴン様ペプチド―1受容体アゴニスト(GLP―1受容体作動薬)の自己注射を1週間に1回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行うために血糖自己測定器を使用した場合には、インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて、所定点数を算定できるとされています。トルリシティ皮下注もGLP―1受容体作動薬ですので、前問の患者さんも要件を満たせば算定対象となります。
血糖自己測定器加算②
- 2型糖尿病のためインスリン製剤の自己注射を行っている患者さんで、妊娠中の方について、1日3回の血糖自己測定を指示しています。在宅自己注射指導管理料の血糖自己測定器加算は「月90回以上測定する場合」を算定できますか。
- 算定できます。血糖自己測定器加算の「月90回以上測定する場合」と「月120回以上測定する場合」の点数の算定対象となるのは、次の場合です。①1型糖尿病でインスリン製剤の自己注射を1日1回以上行っている患者、②12歳未満の小児低血糖症の患者、③妊娠中の糖尿病患者又は妊娠糖尿病であって高リスクの患者となります。今回のケースでは、傷病名欄等で妊娠中であることが判断できないようであれば、レセプトの「摘要」欄等で補足が必要と考えます。
インスリン製剤を複数月分処方した際の注入器、注射針加算
- インスリン製剤の自己注射を行い在宅療養指導管理を実施している患者さんで、在宅自己注射指導管理料と血糖自己測定器加算、注入器加算、注入器用注射針加算を算定しています。
インスリン製剤を2月分又は3月分処方している場合は血糖自己測定器加算を1月に2回又は3回算定できるとされていますが、同様に注入器と注入器用注射針を2月分又は3月分支給している場合も1月に2回又は3回をまとめて算定できますか
- 1月にまとめて算定できません。医療機関が注入器を給付又は貸与し、注入器用注射針を給付した場合は、それぞれ支給した月に1回算定します。
複数の在宅療養指導管理
- 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者さんが新たにインスリンの自己注射及び自己血糖測定を始めました。在宅自己注射指導管理料は算定できませんが、血糖自己測定器加算及び導入初期加算は算定できますか。
- 血糖自己測定器加算は算定できますが、導入初期加算は算定できません。同一の医療機関において同一の患者に対し複数の在宅療養指導管理を行う場合、在宅療養指導管理料は主たるもののみ算定しますが、従たる指導管理に係る在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料は別に算定できるため、血糖自己測定器加算は算定できます。導入初期加算は在宅自己注射指導管理料の注の加算であるため当該指導管理料を算定しない場合は算定できません。
在宅自己導尿指導管理料
- カテーテルを留置して持続的に排尿している神経因性膀胱の患者さんに対し、訪問診療時に医師がカテーテル交換を行っている場合、在宅自己導尿指導管理料を算定できますか。
- 算定できません。在宅自己導尿指導管理料は、在宅自己導尿(患者自らが実施する排尿法)について指導管理を行った場合に算定します。したがってカテーテルを留置した持続的な導尿は該当しません。なお、在宅で寝たきりの患者さんに自ら留置カテーテルを交換するため、医師が指導管理を行った場合は、在宅寝たきり患者処置指導管理料の対象になります。
在宅酸素療法の酸素ボンベ加算
- 在宅酸素療法で酸素ボンベを使用している患者さんが、6月初回の診察前に他医療機関に入院し、7月に退院しました。6月中に使用した酸素ボンベの費用は算定できますか。
- 算定できます。6月中に診察日がない場合、6月のレセプトでは算定できませんが、在宅療養指導管理材料加算の酸素ボンベ加算は3月に3回算定できるため、7月の初回の診察時に在宅酸素療法指導管理を行った上で酸素ボンベ加算を当月分に加え、6月分と併せて2回分算定します。この場合、当月分に加え前月分も算定した旨をレセプトの摘要欄に記載します。
輸液器具等の算定
- 在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定する患者さんに輸液用器具、注射器、輸液ラインを7組支給しました。これら器具の算定はどのようになりますか。
- C160在宅中心静脈栄養法輸液セット加算とC300特定保険医療材料料の005在宅中心静脈栄養用輸液セットをそれぞれ算定します。輸液用器具、注射器、輸液ラインが6組までは輸液セット加算に含まれ、7組目は特定保険医療材料の本体、付属品を算定します。
居宅療養管理指導費
- 同一建物の居住者であるAさんとBさんに同一日に訪問診療を行い、Bさんにのみ居宅療養管理指導を実施しました。この場合、訪問診療料と同様に居宅療養管理指導費も「同一建物居住者に対して行う場合」の所定単位数を算定するのでしょうか。
- 同一建物居住者以外の単位数を算定します。在宅患者訪問診療料はAさん、Bさんともに「同一建物居住者の場合」の所定点数を算定しますが、居宅療養管理指導は同一日に複数の同一建物居住者に実施していないため居宅療養管理指導費の「同一建物居住者に以外の者に対して行う場合」の所定単位数を算定します。
情報提供不要の居宅療養管理指導費
- 居宅療養管理指導費はケアマネジャーへの情報提供を行った上で算定することとされていますが、介護保険による他のサービスを利用していないためケアマネジャーがついていない患者さんに対しては、情報提供をしていなくても算定できますか。
- 算定できます。居宅療養管理指導費の算定にあたっては、ケアマネジャーへの情報提供が前提とされていますが、ケアマネジャーがついていない患者さんの場合、情報提供は不要です。ケアマネジャーがついていない場合とは、①居宅療養管理指導以外の介護サービスを利用していない場合、②自らケアプランを作成している場合、が該当します。
複数医師指導の居宅療養管理指導費
- 同一月において、同一の患者さんに対して、当院の2名の医師がそれぞれ別の日に訪問診療を行いました。この場合、それぞれの訪問診療日に居宅療養管理指導費を算定できますか。
- 算定できません。居宅療養管理指導費は、1人の介護保険利用者に対して主治の医師及び歯科医師のみが月2回まで算定することとされています。同一医療機関の複数の医師が指導を行った場合も、1人の医師によるものしか算定できません。
検査
HbA1c
- 慢性膵炎の患者さんに、HbA1cを実施したところ減点されました。何故ですか。
- 慢性膵炎は糖尿病を合併するケースがあり、HbA1cで血糖等の状態を評価することは必要と考えられますが、その場合は傷病名欄に「糖尿病」又は「糖尿病の疑い」の病名が記載されているか、若しくは摘要欄に糖尿病の合併を疑った旨の詳記が必要とされております。これらの記載が無く、慢性膵炎の患者さんにHbA1cを実施した場合は減点される可能性がありますのでご注意ください。
1・5AGとヘモグロビンA1c
- インスリン治療を開始して間もない患者に対して1・5AGとヘモグロビンA1cの検査の必要性を認めましたが、同一月内に2項目算定できますか。
- 算定できます。1・5AG、グリコアルブミン、ヘモグロビンA1cのうちいずれかの検査を同一月内に併せて2回以上実施した場合は月1回に限り主たるもののみ算定できますが、次の患者に対してはいずれか1項目を月1回に限り別に算定できます。①妊娠中の患者、②1型糖尿病患者、③経口血糖降下薬の投薬を開始して6か月以内の患者、④インスリン治療を開始して6か月以内の患者。今回のケースは④にあてはまるものと思われますので、それぞれ算定できます。
血糖自己測定器加算と血糖検査
- 在宅自己注射および血糖自己測定を行っている患者に対して、外来受診時に血糖測定の必要性を認めたため院内で血糖検査を行った場合、検査料等は算定できますか。
- 算定できます。在宅療養指導管理加算の血糖自己測定器加算を算定している患者さんであっても、外来受診時に血糖測定の必要性を認めた場合には、当該検査の費用も別に算定できます。
PSAの摘要欄記載
- 前立腺がんを疑ってPSAを施行し、転帰を中止としました。3か月後、再度前立腺がんを疑ってPSAを施行しました。摘要欄には前回の検査値及び実施日の記載は必要ですか。
- 不要です。前立腺がん疑いの転帰を一度中止にし、新たに疑い病名を起こして算定する場合は初回扱いとなります。
腫瘍マーカー
- 悪性腫瘍の疑いのある患者さんに、画像診断と腫瘍マーカーを実施する予定でしたが、画像診断の機器がトラブルのため使用できず腫瘍マーカーのみを実施したところ、腫瘍マーカーが減点されました。画像診断未実施の患者さんには、腫瘍マーカーは算定できないのでしょうか。
- 腫瘍マーカーは画像診断が必須とはされておりませんが、「診療及び腫瘍マーカー以外の検査の結果から悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる場合」に算定することとされております。お問い合わせの事例では、腫瘍マーカー以外の検査が実施されておらず、また症状詳記等も無かったため、「悪性腫瘍の患者であることが強く疑われる場合」に該当しないと判断されたものと思われます。
溶連菌検査後の細菌培養同定検査
- 溶連菌感染を疑い、A群β溶連菌迅速試験定性を実施、結果が陰性だったため引き続き細菌培養同定検査を実施しました。検査料はそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。A群β溶連菌迅速試験定性検査の結果が陰性で引き続き細菌培養同定検査を実施した場合も、溶連菌検査の所定点数のみ算定することとされています。A群β溶連菌迅速試験定性検査(130点)は、細菌培養同定検査(「1 口腔、気道又は呼吸器からの検体」160点)よりも低い点数とされていますが、細菌培養同定検査を算定することは認められていません。
インフルエンザの診断
- 高熱で来院した患者さんの症状や同居家族の状況等から強くインフルエンザが疑われる場合、迅速検査を実施しなくても抗インフルエンザ薬を投与できますか。
- 症状等からインフルエンザの確定診断がなされる場合は、検査を行っていなくても抗インフルエンザ薬を投与できます。
連日の検査の算定
- 患者さんがインフルエンザの疑いで来院し迅速検査を行いましたが結果は陰性でした。翌日も来院され、再度検査を実施したところ陽性となりました。連日の検査となりますが、それぞれ算定できますか。
- 算定できます。その場合は検査を2回実施した理由(「1回目は陰性だったが、偽陰性を疑い翌日再度実施しインフルエンザ確定」等)を摘要欄に記載してください。
ヘリコバクター・ピロリ感染診断
- 先日、慢性胃炎で受診中の患者さんにヘリコバクター・ピロリ感染を疑い、迅速ウレアーゼ試験を実施したところ減点されました。何故でしょうか。
- ヘリコバクター・ピロリの感染診断は、通知でプロトンポンプインヒビター製剤(PPI)等のヘリコバクター・ピロリに対する静菌作用を有するとされている薬剤が投与されている場合は、感染診断にあたって当該静菌作用を有する薬剤の投与中止又は終了後2週間以上経過していることが必要、とされています。お問い合わせの事例では、既に慢性胃炎に対してPPIが投与されており、迅速ウレアーゼ試験を実施した時点でも服用中とのことでしたので、PPI投与中止又は終了後2週間以上経過しているという要件を満たしていないため、減点されたものと思われます。
なお、ヘリコバクター・ピロリ感染診断のうち「抗体測定」に限り、当該通知の規定に関わらずPPIを休薬せずに実施した場合も算定できる旨が、厚生労働省の事務連絡で示されております。
抗シトルリン化ペプチド抗体検査
- 7月に関節リウマチ疑いで抗シトルリン化ペプチド抗体(抗CCP抗体)定性検査を実施し陰性だった患者に対して、確定診断がつかないため10月に再度実施しました。レセプトに記載すべき事項はありますか。
- 「摘要」欄に「未確」と表示し、7月の検査実施日及び検査値、今回の検査実施日及び検査値を記載します。関節リウマチを疑うものに対して、抗CCP抗体定性・定量検査は原則として1回に限り算定しますが、結果が陰性の場合は3月に1回に限り算定できるものとされています。上記に該当し、2回以上算定する場合は、「未確」と表示した上で、当該検査の実施年月日と検査値をすべて記載することとされています。
同一起因菌の細菌顕微鏡検査
- 足白癬と爪白癬を疑い、足と爪それぞれの部位から検体を採取して細菌顕微鏡検査を行いました。部位毎に細菌顕微鏡検査は算定できますか。
- 算定できません。2020年改定より同一起因菌によると判断される場合であって、複数部位から当該起因菌を検索する目的で細菌顕微鏡検査を行った場合、主たる部位のみの算定となりました。
複数の方法による塗沫検査
- 一つの喀痰から抗酸菌塗沫検査、グラム染色法による塗沫検査を同時に行いました。この場合、塗沫検査を2回算定することはできますか。
- 算定できません。塗沫検査の検査料はD017排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査で算定しますが、染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、各種の方法を2以上用いた場合であっても、1回として算定します。
同一菌に対する複数検体の培養同定
- 細菌培養同定検査で、同一の菌を培養するため異なった部位から複数の検体を採取した場合、それぞれ算定できますか。
- 算定できません。1回のみ算定します。症状などから同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検査する目的で異なった部位や同一部位の複数箇所から採取しても、主たる部位又は1部位のみの点数となります。
細菌培養同定検査と大腸菌血清型別
- 細菌培養同定検査の結果、大腸菌が確認されたため、血清型を鑑別するために大腸菌血清型別を実施したところ、細菌培養同定検査と微生物学的検査判断料が減点されました。なぜでしょうか。
- 「D012-32大腸菌血清型別」は「D018細菌培養同定検査」により大腸菌が確認された後、血清抗体法により大腸菌のO抗原又はH抗原の同定を行った場合に算定することとされており、細菌培養同定検査の実施が前提とされていますが、通知で「D018細菌培養同定検査の費用は別に算定できない」とされております。このため、細菌培養同定検査が減点され、他に微生物学的検査判断料を算定すべき検査料が算定されていなかったため、微生物学的検査判断料も減点されたものと思われます。
細菌薬剤感受性検査
- 細菌感染症を疑い月末に細菌培養同定検査を行ったところ、菌が検出されたため、引き続き細菌薬剤感受性検査を実施しました。薬剤感受性検査の実施が翌月となったのですが、翌月は患者さんが来院しなかったため再診料を算定せずに、実日数1日として微生物学的検査判断料と細菌薬剤感受性検査のみを算定したところ、レセプトが返戻されました。なぜでしょうか。
- 質問の事例のように細菌薬剤感受性検査の実施が月をまたぎ、かつ患者さんが来院しなかった場合は、再診料を算定しないため実日数は「0日」となります。なお、微生物学的検査判断料は、前月の細菌培養同定検査の際に算定しているため、当該月は算定しません。
検査翌月の検査判断料
- 8月末に細菌培養同定検査を実施し、9月になって陽性の結果が出たため薬剤感受性検査を実施しました。8月に細菌培養同定検査と同時に微生物学的検査判断料を算定していますが、9月に薬剤感受性検査を算定する場合、月が変わっているため微生物学的検査判断料を再び算定できますか。
- 算定できません。9月に実施した薬剤感受性検査は8月の培養同定検査と一連のものであるため、月が変わっていても微生物学的検査判断料は1回のみの算定となります。
細菌培養同定検査後の薬剤感受性検査
- 細菌培養同定検査を実施し、後日、菌が検出されたため、薬剤感受性検査を実施しました。当月は受診が1日のみであったため実日数1日となりますが、検査料はそれぞれ算定できますか。
- それぞれ算定できますが、レセプトに「細菌培養同定検査実施後、患者が来院しなかった」旨を記載する必要があります。薬剤感受性検査は、細菌培養同定検査が陽性だった場合にのみ算定できるものであり、また細菌培養同定検査の結果が出るまでは数日間を要します。そのため、実日数1日で両検査を算定する場合は、患者の来院がその後なかったことがわかるようコメントを入れる必要があります。
クラミジア・トラコマチス核酸検出
- 泌尿器、生殖器、咽頭から検体を採取し、それぞれに対してクラミジア・トラコマチス核酸検出を実施した場合、所定点数を検体ごとに算定できますか。
- 算定できません。平成20年3月28日付けの事務連絡で、「主たるもののみ1つを算定する」とされており、検体ごとには算定できません。
時間外緊急院内検査加算
- 深夜に当院を受診した患者さんに対し、超音波検査を実施しました。時間外緊急院内検査加算を算定できますか。
- 算定できません。時間外緊急院内検査加算は「緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において、当該保険医療機関内において検体検査を行った場合」に算定するとされています。超音波検査は検体検査ではないため、時間外緊急院内検査加算は算定できません。
外来迅速検体検査加算
- 外来迅速検体検査加算の対象となる検体検査を6項目行い、5項目が当日中に検査結果を得ることができました。当日中に結果が得られなかった1項目の検査料を算定せずに、5項目のみを実施したとして外来迅速検体検査加算を算定できますか。
- 算定できません。外来迅速検体検査加算は、同日に実施した加算対象となるすべての検体検査について、同日中に結果を説明するとともに患者さんに文書で情報を提供し、結果に基づく診療を行った場合に算定するとされています。実施した対象となる検査の中で当日中に検査結果を得ることができないものがある場合は、算定要件を満たさないこととなります。従って、当該検査を算定せずに外来迅速検体検査加算を算定することはできません。
外来迅速検体検査加算
- 外来迅速検体検査加算の加算対象検査である尿一般、HbA1c、TP、AST、ALTの5項目行いました。そのうち、当日に説明と文書による情報提供を行った項目が尿一般とHbA1c、の2項目で、TP、AST、ALTの3項目は当日に結果が出ず、説明が行えませんでした。外来迅速検体検査加算は2項目分算定できますか。
- 算定できません。外来迅速検体検査加算は、当日行った加算対象検査全てについて、当日中に説明と文書による情報提供が行われた場合に算定できます。加算対象検査のうち、1項目でも当日中に結果報告できなければ、外来迅速検体検査加算は算定できません。
外来迅速検体検査加算
- アデノウイルスやインフルエンザウイルス感染症を疑い、迅速検査キットを用いて感染診断を行った場合、検査結果を文書で提供すれば外来迅速検体検査加算を算定できますか。
- 算定できません。外来迅速検体検査加算は、入院外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定める検査について、結果について検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、所定点数に加算することとされています。アデノウイルスやインフルエンザウイルスの迅速検査キットを用いた検査は、外来迅速検体検査加算の対象となる厚生労働大臣が定める検査に該当しないため、加算できません。
迅速キットを用いた場合の外来迅速検体検査加算
- アデノウイルスやインフルエンザウイルス感染症を疑い、迅速検査キットを用いて感染診断を行った場合、検査結果を文書で提供すれば外来迅速検体検査加算を算定できますか。
- 算定できません。外来迅速検体検査加算は、入院外の患者に対して実施した検体検査であって、別に厚生労働大臣が定める検査について、結果について検査実施日のうちに説明した上で文書により情報を提供し、当該検査の結果に基づく診療が行われた場合に、所定点数に加算することとされています。アデノウイルスやインフルエンザウイルスの迅速検査キットを用いた検査は、外来迅速検体検査加算の対象となる厚生労働大臣が定める検査に該当しないため、加算できません。
心臓超音波検査と心電図検査
- 心電図検査と心臓超音波検査を算定したところ、心電図検査が査定されました。心電図検査は他の検査と併せて算定できないという規定は無いと思うのですが、心臓超音波検査とは併せて算定できないのでしょうか。
- 心電図検査の告示、通知には他の検査と併せて算定できない旨の規定はありませんが、心臓超音波検査の告示、通知には「心臓超音波検査に伴って同時に記録した心電図、心音図、脈派図及び心機図の検査の費用は、所定点数に含まれる」との規定があります。今回の査定は、この規定によるものと思われます。
なお、心電図検査の結果を受け精査目的で続けて心臓超音波検査を実施した場合は算定可能ですが、経過の詳記をお勧めします。
超音波検査の減算
- 月の始めに腹部超音波検査を行い、3日後に経胸壁心エコー検査を行いました。心エコー検査は2回目として100分の90に減算する必要がありますか。
- 減算をする必要はありません。点数表上、Aモード法、断層撮影法、心臓超音波検査、ドプラ法、血管内超音波法は別検査とみなされます。同月内にそれぞれの区分を1回ずつ行った場合は減算をする必要はありません。
乳腺に対する断層撮影法
- 乳腺症の患者さんに対し、エコー検査を行いました。D215超音波検査の断層撮影法「ロ⑴胸腹部(530点)」で算定できますか。
- 算定できません。乳腺、睾丸、腋窩、皮下腫瘍等体表に近いものに対する超音波検査は「ロ⑶ その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等)(350点)」で算定します。なお、前立腺、腹部大動脈、胸部大動脈は「ロ⑴胸腹部」に該当します。
残尿測定検査①
- 超音波検査による残尿測定検査を実施した患者さんに、同一月に導尿による残尿測定検査を実施した場合、「超音波検査によるもの55点」+「導尿によるもの45点×90/100」を算定できますか。
- どちらも100/100で算定します。残尿測定検査は同一月2回目の算定であっても逓減とならず100/100で算定します。ただし、月2回が上限となり、3回目以降は算定できませんのでご注意ください。
残尿測定検査②
- 超音波検査による残尿測定検査を実施した患者さんに、同一日に導尿による残尿測定検査を実施した場合、それぞれの点数を算定できますか。
- 算定できません。同一日に超音波検査による残尿測定検査を実施した患者さんに、同一日に導尿による残尿測定検査を実施した場合、主たるもののみを算定します。
DEXA法による大腿骨撮影
- 骨粗しょう症の診断のためDEXA法による大腿骨撮影を行いました。D217骨塩定量検査で算定しますが、どの区分の点数が該当しますか。
- 「2 MD法、SEXA法等(140点)」が該当します。当該点数は、DEXA法(腰椎撮影を除く)、単一光子吸収法、二重光子吸収法、MD法、SEXA法、DIP法、単色X線光子を利用した骨塩定量装置による測定及びpQCTによる測定を行った場合に算定します。
なお、DEXA法により、腰椎と大腿骨の撮影を同時に行った場合は「1DEXA法による腰椎撮影(360点)」と「大腿骨同時撮影加算(90点)」により算定します。
患者希望による骨塩定量検査
- 患者さんが、半年に1回程度の骨塩定量検査を希望しています。この場合、保険診療で骨塩定量検査を実施できますか。
- 保険診療として行うことはできません。骨塩定量検査は骨粗しょう症の診断及びその経過観察の際に行うものです。単に患者さんの希望により行なう場合は、健康診断として扱います。
骨塩定量検査
- 骨粗しょう症の経過観察のため5月15日に骨塩定量検査を実施しました。前回の実施日は1月24日でしたが、検査料は算定できますか。
- 算定できます。骨塩定量検査は骨粗しょう症の診断及びその経過観察の際に行った場合にのみ、4ヵ月に1回を限度として算定するものです。暦月で考えるため、前回の実施日が1月24日であれば、5月1日から算定可能となります。
終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
- 睡眠時呼吸障害疑いの患者さんに対し、終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定を3日連続して測定しました。終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は「一連につき」とされていますが、いつまでの期間をさすものですか。
- 終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の一連につきとは、睡眠時呼吸障害の診断が確定するまでの間をさします。
内視鏡検査のフィルム代
- 内視鏡的胃ポリープ切除術を施行し、手術当日に術後の術野確認のため、内視鏡写真診断を行った場合、内視鏡検査料は別に算定できないとされていますが、使用したフィルム代は算定できますか。
- 算定できません。内視鏡検査の通則では、使用したフィルムの費用を加算することは定められていますが、手術同日の場合は認められていません。
他医療機関撮影の内視鏡写真
- 当院にかかりつけの患者さんが再診時に、他の医療機関で撮影された内視鏡写真を持参し、当院で診断を行いました。この場合、診断料として70点を算定できますか。
- 算定できません。内視鏡検査の通則の3で、「当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合は、1回につき70点を算定する」と定められており、他医療機関撮影の内視鏡写真を診断した場合には70点が算定できますが、コンピューター断層撮影と同様に、初診時のみ算定できることとされております。お問い合わせの事例は再診時に診断を実施しておりますので、算定できません。
色素内視鏡法施行時の色素の費用
- インジゴカルミンを用いた色素法により胃内視鏡を行いました。胃・十二指腸ファイバースコピーの粘膜点墨法加算を算定しますが、使用した色素の費用は算定できますか。
- 算定できません。胃・十二指腸、小腸、直腸、大腸の各内視鏡において色素法を行った場合、各点数における粘膜点墨法加算に準じて算定することとされていますが、使用されたインジゴカルミン、メチレンブルー、トルイジンブルー、コンゴーレッド等の色素の費用は所定点数に含まれ、別に算定できません。
鼻腔・咽頭拭い液採取
- 溶連菌感染を疑った患者さんに迅速キットを用いて検査を行ったところ陰性であったため、同一日にインフルエンザウイルス抗原定性検査を行いました。この場合、各々の迅速検査に用いた検体の採取に係る、鼻腔・咽頭拭い液採取はそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。1回のみの算定となります。告示上、D419の「6 鼻腔・咽頭拭い液採取(5点)」は、同じくD419の3の動脈血採取のような「(1日につき)」との記述が無く、また、通知でも1日につき1回のみの算定とする規定はありませんが、「同日に複数検体の検査を行った場合でも1日につき1回の算定となる」との疑義解釈が2016年4月25日付けの厚生労働省からの事務連絡で示されており、同一日に複数の検体採取を行っても1回のみの算定となります。
画像診断
EDチューブ挿入術
- EDチューブ挿入術は、X線透視下でEDチューブを挿入し、先端が十二指腸あるいは空腸内に存在することを確認した場合に算定するとされていますが、この場合のX線透視にかかる費用は算定できますか。
- 算定できません。透視診断(使用した薬剤含む)、画像診断の費用は所定点数に含まれ別に算定できません。
胃瘻カテーテル交換時の透視診断
- 透視下で胃瘻カテーテル交換を実施し、経管栄養カテーテル交換法を算定しました。この場合、透視診断の費用は算定できますか。
- 算定できます。透視診断は「他の処置の補助手段として行う透視については算定できない」とされていますが、J043―4経管栄養カテーテル交換法の通知で「なお、その際行われる画像診断及び内視鏡等の費用は、当該点数の算定日に限り、1回に限り算定する」とされ、また平成26年11月5日付けの厚生労働省事務連絡で、胃瘻カテーテル交換の際に併せて行った透視診断の費用は、経管栄養カテーテル交換法の算定日に限り、1回に限り算定できる旨が示されております。
他医療機関撮影のX線フィルムの読影
- 他医療機関で撮影したエックス線フィルムを患者が持参し、診断を行いました。胸部単純撮影を3枚、胸部造影剤撮影2枚を読影した場合、診断料の算定はどのようになりますか。
- 胸部単純撮影85点と造影剤使用撮影72点を算定します。他医療機関で撮影したフィルム等の診断料は撮影回数にかかわらず撮影部位及び撮影方法ごとに1回ずつ算定できます。撮影方法とは単純撮影、特殊撮影、造影剤使用撮影又は乳房撮影を指します。
他院撮影エックス線の読影
- 同一の患者さんで、他院で撮影したエックス線単純撮影のフィルム2枚(頚椎・腰椎)を読影しました。病名は頚椎椎間板症と腰椎椎間板症です。この場合、写真診断料はそれぞれ85点を算定できますか。
- 算定できます。他の医療機関で撮影したフィルム等の診断料は、撮影部位及び撮影方法別に1回ずつ算定できます。撮影部位については、通常同一フィルム面に撮影し得る範囲(胸椎下部と腰椎上部など)を同一部位とみなすため、頚椎と腰椎については別部位と考えます。
対称部位の撮影
- 右膝関節症の診断において、右膝関節のエックス線撮影を行うと同時に、比較のため左膝関節も撮影しました。別部位として撮影診断に係る所定点数をそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。耳・肘・膝等の対称器官又は対称部位の健側を患側の対称として撮影する場合の撮影料、診断料については、同一部位の同時撮影を行った場合と同じ取扱いとなります。
肉離れの診断に伴うXーP撮影
- 肉離れの患者さんに対し診断目的でX―P撮影を行ったところ、査定されました。骨折と鑑別するために実施したのですが、認められないのでしょうか。
- 骨折の疑いを伴う患者さんに対するX―P撮影の算定は認められます。お問い合わせの事例では、骨折の疑い病名が記載されておらず、X―P撮影の必要性がレセプト上では認められなかったものと思われます。
CTの造影剤使用加算
- ガストログラフィンを経口投与し、造影CTを行います。造影剤使用加算は算定できますか。
- 算定できません。造影剤使用加算は静脈内注射、点滴注射、腔内注射及び穿刺注入等により造影剤を使用した場合に算定します。経口より造影剤を投与した場合は対象外となります。
同時に行った複数部位のCT撮影
- 頭痛と腹痛を訴えて来院した患者に対し、それぞれ別の疾患を疑い、頭部及び腹部のコンピューター断層撮影(以下、CT撮影)を同日に行いました。CT撮影の費用はそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。同時に行われたCT撮影の費用は、スライスの数、疾患の種類数又は撮影部位の数に係らず、一連として主たるもののみ算定します。ただし、同日であっても、患者の状態の変化により必要に応じて行った場合はこの限りではありません。この場合はレセプトの摘要欄に症状詳記の上、2回目以降の撮影の費用は所定点数の100分の80で算定します。以上の取扱いは、磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)においても同様です。
他医療機関撮影の画像の算定①
- 初診の患者が他医療機関で撮影したCT画像を持参し、診断を行いました。診断料は算定できますか。
- 算定できます。他医療機関で撮影されたコンピュータ断層撮影のフィルムについて診断を行った場合、初診料を算定した日に限りコンピュータ断層診断料が算定できます。
他医療機関撮影の画像の算定②
- 初診時に他医療機関で撮影したCT画像について診断を行いコンピュータ断層診断料を算定した患者に対し、同一月内に自院でMRI撮影を行いました。コンピュータ断層診断料を再度算定できますか。
- 算定できません。コンピュータ断層診断料は撮影の種類や回数、また自院他院での撮影にかかわらず月1回の算定に限られます。ただし撮影料は算定して差し支えありません
投薬
療養病床退院時の処方
- 療養病棟入院基本料を算定している患者さんが退院後に介護老人保健施設へ入所することになりました。退院時に老健施設において使用する薬剤を投与した場合、薬剤料を算定できますか。
- 算定できません。療養病棟入院基本料のように投薬に係る費用が包括されている入院基本料又は特定入院料を算定している患者さんに対しては、退院後に在宅において使用するための薬剤(在宅医療に係る薬剤を除く)を投与した場合に限り薬剤料を算定できることとされています。介護老人保健施設はこの規定における「在宅」の取り扱いとはなりません。
介護保険や自立支援等からの重複給付とならないよう「在宅」の範囲は自宅の他に一定の施設が定められています。
退院時の院外処方
- 入院患者が退院し在宅療養へ移行します。この患者さんに院外処方により退院時処方を行い、処方せん料を算定できますか。
- 算定できません。退院時の投薬については、服用の日の如何にかかわらず入院患者に対する投薬として扱うこととされています。入院中の患者さんに対しては院内処方で投薬しなければならず、院外処方による投薬は認められておりませんので、処方せん料も算定できません。
お盆休みの長期投与
- 14日を上限とする薬剤を定期処方しているかかりつけの患者さんがいます。次回の受診予定日が当院のお盆休みの期間にあたるため、年末年始と同様に30日分を処方しようと考えていますが、保険請求は認められるでしょうか。
- 特殊の事情(海外への渡航、年末・年始等)の場合は、14日を上限とされる薬剤であっても、最小限の範囲において、1回30日を限度に投与することが認めれていますが、医療機関のお盆休みは、この「特殊の事情」には該当しないため、14日分を超えて投与することは認められません。
年末年始にかかる長期投与
- 投薬期間を1回30日分を限度とする薬剤を年末年始の期間にかけて処方をする場合、特殊の事情として40日分を処方することはできますか。
- 認められていません。1回14日分を限度とされている薬剤について、年末年始等特別な事情がある場合、30日分を限度として投与できるとされていますが、1回30日限度とされている薬剤はこの様な規定がないため、日数を超えての処方はできません。
公費に係る処方箋料
- 難病の公費を持っている患者さんに対し、公費に係る薬剤とそれ以外の薬剤を1枚の処方箋で院外処方しました。処方箋料は公費を適用して算定できますか。
- 算定できます。院外処方箋に難病に係る薬剤が1剤でも含まれている場合、公費を適用して算定します。
処方した薬剤の紛失
- 当院は院外処方です。患者さんが薬局で薬剤を受け取った後、薬剤を紛失してしまいました。再度診察し、無くした日数分の薬剤を処方箋で処方した場合、保険請求できますか。
- 保険請求できません。医療機関の処方箋再発行費用と、薬局での調剤に関する費用は患者負担となります。
同日の院内・院外処方
- 来院しインフルエンザが確定した患者さんに対し、イナビルを院内で吸引させました。同時に定期薬を院外処方することはできますか。
- できます。今回のケースではイナビルは処置薬剤として算定します。同日に院内処方と院外処方で併用することは保険診療上認められていませんが、処置の項における薬剤料と処方せん料を同日に算定することは差し支えありません。
予防接種時のアセトアミノフェン処方
- 新型コロナウイルスワクチン予防接種を行い、熱が出た場合の予防投与としてアセトアミノフェンを処方しました。処方に係る費用は保険請求できますか。
- 保険請求できません。症状がなく、予防投与を目的としたものに対しては、保険請求の対象となりません。
30日を超える長期投与
- 30日を超える長期投与を行う場合、レセプトの摘要欄に何か記載する必要はありますか。
- レセプトの摘要欄等に何らかの記載をすることは求められておりません。
一般名処方加算の対象医薬品
- 後発医薬品のある医薬品は、すべて一般名処方加算の対象となるのでしょうか。
- 原則として後発医薬品のある医薬品は一般名処方加算の対象となりますが、①先発医薬品のない後発医薬品、②先発と後発の価格差がない(少ない)医薬品等、一部の医薬品は対象から除かれています。厚生労働省が公開している「一般名処方マスタ」は対象となる成分・規格が網羅されているため、マスタにないものは対象外となります。
向精神薬多剤投与①
- 向精神薬多剤投与に該当した場合、所定点数の80/100で薬剤料を算定しますが、向精神薬多剤投与に該当した薬剤のみを減算すればよいのでしょうか。
- 向精神薬多剤投与に該当した処方時に処方した、全ての薬剤料を減算します。例えば、抗不安薬を2種類、睡眠薬を3種類、向精神薬多剤投与の規定に関わらない感冒薬を1種類、外用薬の湿布薬を1種類処方した場合、所定点数を減算するのは向精神薬多剤投与に該当した睡眠薬だけではなく、同一処方で投与した抗不安薬、感冒薬、湿布薬も所定点数の80/100で算定します。
向精神薬多剤投与②
- 1回の処方で抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を4種類以上又は抗精神病薬を4種類以上投与した場合(以下、「向精神薬多剤投与」)、処方料・処方せん料は「内服薬7種類以上」の場合を算定するのでしょうか。
- 「向精神薬多剤投与の場合」の処方料(20点)、処方せん料(30点)を算定します。
向精神薬多剤投与の報告
- 9月に診療した患者で、向精神薬多剤投与に係る処方をしました。厚生局への報告はいつ行えば良いでしょうか。
- 7月から9月までに行った向精神薬多剤投与の状況は10月に報告を行います。向精神薬多剤投与を行った医療機関は毎年度4月、7月、10月、1月に、前月までの3か月間に係る向精神薬多剤投与の状況を別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告するものとされています。
向精神薬調整連携加算①
- 直近の処方が向精神薬多剤投与に該当していた患者さんに対して、今回の処方で向精神薬の種類数を減らした上で、当院の看護師に病状の変化等の確認をするよう指示しました。当院は院外処方です。処方箋料の向精神薬調整連携加算は算定できますか。
- 算定できません。処方箋料(院外処方)における向精神薬調整連携加算の算定にあたっては、減薬に係る病状変化の確認を、調剤薬局の薬剤師に指示を行うことが求められています。処方料(院内処方)の場合は、自院の薬剤師に加え、看護師又は准看護師への指示でも算定できます。
向精神薬調整連携加算②
- 直近の処方が向精神薬多剤投与に該当していた患者さんに、今回の処方で向精神薬の1日あたり用量を減らした上で、薬剤師に病状変化の確認を指示しました。減量後も引き続き向精神薬多剤投与に該当していますが、向精神薬調整連携加算は算定できますか。
- 算定できます。向精神薬の種類数又は投薬量を減らした上で病状確認の指示を行えば、その時点で向精神薬多剤投与に該当していたとしても算定できます。
耳垢水
- 耳垢栓塞除去の前処置として耳垢水を院外処方しました。処方せん料は算定できますか。
- 算定できません。処置にあたって事前使用が必要な薬剤等は院外処方もできますが、その場合は処方せん料を算定できません。院内処方する場合は薬剤料を処置の項で算定します。
同一の医療機関で同一日に発行された院外処方せん
- 患者さんが同日に内科と外科の2人の先生に受診し、それぞれ処方せんを交付する場合、2回の処方せん料を算定できますか。また何か摘要欄記載等は必要でしょうか。なお、内科と外科を標榜してそれぞれ別の医師が診療しています。
- それぞれ算定できます。複数の診療科を標榜する保険医療機関において、2以上の診療科で、異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき処方せん料を算定することができます。なお、2以上の診療科で異なる医師が処方した旨を摘要欄に記載します。
処方せん料
- 在宅自己注射指導管理を実施している患者さんに、インスリン製剤や内服薬等を院外処方で投与しています。内服の残薬があるとのことで当月はインスリン製剤のみを院外処方したところ、処方せん料が減点されました。インスリン製剤のみを院外処方した場合、処方せん料は算定できないのでしょうか。
- 算定できません。インスリン製剤等、在宅自己注射指導管理をはじめとする在宅療養指導管理に用いる在宅薬剤等を院外処方することはできますが、在宅薬剤等のみを院外処方する場合は、処方せん料は算定できません。処方せん料はあくまでも「投薬」の部の点数であり、院内処方した場合にレセプトで「⑳投薬」の項で算定される薬剤を院外処方せんで処方した場合に算定することとなります。在宅薬剤等は「⑭在宅」の薬剤として算定すべき薬剤等となりますので、在宅薬剤等のみの処方の場合は処方せん料は算定できません。
処方箋料の一般名処方加算1①
- 処方箋料の一般名処方加算1は、処方箋に記載された医薬品のうち後発医薬品のあるものについて、全てを一般名処方した場合に算定できますが、その日院外処方した医薬品が1種類のみだった場合でも算定できますか。
- 算定できません。一般名処方加算1(6点)は加算対象となる医薬品が2品目以上で、且つそのすべてを一般名処方した場合に算定できます。処方した医薬品が1品目で、その医薬品が加算対象医薬品だった場合は一般名処方加算2(4点)が算定できます。
処方箋料の一般名処方加算1②
- 一般名処方加算1を算定する場合、当該処方箋において、後発医薬品のある医薬品は一般名処方加算の対象外となっている(一般名処方マスタに載っていない)品目も含めて、全て一般名処方する必要がありますか。
- 一般名処方加算1を算定する場合、その処方箋に記載されている後発医薬品のある医薬品は、加算対象外の品目も含めて、全て一般名処方する必要があります。
特定疾患処方管理加算
- 特定疾患を主病とする患者さんであっても、特定疾患療養管理料は初診日又は退院日から1月以内は算定できませんが、特定疾患処方管理加算も同様に算定できないのでしょうか。
- 算定できます。特定疾患処方管理加算は、特定疾患を主病とする患者さんであれば初診日又は退院日から1月以内であっても算定できます。特定疾患療養管理料の算定は特定疾患処方管理加算の算定要件ではありませんので、算定漏れにはご注意ください。
特定疾患処方管理加算
- 主病を糖尿病とする患者さんで、主病以外の甲状腺機能低下症に対してチラーヂンS錠を28日分処方し、特定疾患処方管理加算の65点を算定したところ18点に減点されました。
- 特定疾患処方管理加算の65点は、特定疾患を主病とする患者であって、その主病に対して28日分以上の投薬を行った場合に算定できるものです。甲状腺機能低下症は特定疾患処方管理加算の対象疾患となりますが、今回は主病の特定疾患に対する投薬ではないため、65点の加算は算定できません。一方18点の加算は特定疾患を主病とする患者の主病以外に対する投薬についても算定できるため、18点に減点されたものと思われます。
特定疾患処方管理加算1
- 特定疾患を主病とする患者さんが、同月2回受診、それぞれ院内処方した後日、急性疾患で再度受診されました。3回目の受診時は院外処方を行いましたが、この場合、当月の特定疾患処方管理加算1(18点)は、処方料の加算として2回、処方箋料の加算として1回、計3回分それぞれ算定できますか。
- 算定できません。特定疾患処方管理加算は処方料と処方箋料のどちらにも設定されている点数ですが、加算1は処方料と処方箋料に対して合わせて月2回に限り算定することとされています。
特定疾患処方管理加算2(外用薬処方)
- 特定疾患処方管理加算2(66点)は、主病である特定疾患の治療薬を28日分以上処方した場合に算定できますが、気管支喘息に対する吸入薬等、外用薬の処方も対象となりますか。
- 対象となります。内服薬・外用薬問わず、特定疾患に対して直接の効能・効果がある薬であれば特定疾患処方管理加算2の対象となります。
特定疾患処方管理加算2(隔日投与)
- 1日おきに服用するものとして14日分の薬を投与した場合等、処方期間が28日以上となれば特定疾患処方管理加算2は算定できますか。
- 算定できます。服用日数に関わらず、処方期間が28日分以上となる場合は特定疾患処方管理加算2の対象となります。ただしこの場合、その旨がわかるよう、レセプトの「摘要」欄に「隔日投与」等のコメントが必要となります。
包括される薬剤の自費徴収
- 薬剤料が包括される医学管理料等を算定する患者さんに対し、薬剤料が高額で逆ザヤになる場合等に薬剤料を自費で負担してもらっても良いでしょうか。
- 患者さんに自費で負担させることはできません。薬剤料に限らず、包括され別に算定できない等の理由で患者さんに保険診療の療養の給付に係る費用の一部を自費負担させることは認められません。
薬剤情報提供料
- 処方内容の変更を行った場合、薬剤情報提供料は同月内でもそのつど算定できるとされていますが、内服薬3種類の薬剤の処方を同月内に1種類にした場合でも算定に問題ありませんか。
- 種類数の変更や類似する効能・効果を有する薬剤への変更、同一薬剤の服薬量の変更などが処方内容の変更にあたりますので、算定は問題ありません。なお、処方日数のみの変更は処方内容の変更には当たらないため、算定の対象にはなりません。
湿布薬の処方枚数制限
- 月初に湿布薬を63枚処方した患者が月末に再来院しました。この時に再度70枚の湿布薬を処方できますか。
- できます。原則として1処方につき63枚を超えた湿布薬は算定できないものとされていますが、別の日に処方された湿布薬について算定を妨げる規定はありません。ただし、通算の処方枚数が多すぎると査定される可能性があるため、疾患の特性や受傷範囲等に応じた適切な枚数であることが必要です。
63枚を超える湿布薬の処方
- 1回の処方で63枚を超えて湿布薬を投与する場合、院外処方せんの備考欄に何か記載する必要がありますか。
- 院外処方せんの備考欄に「疾患の特性などにより必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投与する理由」を記載します。また、レセプト請求時には、レセプトの摘要欄に同じく理由を記載します。
セルテクト錠
- 慢性気管支炎の患者さんにセルテクト錠を処方したところ、査定されました。何故でしょうか。
- セルテクト錠はアレルギー性疾患治療剤であり、効能・効果は「アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚掻痒症、湿疹・皮膚炎、痒疹」とされています。傷病名が慢性気管支炎のみとのことですので、適応外として減点されたものと思われます。
エンシュアリキッド
- 食欲不振で食事の摂取量が少なくなった患者さんにエンシュアリキッドを投与したところ、減点されました。なぜでしょうか。
- エンシュアリキッドの「効能又は効果」は、「一般に、手術後患者の栄養保持に用いることができるが、特に長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合の経管栄養補給に使用する」とされております。「食欲不振」との記載だけでは、「長期にわたり、経口的食事摂取が困難な場合」に該当しているかどうか判断がつきかねるため、減点されたものと思われます。エンシュアリキッドは「効能又は効果」としていわゆる「適応病名」ではなく、使用対象となる患者さんの状態が示されておりますので、投与している患者さんの状態が「効能又は効果」に該当することがわかるようなレセプト記載が必要です。
クラビットとビオフェルミンR
- クラビットとビオフェルミンRを同時に処方したところ、ビオフェルミンRが査定されました。ビオフェルミンRは抗生物質投与時における腸内環境の改善が適応とされていますが、クラビットとは併用できないのでしょうか。
- ビオフェルミンRはクラビットと併用できません。ビオフェルミンRの適応は「抗生物質、化学療法剤投与時の腸内菌叢の異常による諸症状の改善」ですが、併用できる抗生物質等はペニシリン系、セファロスポリン系、アミノグリコシド系、マクロライド系、テトラサイクリン系、ナリジクス酸の6種類に限定されています。クラビットはニューキノロン系の抗生物質ですので、ビオフェルミンRとは併用できません。
クレナフィンの処方
- 他院でクレナフィン爪外用液を処方されていた患者さんが当院に転院となりました。引き続きクレナフィンを処方していくにあたり、当院で真菌検査を実施する必要はありますか。
- 他院で真菌検査が実施され、爪白癬の確定診断がなされていることを情報提供文書等で確認できていれば必要ありません。その場合、他院で検査実施済みである旨を摘要欄に記載します。クレナフィン爪外用液は直接鏡検又は培養等に基づき爪白癬であると確定診断された患者に対して投与が認められています。転院患者の場合は転院元の医療機関での真菌検査の有無を確認しましょう。また、クレナフィンの標準的な投与期間は48週以内とされているため、転院元の投与開始日も併せて確認しておきましょう。
ザルティア錠
- 排尿障害を有する患者さんにザルティア錠2・5㎎を処方したところ、減点されました。排尿障害には投与できないのでしょうか。
- ザルティア錠2・5㎎及び5㎎は、「保険給付上の注意」として、①本製剤の効能・効果は、「前立腺肥大症に伴う排尿障害」であること、②本製剤が「前立腺肥大症に伴う排尿障害」以外の治療目的で処方された場合には、保険給付の対象としないこととする、とされております。また、平成26年4月17日付保医発0417第4号の通知で「本製剤の効能・効果に関連する使用上の注意において『本剤の適用にあたっては、前立腺肥大症の診断・診療に関する国内外のガイドライン等の最新の情報を参考に、適切な検査により診断を確定すること』とされており、適切な検査により前立腺肥大症と診断された場合に限り算定できること。また、診療報酬明細書の記載に当たっては、尿流測定検査、残尿検査、前立腺超音波検査等の診断に用いた主な検査について、実施年月日を摘要欄に記入すること」とされており、診断に用いた主な検査の実施年月日をレセプトの摘要欄に記載することが必要となります。
タミフルの予防投与
- インフルエンザウイルス感染症と診断した患者さんのご家族から、予防目的のタミフル(オセルタミビルリン酸塩)を求められました。この場合、保険診療で投与できますか。
- 保険診療では投与できません。自由診療となります。抗インフルエンザウイルス剤のタミフルカプセルは薬機法上の効能・効果として「インフルエンザウイルス感染症を発症している患者の同居家族又は共同生活者である下記の者(①高齢者(65歳以上)、②慢性呼吸器疾患又は慢性心疾患患者、③代謝性疾患患者(糖尿病等)、④腎機能障害患者)を対象」として予防投与が認められていますが、予防投与は保険診療の対象とはされておりません。従って、お問い合わせの事例では予防投与としてタミフルを処方することは薬機法上は可能ですが、保険診療ではなく自由診療として取り扱うこととなります。
ヒアレインミニ点眼液
- ヒアレインミニ点眼液をドライアイの患者さんに処方したところ、適応外との理由で査定されました。ドライアイの患者さんには処方できないのでしょうか。
- ヒアレインミニ点眼液はヒアレイン点眼液と異なり、添付文書の効能・効果の欄で、「ヒアレインミニ点眼液0・1%、ヒアレインミニ点眼液0・3%の保険請求については、シェーグレン症候群又はスティーブンス・ジョンソン症候群に伴う角結膜上皮障害に限る」とされているため、ドライアイに対する処方は認められておりません。
ペンレステープ
- 伝染性軟属腫の処置に使用するため、ペンレステープを患者さんに渡し貼付して頂きました。この場合ペンレステープは外用薬の投薬として、調剤料や処方料をレセプトの投薬の部で算定できますでしょうか。
- 算定できません。処置に使用する薬剤として、レセプトの処置の部においてペンレステープの薬剤料を算定します。
同一日の院内・院外処方
- みずいぼの患者さんに対して、摘除処置に使用するためのペンレステープをお渡ししました。同時に風邪薬を院外処方できますか。
- できます。同一日に同一の患者に対し院内処方と院外処方を行うことは原則として認められていませんが、ペンレステープは処置薬剤として患者に支給するため、同一日に同一の患者に対して院外処方を行っても差し支えありません。この場合、ペンレステープの薬剤料は処置の項で算定します。
維持療法が必要な難治性逆流性食道炎
- 「維持療法の必要な難治性逆流性食道炎」への投薬としてパリエット20㎎を投与しましたが、10㎎査定されました。なぜですか。
- 「維持療法の必要な難治性逆流性食道炎」においては、パリエットの投与量は1日10㎎となっています。1日10㎎の維持療法実施中に再発が認められた場合に、「逆流性食道炎」に対する再治療として1日20㎎の投与を行うことが出来ますが、8週間までの投与となりますのでご留意下さい。「維持療法の必要な難治性逆流性食道炎」に対する用法・用量は製剤により異なります。
花粉症
- 「花粉症」の病名で点鼻薬及び点眼薬を処方したところ、点眼薬が査定されました。何故ですか。
- 審査上、「花粉症」は「アレルギー性鼻炎」を指し「アレルギー性結膜炎」は含まないこととされております。今回の査定は点眼薬に対する病名漏れによる査定と思われます。一般に「花粉症」といえば「花粉等に起因するアレルギー性疾患」と捉えられておりますが、審査では「花粉症」の病名では点眼薬は適応外となってしまいます。「アレルギー性結膜炎」の病名漏れにはくれぐれもご注意下さい。
摘要欄記載の必要な薬剤:ミカトリオ配合錠
- 高血圧症に対し、テルミサルタン、アムロジピン及びヒドロクロロチアジドを一定期間併用していた患者さんへの処方を、ミカトリオ配合錠に切り替えることになりました。レセプトの摘要欄に記載すべき事項はありますか。
- ミカトリオ配合錠は、テルミサルタン80mg、アムロジピン5mg及びヒドロクロロチアジド12・5mg(以下、「3剤」)を一定の期間、同一用法・用量で継続して併用し、安定した血圧コントロールが得られている場合に切り替えを検討することとされており、切り替えた月のレセプトにおいては、次の記載が必要とされています。①「3剤」の併用療法として使用していた品名及び使用期間②「3剤」の併用療法において「安定した血圧コントロールが得られている」旨、その判断の際に参照した血圧測定値及び当該血圧測定の実施年月日
摘要欄記載の必要な薬剤:タケルダ配合錠
- 狭心症の患者さんに対して、タケルダ配合錠を処方することになりました。レセプトの摘要欄に記載すべき事項はありますか。
- 胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある旨がわかるような記載が必要です。タケルダ配合錠は、アスピリン(狭心症等の疾患又はPTCA等の術後における血栓・塞栓形成の抑制目的)とランソプラゾール(低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制目的)の配合剤です。適応は胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の既往がある患者に限られるため、そのことが判断できるようなレセプトを作成する必要があります。なお、現に胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の治療中である患者は適応外となります。
慢性心不全患者へのアーチスト錠処方
- 慢性心不全の患者に対してアーチスト錠1・25mgを投与したところ、「A 医学的に適応と認められないもの」として査定されました。どのような理由が考えられますか。
- アーチスト錠(一般名:カルベジロール)の適応のひとつとして「虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の状態が挙げられます。傷病名が単に「慢性心不全」とされていた場合、それが虚血性心疾患又は拡張型心筋症由来のものなのかどうかが不明であり、適応外とみなされた可能性があります。また、「虚血性心疾患又は拡張型心筋症に基づく慢性心不全」の状態の方であっても、適応とされているのはアンジオテンシン変換酵素阻害薬、利尿薬、ジギタリス製剤等の基礎治療を受けている方に限られますのでご留意ください。
注射
重症腋窩多汗症に対する注射
- 重症の腋窩多汗症の患者さんに、学会が作成したガイドラインに沿ってボトックス注射を行いました。注射の手技料はどの点数を算定すれば良いのでしょうか。
- G017の「腋窩多汗症注射(片側につき)200点」を算定します。なお、同一側の2箇所以上に注射を行った場合であっても、所定点数は片側につき1回の算定となります。
外来でのインスリン注射針
- 糖尿病の患者さんで、認知症により在宅での注射自己管理が困難なため外来でインスリン注射を実施しています。この場合、使用した注射針の費用は算定できますか。
- 算定できません。院内で行う注射に使用した材料(注射針、点滴用回路、衛生材料等)で特定保険医療材料以外のものの費用については手技料に含まれ、別に算定できません。
在宅自己注射指導管理料と外来での注射の費用
- 在宅自己注射指導管理料を算定している患者さんに対して、自己注射とは関連しない静脈注射を外来で実施した場合、その費用は算定できますか。
- 算定できます。在宅自己注射指導管理料を算定する場合、同月に当該自己注射に係る注射を外来で実施した場合の費用は算定できませんが、それ以外の注射であれば算定制限を受けません。
同日再診で実施した静脈注射実施料
- 同日再診で2回とも静脈注射を実施した場合、手技料を2回分算定できますか。
- 算定できます。手技料は1回につき算定できますので、同日再診で必要があって静脈注射を2回実施した場合は2回分算定します。
手術と同日に行った注射の手技料
- 汚染された挫創に対し創傷処理を実施しました。受傷した場所から破傷風の感染リスクが高いと判断し、創傷処理と同日に破傷風トキソイドを注射しました。手術と同日ですが、この注射の手技料は算定できますか。
- 算定できます。手術日の手術に関連する注射の手技料は算定できませんが、今回、破傷風の感染リスクが高いと判断し実施したトキソイド注射は、手術を行うか否かに関わらず必要なものと考えられます。従って、「手術に関連する注射」には該当せず、注射の手技料は算定できます。
注射薬の残余
- 注射でアンプル剤を使いました。全量を使い切れず、残余分は破棄をしましたが1筒として算定できますか。
- 算定できます。アンプル剤は保存が不可能なため、残余分を破棄しても1筒として算定します。
なお、バイアル剤の場合は、実際に使用した分量の薬価を薬剤料として算定します。ただし、患者が再度来院しなかった等やむを得ず残余分を破棄した場合は、破棄分を含めて算定します。この場合、明細書にその旨の注記が必要です。
カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
- 療養病棟入院基本料を算定している患者さんに対して、血液透析治療の目的でブラッドアクセス挿入を行いました。この場合、カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入の手技料を算定できますか。
- 算定できません。カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入は注射の部の点数であり、療養病棟入院基本料に包括される点数に該当するため、算定できません。
リハビリテーション
呼吸器リハの算定起算日
- 呼吸器リハビリテーション料の算定限度日数等の起算日となる「治療開始日」とは、具体的にいつを指すのでしょうか。
- 呼吸器リハビリテーションを開始した日を指します。
目標設定等支援・管理料
- 脳血管疾患等リハビリ、廃用症候群リハビリ又は運動器リハビリを算定する要介護・要支援者については、それぞれの疾患別リハビリテーションの起算日から算定日数上限の1/3を経過後、直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定していなければ、所定点数が90/100に減算されますが、
Q1 要介護・要支援認定を受けたが介護保険サービスは利用していない患者も該当しますか。
Q2 要介護・要支援認定を受けた患者で目標設定等支援・管理料を算定していないと、リハの所定点数が90/100になる患者は、算定日数上限を超えて維持期リハビリテーションに移行した患者のみですか。
Q3 要介護・要支援認定を受けた患者に対し、起算日から算定日数上限の1/3を経過するまでに、一度でも目標設定等支援・管理料を算定すれば、その後目標設定等支援・管理料を算定しなくても所定点数を90/100に減算する必要はありませんか。
Q4 算定日数上限の1/3を経過後に要介護・要支援認定を受けた場合も、目標設定等支援・管理料を算定しなければ、所定点数が90/100に減算されますか。
Q5 要介護・要支援認定の申請中に目標設定等支援・管理料を算定できますか。
Q6 要介護・要支援認定を受けた入院患者も算定日数上限の1/3を経過後、直近3か月間に目標設定等支援・管理料を算定していないと、所定点数が90/100に減算されますか。
-
Q1 該当します。
Q2 要介護・要支援認定を受け疾患別リハビリテーションを実施する全ての患者が対象です。起算日から算定日数上限の1/3(脳血管疾患等リハは60日目、廃用症候群リハは40日目、運動器リハは50日目)を経過後、直近3カ月以内に目標設定等支援・管理料を算定しなければ90/100に減算されます。
Q3 算定日数上限の1/3を経過後、疾患別リハビリテーションを実施する場合、リハビリ実施日の直近3か月以内に目標設定等支援・管理料を算定していなければ減算となりますので、リハビリが長期間に及ぶ場合は注意が必要です。
Q4 減算されます。
Q5 算定できません。要介護・要支援認定を受けた患者が対象です。
Q6 入院患者も減算の対象になります。
転院患者の目標設定等・支援管理料
- 他院で運動器リハビリを受けていた要介護被保険者である患者さんが転院し、当院でリハビリを行っていくことになりました。転院元医療機関で3月以内に目標設定等・支援管理料を算定していた場合でも、当院で当該管理料は算定できますか。算定できる場合、「初回の場合」と「2回目以降の場合」のどちらの点数を算定しますか。
- 算定できます。この場合、「初回の場合」を算定します。目標設定等・支援管理料をすでに算定している患者が他の医療機関へ転院した場合、転院先の医療機関で「初回の場合」を算定できることとされています。なお、当該管理料は3月に1回に限り算定できますが、転院元の医療機関での算定から3月以内であっても差し支えありません。
疾患別リハビリテーション
- 脳梗塞の後遺症で介護保険による通所リハビリテーションを行っている患者が骨折し、骨折に対して医療保険による疾患別リハビリテーションが必要となりました。この場合、通所リハビリテーションと疾患別リハビリテーションを併施することはできますか。
- できます。ある疾患に対して介護保険によるリハビリテーションに移行した日以降は、当該疾患に対して医療保険による疾患別リハビリテーションは原則実施できませんが、当該疾患とは別の疾患に対して医療保険によるリハビリテーションを実施することは差し支えなく、通所リハビリテーションと疾患別リハビリテーションを併施することができます。
精神科専門療法
通院精神療法の向精神薬多剤投与減算
- 1回の処方において抗不安薬を2種類、睡眠薬を2種類投与し投薬における薬剤料等が減算となる患者に対して通院精神療法を行った場合、通院精神療法の点数も100分の50の減算になりますか。
- 減算になりません。通院・在宅精神療法における向精神薬多剤投与減算(所定点数の100分の50を算定)は、1回の処方において抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗うつ薬を3種類以上投与した場合が該当し、「抗不安薬と睡眠薬を合わせて4種類以上」は含まれません。
通院精神療法(初診時)
- 初診の患者さんに対して通院精神療法を20分実施した場合に、通院精神療法の「ハ(2)30分未満の場合(330点)」は算定できますか。
- 算定できません。通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が、初診の日においては30分、再診の日においては5分を超えた場合に限り算定できます。従って、初診時において「30分未満の場合」の点数は算定できません。
在宅精神療法(再診時)
- 再診の患者さんに対して在宅精神療法を20分実施し、在宅精神療法の「ハ(3)30分未満の場合(330点)」を算定する場合、レセプトの摘要欄に特に記載が必要な事項はありますか。
- 診療に要した時間の記載が必要です。※右表をご参照ください。
通院精神療法と認知行動療法
- 通院精神療法と認知行動療法を同日に時間を分けて実施しました。この場合、通院精神療法と認知行動療法をそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。認知行動療法で算定します。I003-2認知療法・認知行動療法の注4では認知療法・認知行動療法と同一日に行う他の精神科専門療法は、所定点数に含まれるものとするとしています。
手術
露出部
- 創傷処理の真皮縫合加算を算定できる露出部とは、どのような部位が該当しますか。
- 通知では、「露出部とは、顔面、頭頸部、上肢にあっては肘関節以下及び下肢にあっては膝関節以下」とされ、さらにこれらの部位であっても「手掌、指・趾、眼瞼」は算定できない部位として示されています。
真皮縫合加算
- 手掌の切創に対し創傷処理を実施し真皮縫合加算を算定したところ、真皮縫合加算が減点されました。手掌は露出部には該当しないのでしょうか。
- 手掌は露出部には該当しますが、真皮縫合加算は算定できません。審査機関においては、眼瞼や手掌については露出部であっても真皮が存在しないため真皮縫合は行われず、加算は算定できない扱いとされております。
露出部と露出部以外が混在する手術
- 露出部と露出部以外にまたがる皮膚腫瘍に対し、「皮膚、皮下腫瘍摘出術」を行いました。腫瘍は長径の2/3程が露出部、1/3程が露出部以外に生じていました。この場合、露出部の点数を算定できますか。
- 露出部の点数で算定します。露出部と露出部以外が混在する場合の算定は、露出部に係る長さが全体の50%以上の場合は露出部の点数で、50%未満の場合は露出部以外の点数で算定します。
デブリードマン
- 左手に火傷を負った患者さんに対して第2指から第5指までデブリードマンを行いました。この場合、K002デブリードマンの点数は1指ごとに算定できますか。
- 算定できません。手術の部通則14では同一手術野が示され、主たる手術の所定点数のみを算定するとしています。デブリードマンは第1指から第5指までを同一手術野として取り扱います。
同一手術野に対する複数手術に係る費用の特例
- 帝王切開術「1緊急帝王切開」と子宮筋腫核出術「1腹式」を同時に行いました。手術料はそれぞれ算定できますか。
- 子宮筋腫核出術の所定点数に帝王切開術の100分の50に相当する点数を加えて算定します。同一手術野に同時に複数の手術を行った場合、原則として主たる手術の点数しか算定できませんが、複数手術に係る費用の特例として、別表第1又は第2に掲げられる手術については、主たる手術の所定点数と従たる手術の100分の50に相当する点数を合算して算定でき、帝王切開術と子宮筋腫核出術(腹式)の組み合わせもこの特例に該当します。なお、行った手術のうち、所定点数と「注」による加算の要件を満たす場合は加算点数を合算し、合算後点数の高い方が「主たる手術」となります。
K134椎間板摘出術とK142脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術
- 第9胸椎の椎弓切除術と、第9、第10胸椎の椎間板切除術を同時に行いました。椎間板摘出術と椎弓切除術は、複数手術に係る費用の特例(別表第1)に掲げられる組み合わせなので、特例の規定に沿ってそれぞれ算定できますか。
- 算定できません。椎間板切除術と脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術の組み合わせは、複数手術に係る費用の特例に掲げられていますが、脊椎の同一高位に対し行った場合は、主たる手術の所定点数に従たる手術が含まれるものとされています。特例が適用されるのは、脊椎の異なる高位に対して手術を行った場合に限られます。
超音波骨折治療法
- 骨折非観血的整復術を実施した患者さんに対し、治癒期間の短縮を目的に超音波骨折治療法を行った場合、K047―3超音波骨折治療法は算定できますか。
- 算定できません。K047―3超音波骨折治療法は告示及び通知で、四肢(手足を含む)の骨折観血的手術を実施した後に行われた場合にのみ算定できるとされており、骨折非観血的整復術の場合には算定できません。
虫垂周囲膿瘍を伴う虫垂切除術
- 虫垂周囲膿瘍を伴う虫垂炎の患者さんに、虫垂切除術を行いました。排液ドレーンは使用せず、生食で洗浄を行いましたが、この場合もK718虫垂切除術の「2 虫垂膿瘍を伴うもの」を算定できますか。
- 算定できます。傷病名や摘要欄の症状詳記などから虫垂周囲膿瘍を伴うことが明らかな場合や、膿瘍に対する処置として生食の使用が明らかな場合は「2 虫垂膿瘍を伴うもの」を算定できます。
子宮頚管拡張
- 流産手術を行う予定の患者さんにあらかじめ子宮頚管拡張を行い、翌日に流産手術を行いました。この場合、子宮頚管拡張と流産手術の双方を算定できますか。
- 算定できません。流産手術に伴う子宮頚管拡張は、「流産手術は原則として術式を問わず、また、あらかじめ頚管拡張を行った場合であってもそれを別に算定することなく、本区分の所定点数のみにより算定する」と通知で規定されているため、流産手術のみを算定します。
病理診断
健康診断から保険診療へ移行時の病理判断料
- 健康診断で内視鏡を行った際に病変を見つけたため、そのまま検体採取し病理診断を行いました。検体採取以降の行為として内視鏡下生検法や病理判断料等を算定できますか。
- 算定できます。健康診断の結果、治療の必要性を認め検体採取や病理組織顕微鏡検査を行った場合、その費用を保険請求できます。ただし、健康診断に含まれている費用(基本診療料や内視鏡検査の費用等)は自費徴収と並行して保険請求することができません。ポリープ切除術等内視鏡検査の費用が含まれる手術を行い、その費用を保険請求する場合は健康診断としての内視鏡検査の費用を自費徴収しないなど、峻別が必要です。
その他
高額療養費支給の多数該当
- 高額療養費の多数該当の適用を受けて自己負担限度額が軽減されていた社会保険の患者さんが、国民健康保険へ変更になりました。この場合、社会保険加入時の高額療養費の支給回数を通算して、国民健康保険加入当初より多数該当として、自己負担限度額が軽減されるのでしょうか。
- 社保から国保になった場合など、加入する保険者が変更になった場合、高額療養費の支給回数は通算しません。したがって、国民健康保険に加入した月以降、高額療養費の支給回数が1年間に4回以上になった時点で、4回目から多数該当の自己負担限度額の対象となります。
子ども医療費助成制度のレセ記載
- 公費番号83の子ども医療費助成制度の受給券で窓口一部負担金は「0円」となっている患者さんについて、一部負担金を徴収せずにレセプトの一部負担金襴を空欄として請求したところ、一部負担金を記載するようにとして返戻されました。どのように記載したらよいのでしょうか。
- 一部負担金襴には「0」を記載します。子ども医療費助成制度では窓口負担が0円となる場合がありますが、レセプトの一部負担金襴は無記入とせずに「0」と記載する必要があります。記載が無い場合は、記載事項の記載漏れと判断され返戻されます。
難病公費54①
- 難病公費54の受給者証の適用区分が「※」と記載されている場合、レセプトの特記事項の記載は受給者証の「階層区分」に応じたものになりますか。
- 応じたものになりません。「階層区分」は自己負担限度額の区分を記載したもので、医療保険の所得区分とは異なります。適用区分が「※」と記載されている場合の特記事項記載については、右表をご参照ください。
難病公費54②
- 難病公費54に係る治療を行った場合、その都度医療費を自己負担限度額管理手帳に記載するとされていますが、在宅医療等で医療費が月末に確定する場合、翌月に診療した月の欄に医療費をまとめて記載できますか。
- 記載できます。翌月に確定した医療費を請求する場合、診療月の欄に医療費を記載し、自己負担の累積額を確認した上で患者から徴収することになります。
難病医療助成公費と重度心身障害者(児)医療公費の併用
- 難病医療助成公費(54)と、重度心身障害者(児)医療公費(81)を併用した場合、(54)の自己負担上限管理票の記載と自己負担金はどのようになるのでしょうか。
- 重度心身障害者(児)医療公費(81)と他の公費制度を併用する場合、他の公費制度が優先されます。まず(54)に係る医療費総額と自己負担金額を自己負担上限管理票に記載の上、(54)の自己負担がある場合は、その窓口負担金を(81)の対象とし、(81)の自己負担金のみを徴収することになります。例として、(54)の医療費が5000円で、自己負担が1000円発生した場合(2割負担の患者さん)、その金額(1000円)を自己負担上限管理票に記載の上、(54)の自己負担1000円に対し(81)を適用して300円(自己負担がゼロの患者さんの場合はゼロ円)を徴収します。
同日再診時の81公費
- 重度心身障害者(児)医療費助成制度(81)の医療券をお持ちの患者さんについて、午前中に受診された際に自己負担金を徴収しましたが、午後に容態の変化があり同日再診されました。この場合、同日再診の分も自己負担金を徴収しますか。
- 徴収します。重度心身障害者(児)医療費助成制度では、入院外においては1回の受診ごとに自己負担金を徴収します。同日再診があった場合は、その都度徴収してください。
医療法人員標準の計算における患者数
- 医療法人員標準を算出する際に、生活保護単独や労災、自賠責などの保険診療外の患者さんを除外するのでしょうか。
- 除外しません。医療法人員標準を算出する際の患者数は、介護保険や自費によるものなど全ての患者さんを含みます。入院基本料等の届け出の場合は保険診療による入院患者のみを対象として算出しますが、医療法人員標準にかかる計算においては保険診療によるものか否かを問わず、全ての患者さんを計算対象とします。
差額ベッド代
- 室料差額が生じない病床が満床のため、やむを得ず2人室に入院させた場合、患者さんから室料差額(差額ベッド代)を徴収できますか。
- 徴収できません。保険外併用療養費制度の「特別の療養環境の提供(いわゆる差額ベッド代)」による費用徴収は、治療上の必要により特別の療養環境を提供した場合や病棟管理の必要性等から特別の療養環境を提供した場合で実質的に患者の選択によらないケースでは室料差額を徴収できません。あくまでも治療上や病棟管理上等の必要性は無いものの、患者さんの希望で特別の療養環境を提供した場合にのみ徴収できるものです。
カルテ(診療録)の保存期間
- カルテ棚が一杯になってしまったので古いカルテを処分したいのですが、カルテの保存期間は何年でしょうか。
- 患者さんの診療の完結の日から5年です。完結していない場合は保存し続ける必要があります。
看護記録の保存期間
- 病棟における看護記録の保存期間は、診療録と同じく診療の完結の日から5年間でしょうか。
- 3年間となります。看護記録は、保険医療機関及び保険医療養担当規則の第9条に規定されている療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録に該当するため、完結の日から3年が保存期間となります。
治癒証明
- 当院にインフルエンザ感染症で受診した患者さんから、「職場から治癒証明を貰って来るように言われた」と証明書の交付を求められました。この場合、証明書発行に係る費用を患者さんに負担させても良いのでしょうか。
- 一般的な診断書と同じく、費用負担を求めることができます。当該文書の交付は健康保険の給付対象外であり、また治療行為等にも該当しないため、自費で費用負担を求めることができます。
通称名が氏名欄に記載された保険証①
- 性同一性障害の患者さんの被保険者証で、表面の氏名欄に通称名、裏面の備考欄に戸籍上の氏名が記載されていました。診療報酬を請求するにあたりレセプトではどちらの氏名を使用すればよいでしょうか。
- 表面の氏名欄に印字されている氏名を使用します。性同一性障害を有する被保険者または被扶養者が被保険者証に通称名の記載を希望した場合、保険者の裁量で戸籍上の氏名と併せて通称名も記載することが可能となりました。記載方法は様々で、表面氏名欄に通称名、裏面備考欄に戸籍上の氏名が記載される場合や、表面氏名欄に戸籍上の氏名が記載された上で「通称名は○○」と併記される場合等が考えられます。いずれの場合も、診療報酬請求時は表面の氏名欄に印字されている氏名を使用します。判断に迷う場合は保険者に確認するのがよいでしょう。
通称名が氏名欄に記載された保険証②
- 被保険者証表面の氏名欄に戸籍上の氏名が印字され「通称名は○○」と併記されている患者さんが、通称名での診察券の発行を希望されました。診察券やカルテに記載する氏名と診療報酬請求に使用する氏名が異なっていても問題ないのでしょうか。
- 問題ありません。診療報酬請求に使用する氏名は必ず被保険者証表面の氏名欄に印字されているものでなければいけませんが、医療機関内で管理する診察券やカルテ等に記載する氏名はどちらを使用しても差し支えありません。カルテ等に使用する氏名とレセプトに使用する氏名が異なる場合は、より適切な管理を心掛けましょう。
労災非指定医療機関での診療
- 仕事中の怪我で受診した患者さんがいます。当院は労災非指定医療機関ですが、どのように扱えばよいですか。
- 労災非指定医療機関での診療は療養費払いとなるため、医療機関は患者さんから全額徴収します。患者さんには後日、労災診療費算定基準の範囲で償還されます。償還を受けるために様式第7号又は第16号を持参するので、それらに療養の内訳等を証明します。なお、証明に係る文書料は徴収できず、無償交付となります。
2ケタの枝番が印字された保険証
- 患者さんが、記号・番号に2桁の枝番がついた保険証を持参しました。レセコンに枝番を入力する必要はありますか。
- 入力する必要があります。ただし既に発行済の保険証で、枝番号がついていない場合は入力する必要はありません。

Copyright(c)2025 千葉県保険医協会 All Rights Reserved.