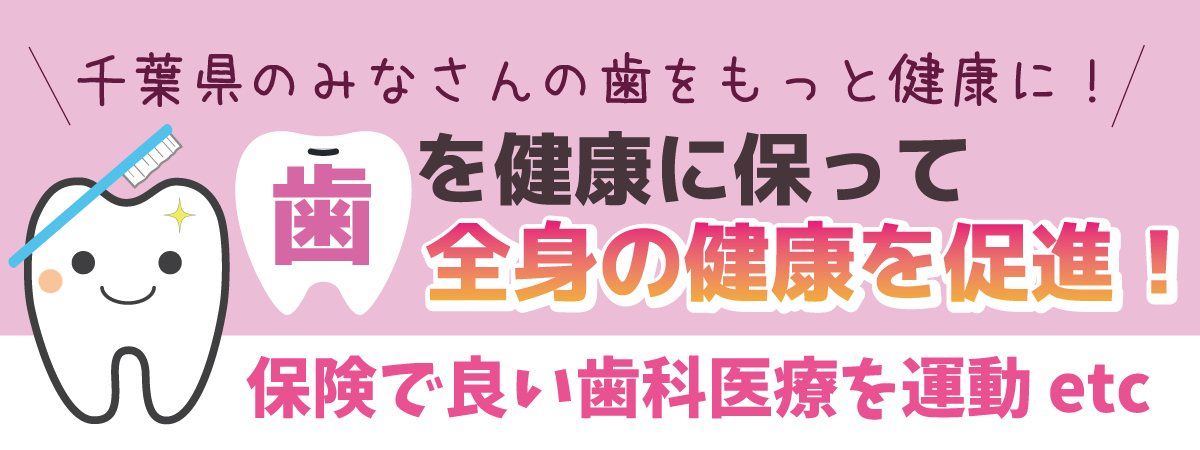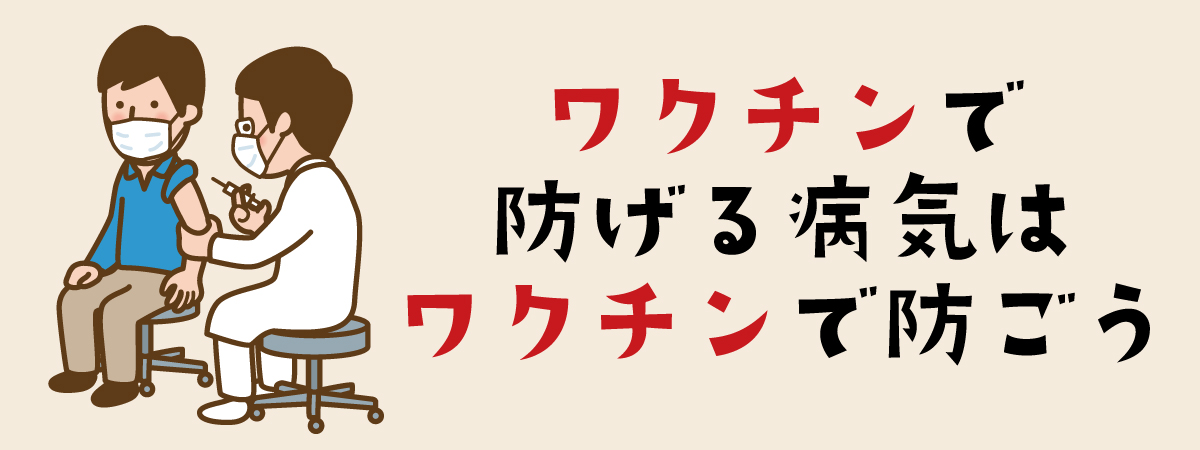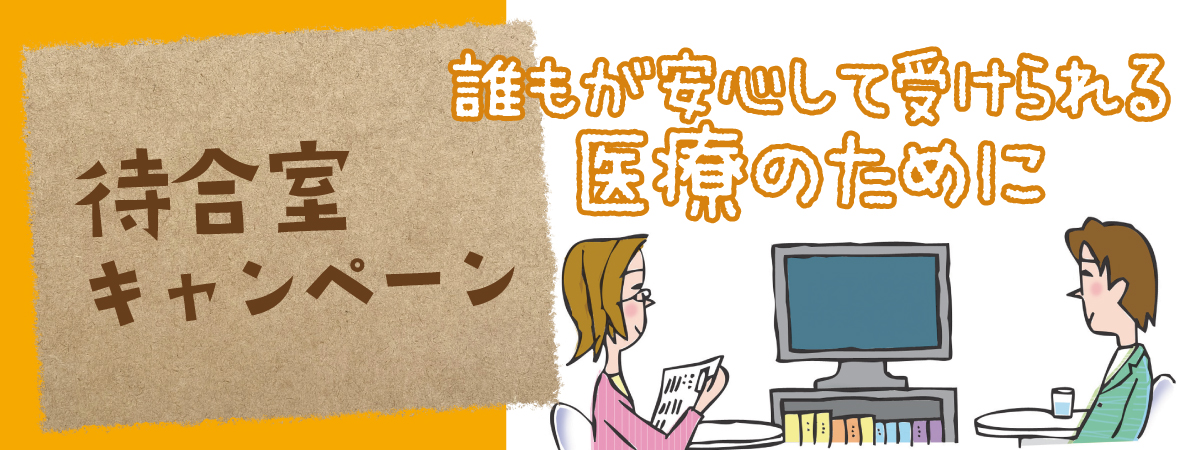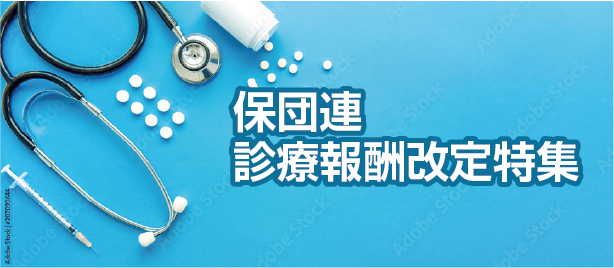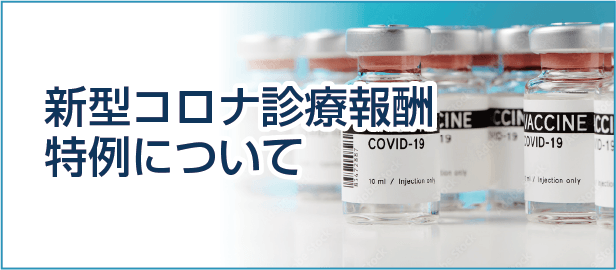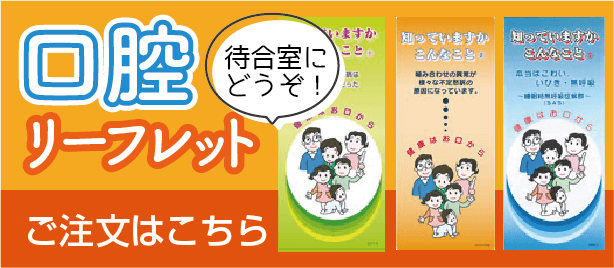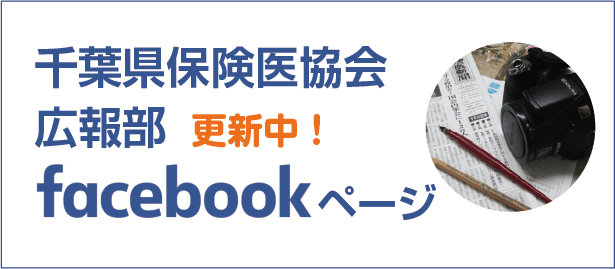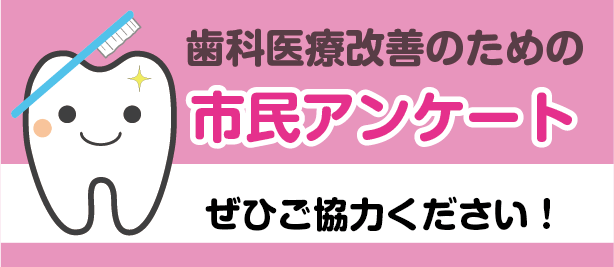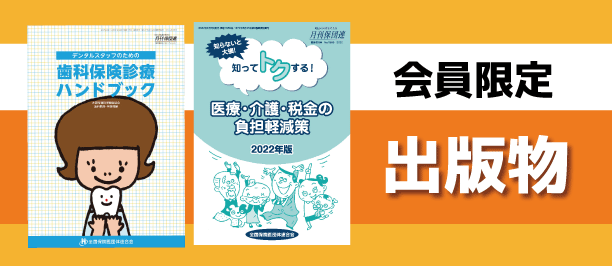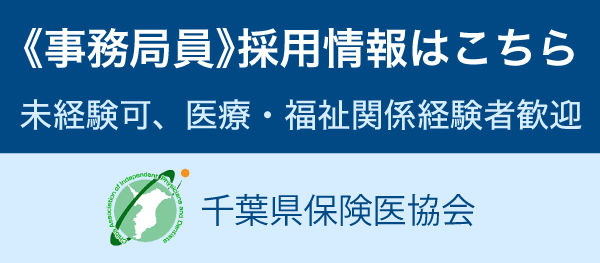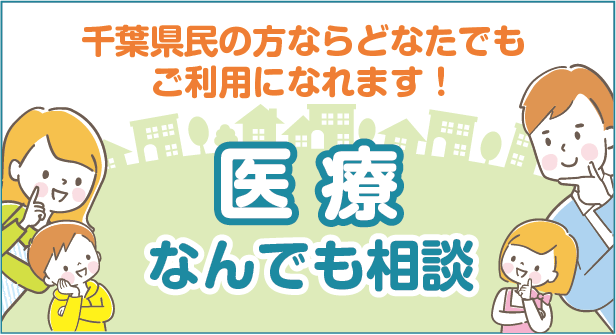千葉協会からも164人が原告として加わった「オンライン資格確認義務不存在確認等請求訴訟」の判決が、11月28日東京地方裁判所(岡田幸人裁判長)で言い渡され、原告の請求を棄却する『不当判決』を下した。
◆療養の給付(健康保険法63条1項)には『資格確認』についての記載はない
原告は、保険医療機関にオンライン資格確認を療養担当規則で義務付けたのは、健康保険法70条1項による授権の範囲を超えているとして、違憲無効であるとしたが、判決文では健康保険法70条1項が「療養の給付を『担当』しなければならない」としているのは受給資格の確認を省令等に委任していることが明確な児童福祉法21条や生活保護法50条1項等が「医療を担当しなければならない」としていることと同様であるとした。
しかし、療養の給付に関しては健康保険法63条1項において、具体的医療サービスである診察、薬剤処方、処置手術、他細目が限定して規定されており、その中には『資格確認』についての記載はない。医療給付を『担当』するという規定の中に『オンライン資格確認』まで含まれるというのは乱暴な法解釈である。
そもそも医療給付を受領する資格の確認の事務は保険者の当然の義務であり、被保険者も一旦住民登録等の正規の手続きをすれば健康保険証が自動的に送られ、被保険者の診療に先立つ当然の前提条件とされてきたものでしかない。これまで療養の給付に関してオンライン資格確認の様に支障を来すことはなかった。
◆閣議決定による違法なオンライン資格確認義務化について合理的な説明できず
今回の判決で違法な閣議決定されたオンライン資格確認義務化について、裁判長は原告の訴えについて合理的な否定もせずに(できず)、国の主張をそのまま採用しており、その判断は不当であるといわざるを得ない。
また、原告が平成25年最判を援用し、「委任命令によって制約されるべき権利利益の性質やこれに対する制約の範囲及び程度が大きいことに鑑みそれとの相関関係において、必要とされる授権規定の明確性の程度がより高くなる」と主張したことについて、『オンライン資格確認義務化は診療行為そのものを規制しない』、『免除規定がある』、『財政支援が行われている』を挙げて、本件に妥当しないとした。
◆判決は厚労大臣の裁量権を根拠無く広く認めるもので、現場感覚からかけ離れたもの
この論拠として、医療機関が受ける制約に比べて、オンライン資格確認の導入で得られる利点の方が大きいと根拠もなく断定した。
理由として『過誤請求ないし不正請求を防ぐことが相当程度期待し得る』、『情報共有等で医療の質の向上も期待できる』などを挙げている。医療DX行程表に示すインフラ整備が不十分である状況を顧みずに、拙速に閣議決定だけで進め、厚労大臣の裁量権を根拠無く広く認めることは現場感覚からかけ離れたものであると言わざるを得ない。更に、原告が示したトラブル事例や廃業を余儀なくされた事例について、「特定の団体内の意見」「回答率も必ずしも高くはない」と調査結果を直視しない姿勢は、国に忖度した不当なもので到底容認できるものではない。
◆拙速なオンライン資格確認義務化は国民の受療権や医療アクセスを侵害する
千葉協会は、今後控訴審においてもオンライン資格確認義務化による医療機関の権利利益の制約が甚大であることを主張し、同時に拙速に進めるマイナ保険証の不合理性を指摘し、国民の受療権や医療アクセスが侵害されないようなシステム構築を求めていく。当面は、各保険者に資格確認書を全被保険者に発行するよう要請する。
以上