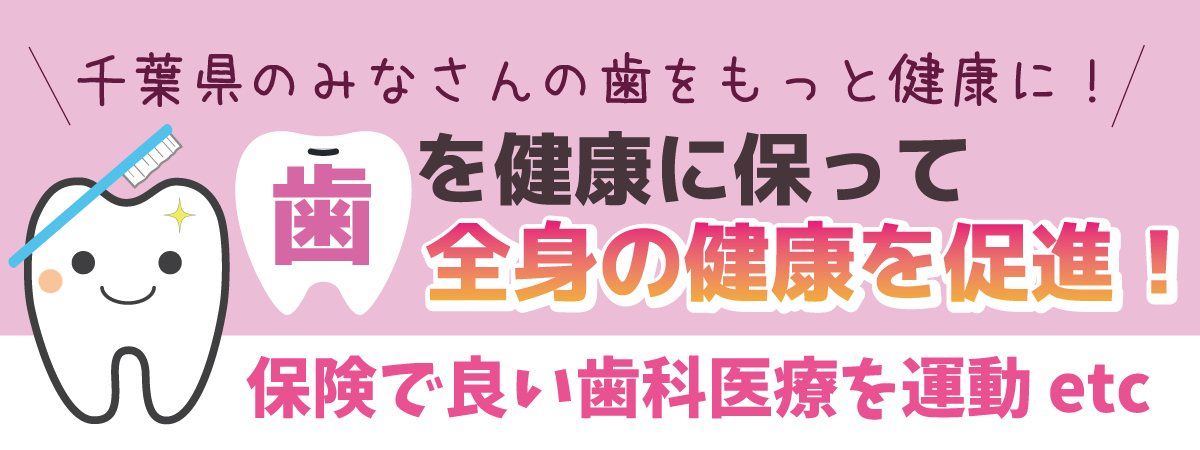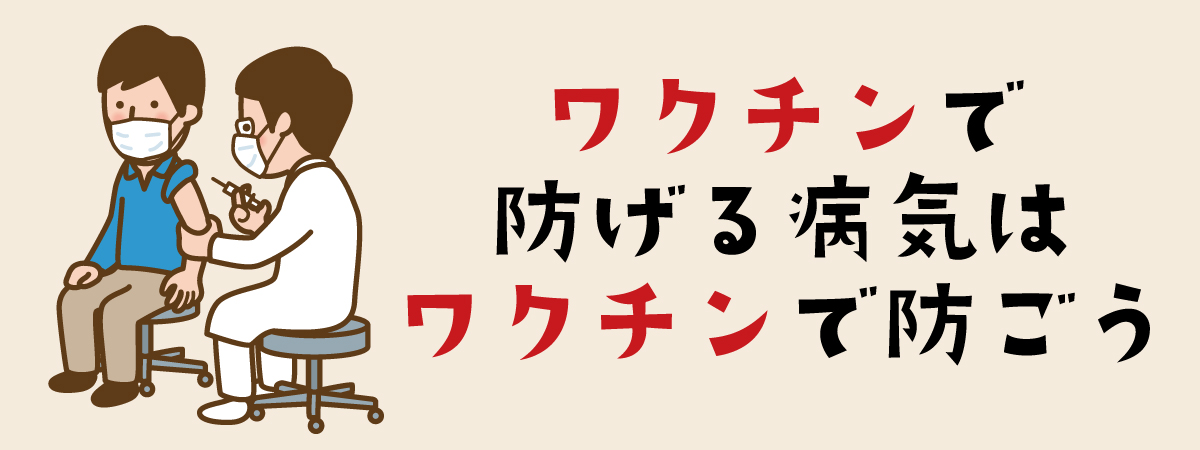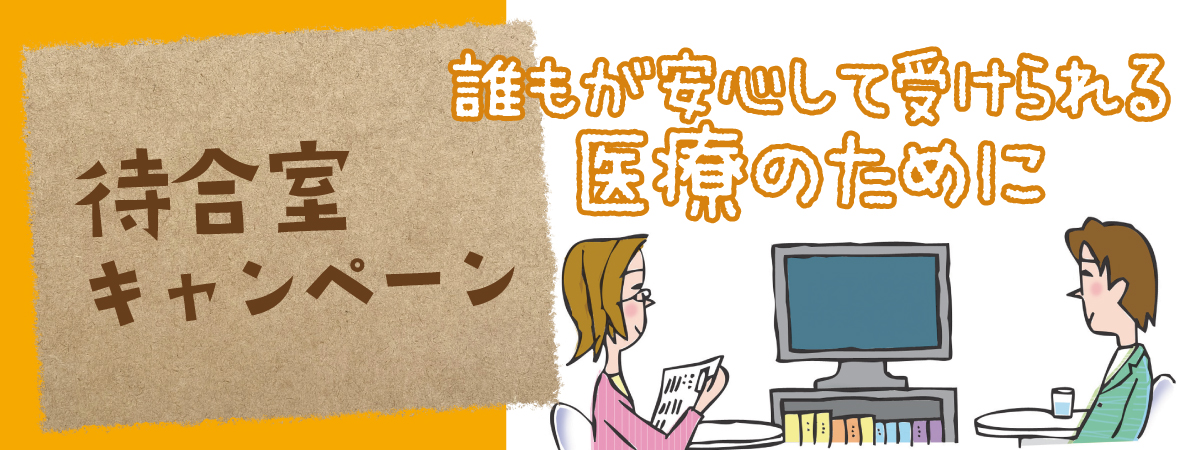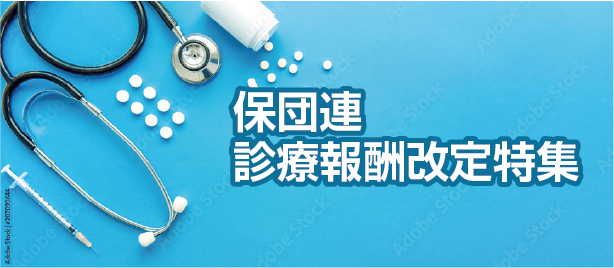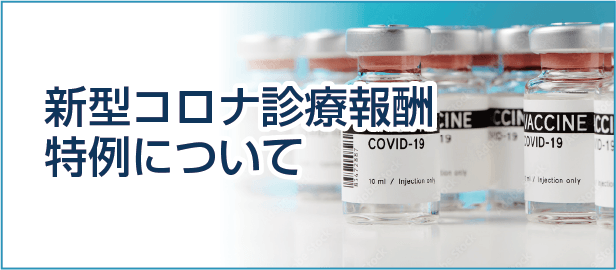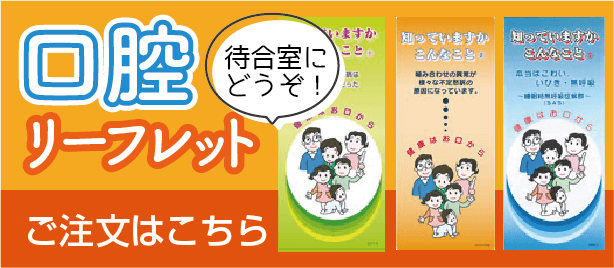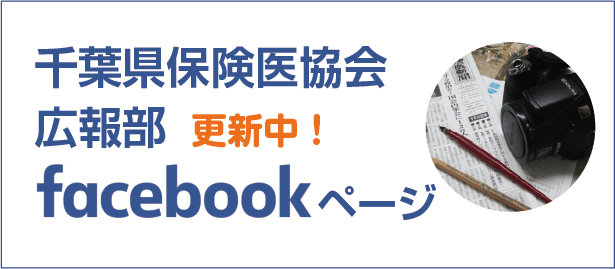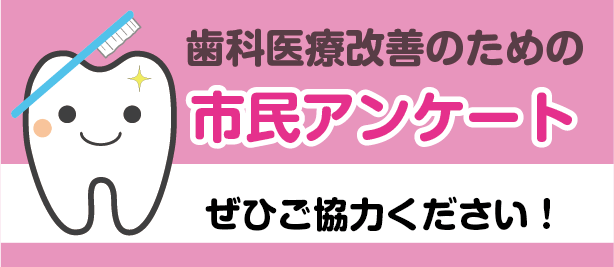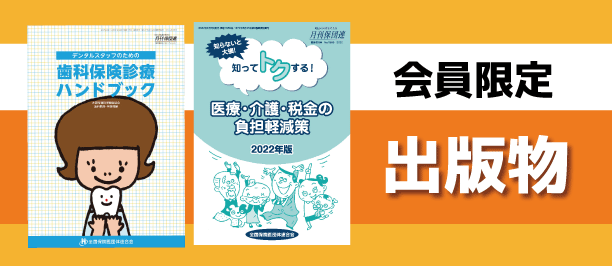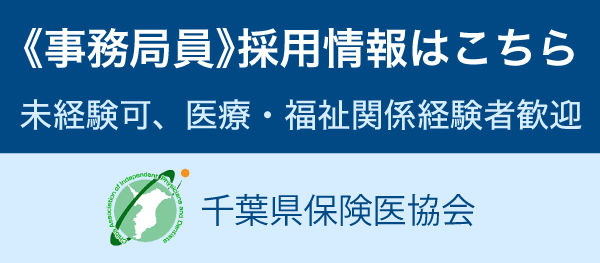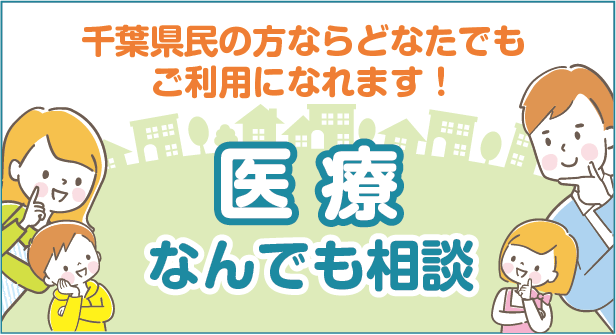~命綱を断ち切るようなことはやめて治療できる制度を~
患者が支払う医療費負担限度額(高額療養費制度)を今年8月から段階的に引き上げる「見直し」について、2025年政府予算案に盛り込まれ、国会での審議が行われています。
今回の負担限度額引き上げはすべての年代、すべての所得階層が対象とされており、文字通り高額療養費制度を利用する1250万人全員に大打撃となります。その引き上げ額も70歳未満の現役世代の年収650万円から770万円の階層では、最終的に1.7倍(2027年8月から)、5万円もの大幅な負担増です。
21日の日経新聞によると、医療費の1カ月あたりの患者負担に上限を設ける「高額療養費制度」の利用者を分析した東大の調査結果を示し、現役世代でも4割は長期治療の人であったことを報じています。高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に一定の歯止めを設けるもので、特に長期療養する場合には、直近12カ月以内に3回、自己負担の限度額に達した場合、4回目から限度額を下げる「多数回該当」という仕組みを導入し、万一の大病でも安心して治療が継続できる命綱をとなっています。
全国保険医団体連合会が子どもをもつがん患者の団体「キャンサーペアレンツ」有志と共同で行った調査では、半数が病気で収入が減る上に、治療(年50万~100万円が4割)と子育てにお金がかかり、現状でも家計は厳しい。これ以上医療費の負担が増えれば、5割が「治療中断」6割が「治療回数減」を考えると回答しました。子どもの進路変更も検討しなければならない状況に追い込まれるとの回答も5割に及んでいます。高額療養費制度は、がん患者をはじめ重篤な患者にとってまさに命綱であり、今回の制度「見直し」は、それを断ち切るに等しいものです。また、高額療養費制度を利用したことがない国民であっても、思いがけず大病を患い高額な医療費を負担する必要が生じることはどの世代にも起こり得ます。
厚労省は、今回の制度「見直し」を決定するにあたり制度利用者の収入減少、医療費支出、受診抑制を含む影響など、実態調査をまったく実施していません。患者団体などの声に押されて、福岡厚労大臣は21日の衆院予算委員会で、上限引き上げによって見込む医療費削減額のうち受診控えによるものが1950億円との試算を示しました。そもそも重篤な疾患で治療を継続している患者にさらなる負担を強いて、財源を捻出するという手法そのものが社会保障の概念とは相いれないものであり、公的医療保険の仕組みを根幹から突き崩すものです。
全世代に打撃となる高額療養費制度の「見直し」は直ちに撤回すべきです。
以上