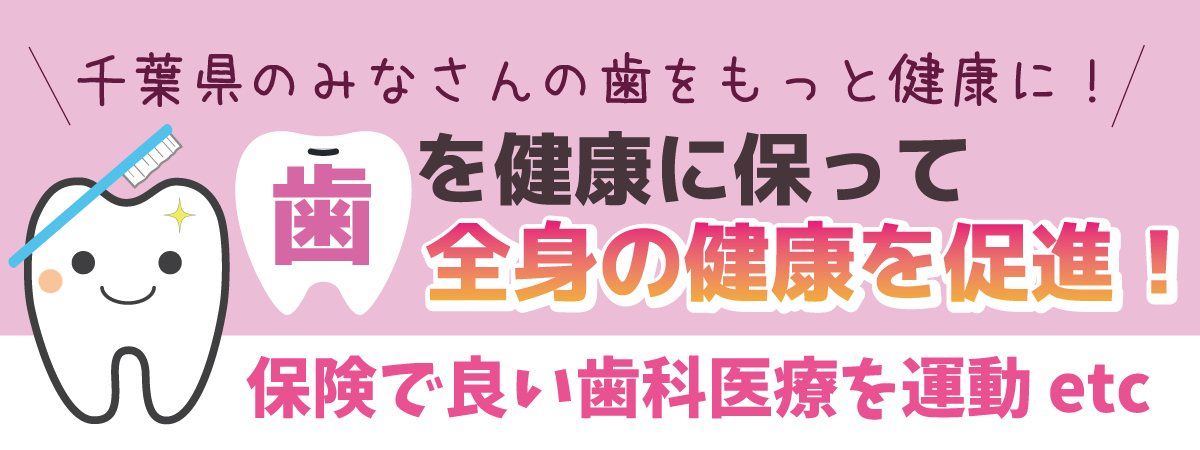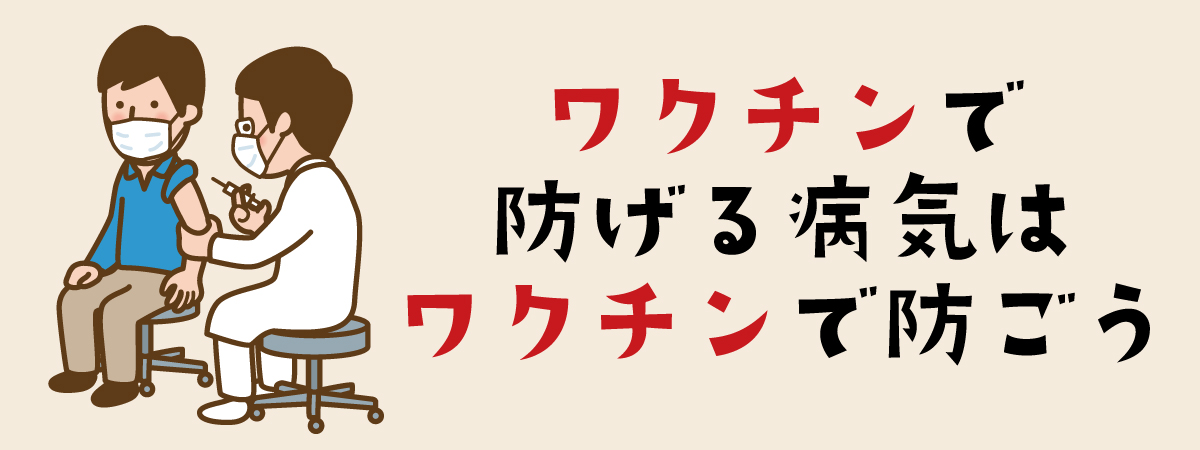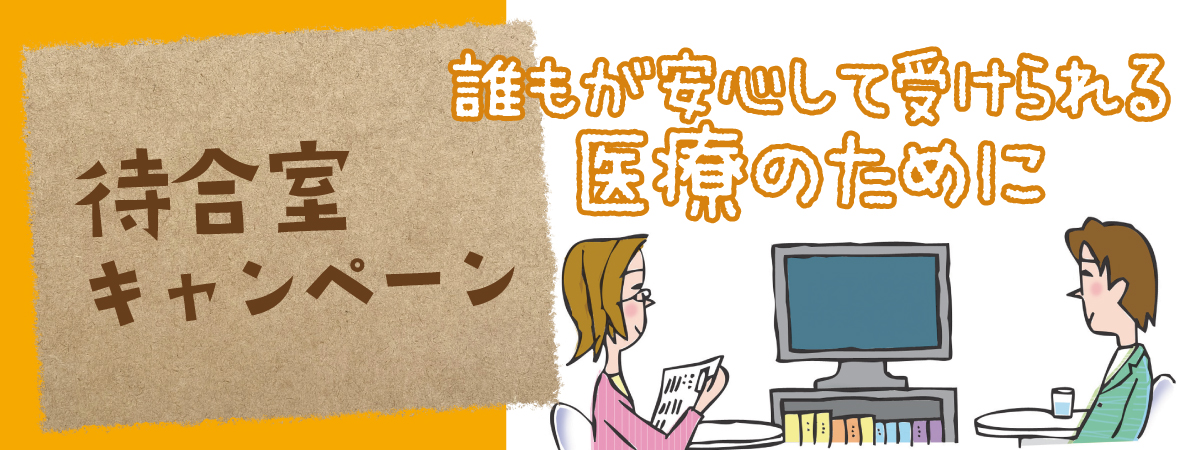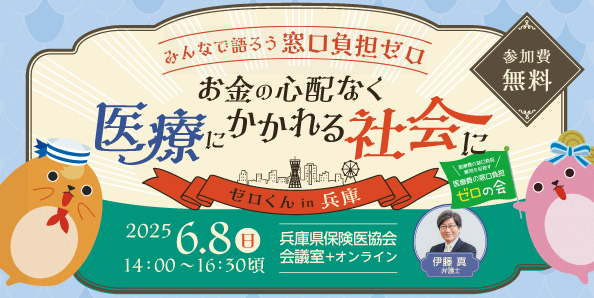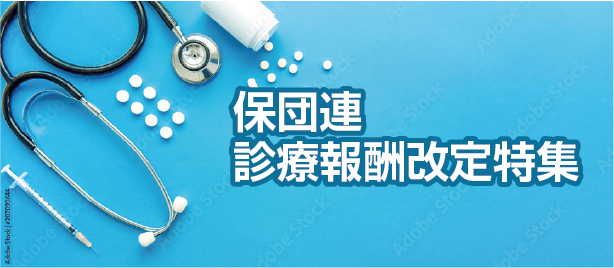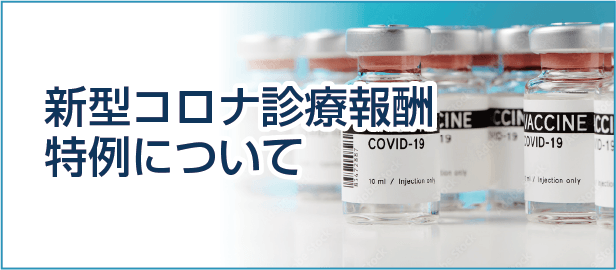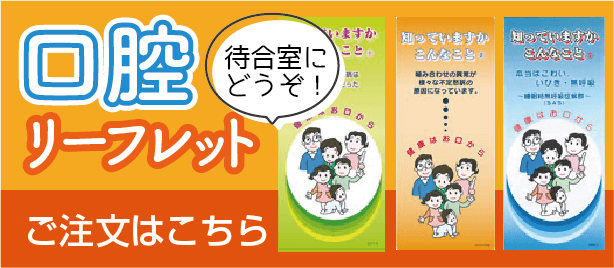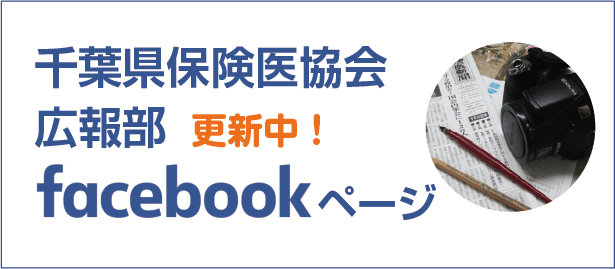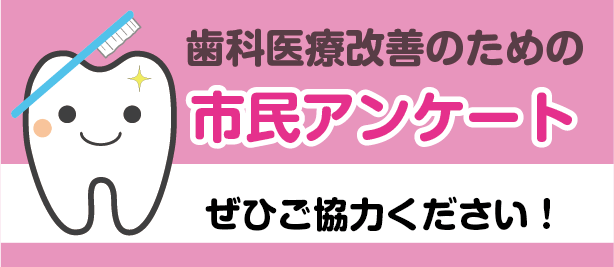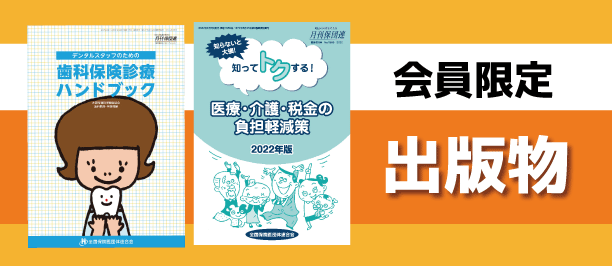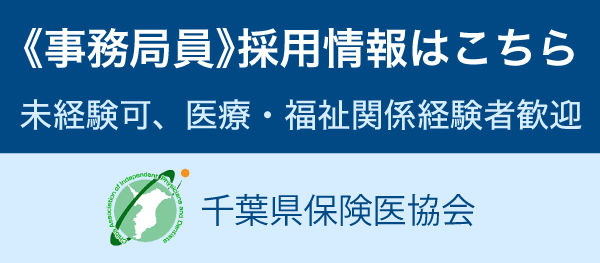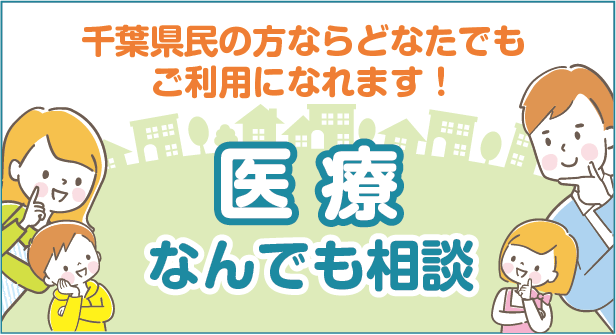声明・主張・談話
- 2022.06.19 第51回千葉県保険医協会定期総会決議
わが国が新型コロナウイルス感染症のパンデミックに見舞われ、2 年半が経とうとしている。昨年の今頃は感染防止に欠かせないマスクや防護具が枯渇し、多くの開業医は手作りのビニールガウン等で自身を覆い、必死に診察する姿があった。今年に入り、世界的にはワクチン接種が加速度的に進み、新たな局面を迎える中で、わが国のワクチン供給は周回遅れとなり、すべての国民へのワクチン接種が滞り、未だに生活に不安を抱き不自由な生活を強いられながら、新型コロナウイルスと対峙している。
現在、第7波感染拡大で収束の兆しが見えない中でも、岸田政権は「新自由主義」路線を継続し、経済最優先、医療、社会保障を蔑ろにする政策を踏襲している。「75 歳以上の窓口負担2割化」についても本年10 月実施を強行する予定である。多くの高齢者が感染を恐れ、受診控えや定期的な健診の遅れも増える中で、医療費の負担増により更に受診を手控えることは、一層の健康悪化につながるものである。また地域医療を担う開業医の経営もコロナによる受診抑制により逼迫し、回復の見通しが立たず閉院を決断せざるを得ない状況も散見され、医療機関への経済的な支援は喫緊の課題である。
更に私たちは命を守り平和を願う医師・歯科医師の団体として、国連「核兵器禁止条約」の発効に賛同し、今後も核兵器廃絶に向けて努力を続けていく所存である。
我々は第51 回定期総会にあたり、今年度も国民皆保険を守り、すべての国民が尊厳を保って幸せに暮らせる社会の実現を目指し、次の事項に全力で取り組むことを決議する。
記
一、 10%以上の診療報酬(特に基本診療料)引き上げと不合理是正を行い、同時に介護報酬の引き上げも行うこと
一、 保険でより良い歯科医療を実現するため、歯科医療費の総枠拡大を行い、歯科技工士や歯科衛生士等の歯科医療従事者の待遇改善を図ること
一、 金銀パラジウムの逆ザヤを生まない制度にすること。
一、 安全に医療を提供するため、医療従事者の労働環境の改善を図ること
一、 国庫負担を増やし、過重な保険料負担や窓口一部負担を大幅に軽減し、新たな患者負担増を行わないこと
一、 審査、指導、監査については保険医の人権と裁量権を尊重すること
一、 感染症、災害、救急、周産期、小児、難病、障害者等の行政的医療を維持できなくなる組織改革はやめ、公立、公的病院の拡充等の支援を行うこと
一、 地域環境の変化による新興、再興感染症に対する体制を充実すること
一、 世界標準のワクチンを希望するすべての人たちに、無料で安心して接種できる体制(日本版CDC、ACIP)を構築すること
一、 消費税損税となっている保険医療にゼロ税率を適用すること
一、原発ゼロをめざし、再生可能エネルギー中心の政策に転換すること
一、唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約を批准すること
一、憲法9 条、25 条などを有する日本国憲法を遵守すること
2022 年6 月19 日
千葉県保険医協会第51 回定期総会
- 2022.06.08 マイナンバーカードの保険証利用等に係る システム導入の義務化に強く反対する
内閣総理大臣 岸田 文雄 殿
厚生労働大臣 後藤 茂之 殿
総務大臣 金子 恭之 殿
デジタル大臣 牧島 かれん 殿厚生労働省は5月25日に開催された社会保障審議会医療保険部会において、2023年4月から保険医療機関でオンライン資格確認のシステム導入義務化と、2024年度中を目途に保険者による保険証発行の選択制の導入、保険証の原則廃止を目指す方向で検討を開始した。「経済財政運営と改革の基本方針」(骨太の方針)においても同様の方針が示され、マイナンバーカードの保険証利用のペースを上げるため国は強制的な手法を取ろうとしている。
国民皆保険の日本では、医療へのアクセスと健康保険へのアクセスは実質的に同一である。保険証が原則廃止ともなれば、マイナンバーカードを持たない者は、健康保険による診療が受けられなくなるので、保険診療を受けたい場合マイナンバーカードを取得せざるを得ない。これはマイナンバーカード取得の実質義務化である。マイナンバーカード取得は法律上任意とされているので、明らかに法律に抵触するのみならず、マイナンバーカード取得を医療へのアクセス条件にすることは、憲法25条で規定された生存権を脅かすもので容認できない。またマイナンバーカードの保険証利用により、マイナポータルに集積された診療情報の閲覧が可能になる。しかし近年、ランサムウエア感染をはじめとするサイバー攻撃のリスクは格段に上がっている。患者の医療情報の漏洩リスクなどプライバシー侵害の問題が何ら解決されていない。
オンライン資格確認は導入コストのみならず、一定のランニングコストを医療機関が負担する。これらの財源を手当てせずに、国が一方的な「義務化」を強要することは、過去にレセプトのオンライン請求を「義務化」しようとして、医療現場に大混乱を招き失敗した歴史から何も学んでいないと指摘せざるを得ない。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対応で疲弊した医療現場に、オンライン資格確認システム導入の義務化を押し付けるのは現場無視も甚だしいと言える。
患者・国民の命と健康を守る医師・歯科医師の団体として、政府・厚労省に対して、医療機関におけるマイナ受付等に係るシステム導入の義務化、保険者における保険証発行の選択制導入や保険証の原則廃止などについて中止・撤回することを強く求めるものである。
- 2021.11.13 HPVワクチン積極的勧奨「再開」の決定を歓迎する ~子宮頸がんからすべての女性の命と健康をまもるために~
千葉県保険医協会はこれまで「ワクチンで防げる病気からすべての人を守る」ために、世界標準のワクチンを費用負担なく、無料で安心接種できる環境を求めて、患者会の皆さんと一緒に定期接種化を求める活動を推進してきました。
そうした中、昨日11月12日開催の厚生科学審議会(予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会)において、ついに「HPVワクチンの積極的勧奨再開」が決まりました。当会は2013年6月以降、8年以上にわたり差し控えられていたワクチン接種の積極的勧奨がようやく再開されることを歓迎します。これまで実現に向けて取り組まれた関係各位には心より感謝と敬意を表します。
今後は国、自治体に対し以下の点を強く求めます。
①8年間でHPVワクチンの接種機会を逃した対象者へのキャッチアップ接種(経過措置)の実施
②カバー率の高い9価ワクチンを適正な価格とし、速やかに定期接種へ切り替えること
③男子への接種に早急に取り組むこと。
④ワクチンの安全性と有効性について科学的な根拠に基づいて情報の提供を行うこと。
⑤医療機関と連携して接種後の健康被害を呈した方への治療や相談、支援体制を強化し、社会的な補償の充実も求められる課題となっています。
- 2021.09.29 感染症対策実施加算の継続等を強く求める
政府は、感染症対策に関する外来・入院時の特例加算を9月末で打ち切り、10月以降は補助金で対応する方針を示した。乳幼児への外来特例は点数を引き下げ半年延長する。多くの医療関係団体が加算継続を要望する中、特例措置を終了させたことに抗議するとともに、下記の通り診療報酬加算の継続を強く求める。新型コロナウイルスは、無症状でも感染力を有し、接触・飛沫対策に加え、エアロゾルへの対応が求められる。こうした特性を踏まえ、今年4月より感染拡大防止を図りつつ日常診療を継続するすべての医療機関等を対象に感染症対策実施加算が措置され、不十分ながらも感染対策への人的・物的経費を補う役割を果たしてきた。地域の医療機関は、変異を繰り返し、感染力を増す新型コロナウイルスと対峙し、心身ともに疲弊しながらクラスター発生等を防止してきた。新規感染者数は減少したものの、秋冬の第6波に向け、感染拡大防止対策の継続は必須であり、医療従事者の努力に報いるためにも加算継続は不可欠である。政府は、年末までの感染対策として、補助金(無床診療所8万円、病院・有床診療所10万円)を追加給付するとした。しかし、当面する感染対策の経費として不十分であり、これまで措置された補助金の執行も大幅に遅れている。迅速・簡便な診療報酬による対応の継続を強く求める。記一、外来等感染症対策実施加算、入院感染症対策実施加算を10月以降もそのまま継続すること。―、乳幼児感染予防策加算は引き下げず、継続すること。
さらに、歯科においては医科と同点数へ引き上げること。
- 2021.08.19 【会長談話】「黒い雨訴訟」上告断念を歓迎し、 被爆者全員の早急な救済を求める。
菅義偉首相は7月27日、広島県のいわゆる「黒い雨」訴訟の原告に対し、広島高裁の判決に上告しない旨の談話を発表し、上告期限の7月29日に原告勝訴の判決が確定した。
黒い雨訴訟は原爆投下後に放射性物質を含んだ「黒い雨」を浴びて、健康被害が生じた広島県広島市や安芸太田市の住民84人が原告となり、「被爆者健康手帳の交付申請却下処分」の取り消しを求めた訴訟で、一審に続き、原告全員を被爆者と認め、被爆者健康手帳交付を命じる判決が7月14日に出ていた。
この判決に対し、広島県と広島市は上告しない意向を示したが、国は「科学的な知見に基づいていない」、「被爆者援護法の枠組みを大きく壊すもので、看過できない」などとし、被告が上告しないと表明しているにも関わらず、補助的な立場で裁判に参加した国が上告を求めるという異例な状態であった。
国が上告断念を迫られたのは高裁判決後、全国で判決支持の声が高まり、「黒い雨」による被爆者の長年に渡る願いと苦しみに国民が心を寄せたことである。
一方で、談話は「今回の判決には過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点があり、政府として本来は受け入れがたい」とし、判決で示された汚染した飲食物の摂取による「内部被曝」による健康被害も広く認めるべき、との指摘には「容認できるものではない」とした。
菅首相は会見で「黒い雨」訴訟の原告と同様の被害者に対しても「訴訟への参加・不参加にかかわらず、認定し救済できるよう早急に検討する」と述べた。千葉県保険医協会は国の責任において救済するという姿勢を評価するとともに、今回、否定された「黒い雨」の援護対象区域の抜本的見直しや被爆者認定の枠組みを抜本的に改め、「黒い雨」により被爆したすべての人々の救済が早急に実現することを願うものである。
- 2021.06.17 【理事会声明】歯科医師による新型コロナワクチン接種は 法的な根拠を担保してから実施すべき
厚労省は4月26日付で事務連絡を出し、歯科医師による新型コロナワクチン接種のための筋肉内注射の実施について、法的な整理を示した。
その事務連絡が発出されて以降、全国各地で実技研修が行われ、接種の迅速化の一手段として全国紙および各種メディアからの報道が続いている。歯科医師の間では少しでも社会に貢献できるのなら協力したいとの前向きな意見がある一方で、万一の医療事故に対する責任の所在や法的な根拠はどうなのか、と心配する声も聞かれている。
歯科医師法第1条は歯科医師の任務を「公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保する」と規定している。新型コロナウイルス感染症が国民の生命と健康を脅かす中で、その対策に参画することは歯科医師としての職業的使命でもあり、必要に応じて安全性を担保してのワクチン接種への協力を惜しむものではない。しかし、新型コロナワクチン接種の体制確保は、ワクチンの開発・供給を巡る動向の中で充分に想定しえた課題である。厚労省が、円滑に対応できるよう予め法律による対応に動かず、人材の逼迫が起こってから緊急避難的に解釈する対応をとったことには問題がある。
事務連絡は、ワクチン接種のための筋肉内注射は医行為に該当し医師法第17条に違反するとした上で、3点の条件(①歯科医師の協力なしにはワクチン接種が実施できない、②歯科医師に筋肉内注射の経験があるか必要な研修を受けている、③被接種者の同意)を満たす場合、「公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、医師法第17条との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる」とし、集団接種会場に限り、医師の監督下で歯科医師によるワクチン接種の筋肉内注射を可能とした。これは歯科医師によるPCR検査の検体採取についての法的整理と同じ手法でである。
歯科医師による新型コロナワクチン接種については、PCR検査の検体採取以上に深刻なリスクを伴うことは明らかであり、検討には一層の慎重さが求められる。それにもかかわらずPCR検査の検体採取と同様に行政解釈により歯科医師の実施を可能とすることは不適切である。本来的には国会審議を通じて必要性と安全性について広く合意し、立法により適法性を確保した上で実施させるべきものであり、単なる事務連絡で済ませられるような話ではない。
医師法の定めを超えて歯科医師の協力が必要と判断するのであれば、責任を現場任せにして解釈と条件だけを示すのではなく、法律を根拠に実施できる条件を整えることが行政の責任である。ワクチンが必要な国民に円滑に行き渡るようにするとともに、これからも起こりうる緊急事態への対応に協力する歯科医師の法律上の位置づけを明確にするよう厚労省の責任ある対応を求める。
- 2021.05.13 75歳以上窓口負担2割化衆議院強行採決に抗議する ~新型コロナウイルス感染拡大の下、負担増をなぜ続けるのか~
5月11日、「75歳以上の医療費窓口負担2割化」などを内容とする健康保険法等の一部改正案が自民、公明、維新、国民民主の各党の賛成多数で採決・可決された。首都圏を中心に3度目の緊急事態宣言が出され未だに収束の兆しが見えない最中、コロナ対策を優先課題とし、それらの審議に注力する時期にもかかわらず、国民に更なる痛みを強いる「窓口負担2割化」法案をわずかな審議時間で採決を強行したことに対し、当会として政府に厳しく抗議する。
今後、審議の舞台は参議院に移ることになるが、今国会で徹底審議の上、廃案を求める。
政府は衆議院審議において、政令で2割負担の対象とする単身世帯「年収200万円以上」(課税所得28万円以上)、夫婦世帯「年収320万円」(所得が多い方が同28万円以上)について「負担能力がある」と繰り返し答弁していたが、負担増による受診控えを見込んで給付費を年1,050億円も削減できると推計している。菅義偉首相は、受診控えの影響額も踏まえず「直ちに健康に影響しない」と無責任な答弁に終始したが、過去の負担増が平均寿命の押し下げにつながったという学識者の指摘もあり、抑制効果が大きく出ることも明らかになっている。
また田村憲久厚労相が「誰かが負担しなければならない」と居直る一方、参考人として意見陳述(4月20日)した日本福祉大学の二木立・名誉教授は「医療に受益者負担を適用すべきではない」として、税・保険料で「応能負担」を求めるべきだと強調した。負担増は大企業・富裕層にこそ求めるべきである。
この間、私たちも取り組んだ「2割化反対」を求める国会請願署名は100万筆を超えた。コロナ感染症が依然猛威を奮い、日々の暮らしや健康への不安が高まっている中、さらに負担を押し付けることへの反対の声が高まっている。
いま政府、国会が全力を上げねばならないのは、国民の生活、生業の保障であり、病床や検査体制の確保、速やかなワクチン接種など医療提供体制を立て直すことであって、断じて「2割化」導入ではない。
私たちは、あらためて「2割化」に反対し、地域の患者・住民とともに成立阻止に向けた取り組みを進めていくことを表明する。
- 2021.04.15 デジタル改革関連5法案の衆議院本会議での採決に抗議する
【国会軽視も甚だしい】デジタル庁設置やマイナンバー利用拡大などを盛り込んだ「デジタル社会形成基本法案」をはじめとしたデジタル改革関連5法案が4月6日、衆議院本会議にて採決・可決された。デジタル改革関連6法案(自治体情報システム標準化法案含め)は、個人のプライバシー権などに多大な影響を孕むとともに、法案関連資料は2千頁以上に及び、十分に時間をかけた慎重な審議が求められている。にもかかわらず、法案関係資料で発覚した多数の誤りについて国会への報告は後回しにされた上、5法案を束ねて一括審議を求めるなど国会軽視の姿勢も甚だしいと言わざるを得ない。
【個人情報保護ないがしろに情報利活用】法案は、「個人情報」の定義(範囲)をより狭いものに変更した上で、個人情報保護3法を一元化し自治体独自の個人情報保護条例を実質上形骸化することなどを通じて、行政が持つ膨大な個人情報について企業等による利活用を大幅に推進する内容である。個人情報保護の理念・規定が決定的に欠落しており、本人の知らないところで、個人情報がやり取りされ、リクナビ事件に見られたような企業によるプロファイリングやスコアリングが野放図に拡大されていくことが懸念される。
【自治体独自の助成策の抑制・後退】また、法案では、自治体の情報システムの「共同化・集約の推進」「標準化」と称して、自治体の主要業務の情報システムを原則国が示す仕様に合わせるよう求めており、地域住民が築き上げてきた医療・介護・福祉等に関わる自治体単独事業や上乗せ・横出しサービスなどが抑制されることが強く危惧される。給付金支給や災害対応などを口実にマイナンバーと預貯金口座の紐付けを促す制度も盛り込まれている。「骨太の方針」が求める高齢者医療における金融資産に応じた患者負担増の仕組みの構築に向けて地ならしを進めるものである。
【官民癒着の強化、医療・社会保障削減に圧力】更に、マイナンバー利用拡大やデータ利活用を強力に進める司令塔として、首相をトップに据え、強い勧告権と巨額の予算を有するデジタル庁を創設するとしている。職員 500 人のうち100 人以上を民間企業より登用し、「デジタル監」は民間出身者を想定し、非常勤職員は兼業も許され、出身企業の給与補填も容認されるなど、政府と ICT 関連業界の癒着が一層強められ、巨大な利益誘導が図られることとなる。財源の負担は国民にしわ寄せされ、医療・社会保障費の更なる削減圧力が高まることも危惧される。 報道によれば、日本維新の会と与党の合意により、国と自治体の役割として「公正な給付と負担の確保」を加える法案修正がされるなど、医療・社会保障の削減を一層強める内容に改悪されている。 デジタル改革関連6法案については、個人情報保護規定の強化、自治体独自事業の存続・拡充の制度的保障、デジタル庁創設・マイナンバー利用拡大の撤回など抜本的修正がなされない限り、徹底審議の上で廃案とすることを強く求める。
- 2021.03.31 マイナンバーカードの保険証利用には強く反対し、無期延期を求める
厚生労働省は3月下旬より本格運用を開始するとしていたマイナバーカードの保険証利用について、社会保障審議会医療保険部会(3月26日開催)で本年10月まで運用を延期することを報告し、了承された。
この間、システムの本格稼働に向けて、3月4日より一部医療機関で試験運用が始まっていたが、資格情報の確認ができない等のトラブルが続出。同省によると、「加入者データの不備による資格確認エラー」「院内システムへの読み取りエラー」などを要因として挙げている。また、加入者データについては昨年10月以降、保険者においてオンライン資格確認システムへの登録が進められているが、「情報が登録されていない」と表示されるケースが相次いでいる。他人の医療情報が医療機関の端末に示される恐れがあり、正確な管理ができていない。極めてお粗末な事態と言わざるを得ない。
3月23日時点で試験運用を行っている機関は全国24都道府県54施設。そもそも500機関で開始する予定であった試験運用自体が大幅に遅れており、カードリーダーの申請件数は病院で60.4%、医科歯科診療所で36%程度。マイナンバーカードの健康保険証としての利用申請件数も現時点で311万件、総人口の2.5%にも満たない。これら運用システムやデーター不備、導入医療機関数、健康保険証利用申請件数などいずれを見ても、運用開始できる実質的な体制が整っていないことは明らかである。
政府は、運用日程ありきでオンライン資格確認システム導入の補助金事業等で医療機関に導入を急がせているが、このまま強引に運用拡大を進めても、現場の混乱は目に見えている。マイナンバーカードを健康保険証として利用させることは、医療現場に無用な混乱を招き、国民が安心して保険診療を受けることの障壁になると言わざるを得ない。
本会は、医療情報とマイナンバーの紐づけがなし崩し的に拡大される事態に繋がるマイナンバーカードの保険証利用には強く反対し、無期延期を求める。そして、関係機関は従前通り、健康保険証で医療が受けられることを広く国民に周知するよう関係機関へ求めていく。
- 2021.02.10 金パラ「逆ザヤ」解消と価格改定制度の抜本的な改善を求める
1月27日、中医協総会は歯科鋳造用金銀パラジウム合金(以下「金パラ」)の「随時改定Ⅰ」の実施を確認し、4月1日以降の金パラの告示価格は1g2,668円に決定された。現行価格の2,450円から218円の引き上げとなるものの、実勢価格と告示価格の間に生じる「逆ザヤ」の根本的な解決にはならない。
2018年夏から値上がりを始めた金パラ価格は、その後も高騰を続け、長期にわたり歯科医院を「逆ザヤ」問題で苦しめてきた。
全国保険医団体連合会が実施した「金パラ『逆ザヤ』シミュレータ」の千葉県分の平均購入価格(カッコ内は告示価格との差)は、2020年1月2,544円(▲869)、2月2,737円(▲1,062)、3月2,532円(▲857)、4月2,774円(▲691)、5月2,607円(▲285)、6月2,602円(▲282)、7月2,665円(▲3)、8月2,798円(▲136)、9月2,854円(▲192)、10月2,878円(▲428)となっており、その後も2,800円から2,900円の間で推移していると推測される。
2020年3月の中医協で随時改定Ⅱの導入が決定され、2020年7月には改定が実施されたものの、実勢価格と告示価格の乖離がほぼ解消されたのは上記のとおり7月のみである。2020年1月から10月までの「逆ザヤ」を平均すると1gで528円、30gで15,840円もの乖離が生じていることになる。告示価格を素材価格からの推計で算出している限り、実勢価格を下回る傾向が強いことがこの調査からも明らかである。
また、7月改定に係る参照期間である1月から3月の平均よりも、10月改定に係る参照期間の4月から6月の平均のほうが高いにもかかわらず、2020年10月はマイナス改定が行われたことになる。これらは現行の基準材料価格改定および随時改定の仕組みの中で発生する「タイムラグ」で説明がつくものではない。当会は、告示価格の改定にあたっては素材価格からの推計ではなく、合金の実勢価格を調査し、その結果を告示価格に反映することを求める。
さらに1月13日の中医協では、14カラット金合金の価格計算に誤りがあったことが公表された。多くの歯科医師が長期にわたる金パラの「逆ザヤ」問題により、歯科用貴金属の価格決定の根拠に不信感を抱いている中での失態であり、現行の価格改定制度への信頼はますます揺らいでいる。
厚労省はこの間、基準材料価格改定時に実施している特定保険医療材料価格調査の結果を非公表としてきた。現行の価格改定制度に対する信頼を取り戻すためにも、価格決定に関するデータやプロセスをすべて公表すべきである。また、「逆ザヤ」問題を早急に解決すべく、告示価格と実勢価格の乖離の実態を速やかに検証し、抜本的な制度改善を行うよう強く求める。
- 2021.01.26 核兵器禁止条約の発効を歓迎し、日本政府の批准を求めます
1月22日、核兵器の開発・製造・保有・使用等を禁じる歴史的な核兵器禁止条約が発効しました。千葉県保険医協会は、この条約の発効を心から歓迎し、長年にわたり条約の発効のために奮闘されてきた被爆者、そして核兵器廃絶と平和のために取り組まれてきた世界中の人々に改めて敬意を表するものです。
今回の発効によって、核兵器は国際的に違法化されました。条約の前文には、「核兵器のいかなる使用も人道の諸原則および市民的良心の命ずるところに反する」と明記、核兵器を人道や市民の視点から包括的に禁止することが謳われています。特に「核兵器による威嚇」にまで踏み込んで禁止、その意味で画期的なものであり、また、「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)(中略)にもたらされた容認しがたい苦難」と前文に「ヒバクシャ」の文言が盛り込まれ、被爆者に寄り添っていることも特徴です。
この条約に対して日本政府は、米国の核抑止力に依存し、「核保有国と非保有国、国際社会の分断をもたらす」として署名・批准を未だに行っていません。その姿勢は国内外から批判を浴びています。唯一の戦争被爆国として、こうした国際社会の大きな流れに背を向けることなく、核兵器廃絶へ向けた具体的なアプローチを行うリーダーとしての役割を果たすべき、と考えます。
国連のグテレス事務総長は、「この条約は核兵器のない世界という目標の実現に向けた重要な一歩」とした上で、「核兵器の使用がもたらす壊滅的な人道的、環境的被害を防ぐための緊急行動」の必要性を提示。「国連にとって核兵器の廃絶は軍縮分野の最優先事項」として各国に核兵器廃絶の実現に向けた協力を呼びかけました。
「戦争は最大の健康破壊」と言われています。健康を守る医師、歯科医師で構成する千葉県保険医協会は、核兵器が廃絶され核戦争の心配がない世界を望んでいます。今後、条約の締約国会議が行われていく中で、核兵器廃絶の道筋がつけられていくことを大いに期待したいと思います。
- 2020.12.10 75歳以上の窓口負担2割導入の自公「合意」に抗議する ~新型コロナウイルス感染拡大の下、負担増を続けるのか~
報道によれば、75歳以上の医療費窓口負担を原則1割から2割に引き上げることについて、年収200万円以上を対象にすることで自民党、公明党が合意したとされる。これが事実であれば、約370万人もの高齢者の窓口負担が2割になる。高齢者のいのちと健康を脅かす負担増をコロナ禍の下でも続ける自民党、公明党に強く抗議する。
新型コロナの教訓は高齢者ほど早期治療が大切
新型コロナの感染拡大が続く中、受診控えによる疾病・心身の状態悪化も多数報告されている。新型コロナ感染者で重症化する割合が高いのが高齢者である。さらに、高齢者ほど高血圧、糖尿病などの基礎疾患を抱えている。窓口負担の引き上げは高齢者の早期治療の機会を妨げることになる。
高齢者の負担割合は3分の1でも不公平ではない
そもそも75歳以上の年収に占める患者負担額の比率は、40代の3倍以上となっている。高齢者の負担割合が1割で、現役世代の3分の1であっても、決して不公平ではない。
現役世代の負担軽減は国庫負担の増額で
政府は現役世代の負担軽減を負担増の理由にあげているが、年収200万円以上を対象に2割負担を導入しても現役世代の負担軽減は年約880億円、一人当たり約800円の減額である。新型コロナ対策で投じた補正予算を考えれば国が負担できない金額ではない。
現役世代の負担軽減は、後期高齢者医療制度への国庫負担割合の引き上げを検討すべきである。
今、必要なのは、感染拡大の防止と医療体制の確保に全力を挙げるとともに、医療や介護の負担を軽減し、すべての人が安心して医療と介護が受けられるようにすることである。
75歳以上の医療費窓口負担2割導入の自公「合意」撤回を強く求める。
- 2020.10.27 核兵器禁止条約の批准50か国到達を歓迎する
10月24日(日本時間の25日)、17年7月に国連で採択された核兵器禁止条約をホンジュラスが批准し、批准国が50か国に到達、90日後にはこの条約が国際条約として発効することが決まった。千葉県保険医協会は、この条約の発効を心から歓迎し、長年にわたり条約の採択と発効のために奮闘されてきた被爆者、そして核兵器廃絶と平和のために取り組まれてきた世界中の人々に改めて敬意を表するものである。
75年前の1945年8月、広島・長崎に投下された原爆は、21万人を超える人々の命を奪い、生き残った人々も現在に至るまで身体的、精神的、社会的な苦痛を強いられてきた。この条約は、人類史に比類ないこうした状況をもたらした核兵器の開発、実験、製造、備蓄、移譲、使用、そして威嚇をも禁止する内容を持ったものである。さらに、「核兵器使用の被害者(ヒバクシャ)(中略)にもたらされた容認しがたい苦難」と被爆者に寄り添いつつ、「核兵器のいかなる使用も人道の諸原則および市民的良心の命ずるところに反する」と核兵器の非人道性を主張している。「核のない世界」を展望し、人類の未来に新たな光をもたらす条約と言って過言ではない。
一方、日本は、「現実の安全保障を踏まえたものではない」「核兵器廃絶へのアプローチが違う」として、この条約には参加しないままである。唯一の戦争被爆国である日本は、こうした国際社会の大きな流れに背を向けることなく、核兵器廃絶の世界のリーダーとして、その役割を発揮すべきと考える。
条約の発効は、核兵器を非人道兵器とする国際的取り決めの誕生となり、核保有国にも非核保有国にも大きなインパクトを与えるものである。今後、締約国会議が行われ、具体的な核兵器廃絶の道筋がつけられていくことを大いに期待したい。
- 2020.03.05 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策に関する緊急要望書
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿貴職におかれましては、国民医療の確保のために尽力しておられることに敬意を表します。 当会は、県内の医師・歯科医師 4180 人余で構成する開業医保険医の団体で、国民医療の充実をめざし様々な活動を行っております。 日本国内での COVID-19 の感染者が増加しています。千葉県での感染者数は16人(3/3 現在)となっており、感染拡大が懸念され、同時に医療機関への影響も広がりつつあります。 当会の会員からは「感染対策に必要なマスクや消毒用エタノールの供給が滞っている。北海道だけでなく、千葉県の医療機関にも供給してほしい」との声が寄せられています。 先日、日本臨床微生物学会が発出した「新型コロナウイルス(2019-nCoV)感染(疑いを含む)患者検体の取扱いについて」では医療従事者の個人防具として手袋、サージカルマスク、ゴーグル、アイシールド、ガウンの着用等で感染予防を行うこととし、呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させること等、標準予防策の遵守を周知しています。しかし、日常診療において、これら防護具による予防策は限界を迎えており、早急な対策を強く求めます。 また、こういった状況を鑑みれば、先月28日に貴職に要請した「2020 年診療報酬改定」への対応は難しく、4月からの実施は延期すべきです。以下、COVID-19 対策を要望いたします。
記
[要望項目]
① 医療機関や高齢者が多い介護施設に対しては診療に必要なマスクおよび防護具、消毒薬等優先的に供給すること。また万一、休業した場合の所得補償を行うこと。
② 治療薬やワクチンの早期開発に向けて研究開発費等を早急に予算化し実施すること。
③ 2020 年診療報酬改定は市場価格が急騰している材料価格の改定を除き、実施を半年間延期すること。そのうえで、延期した診療報酬改定分は補填をすること。
④ 2020 年 3 月 31 日に到来する施設基準の経過措置期限の延長をすること。
⑤ 感染症危機管理体制の強化、並びに健康医療情報を学術的な見地から国民に発信し情報共有ができる「日本版CDC」を創設すること。以上
- 2020.03.05 歯科鋳造用金銀パラジウム合金の「逆ザヤ」解消にはほど遠い基準材料価格改定に強く抗議する
厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
3月5日、2020年診療報酬改定点数および基準材料価格等が告示され、歯科鋳造用金銀パラジウム合金の告示価格は1g2,083円に決定された。 現告示価格30g50,250円から62,490円と12,240円の引き上げにとどまり、全く「逆ザヤ」を解消できる価格ではない。歯科医院の窮状に目を背け、抜本的な改革を怠ってきた厚労省の不作為に対し、厳重に抗議する。 2018年9月以降、金銀パラジウム合金の市場価格が高騰を続ける中、歯科医院は告示価格を大幅に上回る価格での購入を余儀なくされ、1年半もの間「逆ザヤ」に苦しんできた。 当会の会員から寄せられたアンケートによると、金銀パラジウム合金の購入価格(税込)の平均は2019年9月54,511円(▲10,711円)、10月58,743円(▲8,493円)、11月59,806円(▲9,556円)、12月63,029円(▲12,779円)、2020年1月69,630円(▲19,380円)、2月74,463円(▲24,213円)と急激な価格上昇である。同期間内での購入最高金額は93,170円(2020年2月)で、42,920円もの「逆ザヤ」である。今回の告示価格30g62,490円では逆ザヤを解消するどころか、更に継続して赤字を負わせるものであり、断じて容認できない。 厚生労働省はいつまで歯科医院に困難を強いるつもりなのか。直ちに「逆ザヤ」を解消するよう強く要求する。 また、現行の基準材料価格改定および半年ごとの随時改定の仕組みの下では、歯科医療保険制度が健全に発展していくことはもはや不可能である。「逆ザヤ」を生み、歯科医院を追い詰める制度は徹底的に見直しを行い、抜本的な解決手段を講じること重ねて要求する。
- 2019.11.21 「科学的言論を封じる名誉棄損訴訟」控訴審判決に対する見解
⑴医師でジャーナリストの村中璃子氏の一審敗訴が取り消されたことは大いに歓迎する。今後、村中氏が執筆活動を再開され、活躍されることを期待する。
⑵池田氏の不適切な発表が、「データの捏造」ではなかったとして、科学的に根拠のないまま結論を導き出したことに対して捏造ではないとされたことは到底受け入れられない。
⑶一例のデータに基づき結論を出し、「不適切な発表により国民に対して誤解を招く事態となったこと」は科学者および国民の常識からすれば「研究結果の捏造」と言われても仕方がないと考える。
⑷「不適切な発表により国民に対して誤解を招く事態となったこと」は真に遺憾であり、捏造と批判されて当然と考える。したがって、上告審においても村中氏を支援していくこととする。
⑸池田氏の不適切な発表は、仮に捏造と認定されなくとも、研究者として到底許されるものではなく、今後もこれを批判していく。
⑹池田氏の不適切な発表などにより、HPVワクチンの積極的勧奨が中断していることは非常に残念である。年間一万人が子宮頸がんに罹患し、三千人が亡くなっている悲惨な現状を克服するため積極的勧奨の再開を求めて運動をしていく。以上